自宅をペアローンで購入後の離婚は、非常に複雑なトラブルとなることがあります。
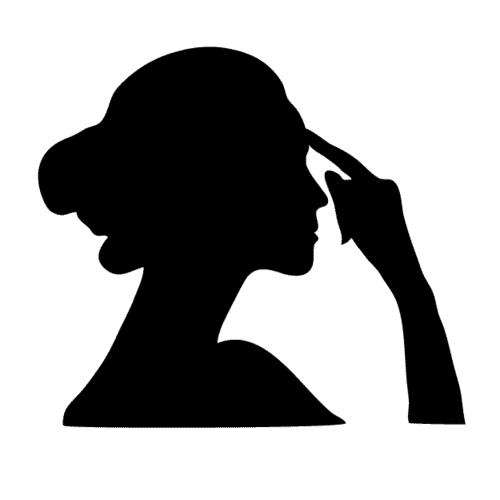 相談者
相談者離婚後も自宅に住み続けたいが、ペアローンが心配
 相談者
相談者ペアローンが残っていると離婚が難しいのでは…?
離婚時の財産分与では、「債務」であるペアローンと、「資産」である不動産を法的にきちんと整理しておくことが、将来のトラブルを避ける重要なポイントです。夫婦関係を解消しても、金融機関とのローン契約は、離婚後も残ります。そのため、離婚してもなお、元配偶者の経済状況に左右されるリスクを負い続けることとなります。
ペアローン解消には、「家を売却する」「どちらかが住み続け、ローンを一本化する」といった解決策がありますが、いずれも金融機関の同意が必要であるなど、複雑な問題を伴います。
今回は、離婚時のペアローンのリスクと、後悔しないための清算方法、そして子供がいる場合の注意点まで、弁護士が解説します。
ペアローンは離婚時に清算すべき

「ペアローンがあると離婚できないのでは」と誤解している人もいますが、ペアローンが、離婚そのものを禁止したり制限したりすることはありません。
ただ、ペアローンを組んで購入した住宅の問題を解決しないまま離婚すると、将来深刻な金銭トラブルに発展するリスクがあります。ペアローンで購入した住宅は、夫婦の共有名義となっており、かつローン契約上、夫婦が互いの連帯保証人になっているのが通常だからです。
離婚によって夫婦という身分関係は解消されます。
しかし、金融機関と締結したローン契約はそのまま残ります。すると、元パートナーがローン返済を滞納したり、破産したりした場合、相手の残債務も含めたローン全額の一括返済を求められるおそれがあります。
また、共有名義である限り、不動産の売却や賃貸、担保の設定といった処分行為は、共有者である元配偶者の同意が必要です。
住宅の扱いを決めるにあたり、離婚後もずっと関わり続けなければならず、関係性が良好でないとストレスになるでしょう。後になって単独所有としたい場合、共有物分割請求という法的な手続きが必要ですが、これは離婚協議とは全く別の手続きで、相当な時間と費用がかかります。
したがって、ペアローンがあっても離婚はできるものの、将来にわたって相手の経済状況に左右されるリスクや、不動産処分の自由が制限されるおそれがあります。トラブルを避けるために、離婚時の財産分与の一環として、ペアローンと不動産の共有名義を清算することが賢明な選択です。
「共有関係を解消する方法」の解説

ペアローンのまま離婚した場合のリスク

次に、ペアローンを組んだまま離婚するリスクを解説します。なぜペアローンを清算せずに離婚してはいけないのか、具体的なリスクを理解しましょう。
相手の滞納や自己破産で返済義務を負う
ペアローンのまま離婚すると、相手の経済状況に、離婚後も人生を左右されます。相手の債務の連帯保証人となっていることの責任は非常に重いものだからです。
離婚後のローン返済が滞れば、金融機関はあなたにも滞納分の支払いを請求してきます。滞納が続けば、残債の一括返済を強いられる危険もあります。離婚協議の中で「住宅ローンは夫が支払う」と約束しても、金融機関との関係では意味を持ちません。
相手が自己破産すると更に深刻で、免責許可決定がされると元配偶者の返済義務はなくなりますが、連帯保証人の債務は残ります。その結果、本来二人で返すはずのペアローンを一人で背負うことになり、自分も返済不能になれば、破産を検討せざるを得なくなります。
「保証契約」の解説

住宅の処分に元配偶者の同意が必要
ペアローンで取得した住宅は、二人の共有となります。そして、共有状態の不動産を売却したり、担保に入れたりといった処分行為には、共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。
したがって、離婚後に「家を売りたい」と考えても、ペアローンだと、相手が反対したり連絡がつかなくなったりすれば、手続きを進められません。元パートナーが亡くなった場合、相続人(再婚相手や子供など)に引き継がれます。その結果、全く面識のない第三者と不動産を共有する事態となり、不動産を売却するのが極めて困難となる人もいます。
「離婚時の財産分与」の解説

意に反して住宅の売却を強いられる
リスクを解消し、夫婦の一方が離婚後も住み続けるには、次の方法があります。
- 離婚時にペアローンを一括返済する。
- 不動産を売却して代金を分与する。
- 住み続ける側が借り換えを行う。
- 財産分与の際、不動産の持ち分を買い取る。
これらの方法なら、不動産の共有状態を解消し、連帯保証債務からも逃れられます。ただし、最大のハードルとなるのが「資力」の問題です。
ペアローンには、「夫婦の収入を合算しないと融資が受けられない」という経済的な理由があることが多く、まして、離婚して世帯収入が減少すると、残ローンを一人で返すのは困難でしょう。一括返済する資力はなく、借り換えの審査も通らないと、最終的には、売却して清算する以外の選択肢がなくなってしまいます。
「財産分与で土地を分ける方法」の解説

金融機関から一括返済を請求される
多くの住宅ローンは、契約者に次の義務の遵守が求められています。
- 通知義務
氏名や家族構成など、届出事項に変更が生じた場合、速やかに金融機関へ通知する義務。離婚は届出事項の変更に該当します。 - 居住要件
融資対象の物件に契約者本人が居住する義務。離婚によって一方が退去すると、この要件に抵触する可能性があります。
金融機関に届け出ることなく、夫婦の一方が退去した場合、上記に違反したとみなされる可能性があります。そして、契約違反となると「期限の利益」を喪失し、ペアローンの残債をただちに一括で返済するよう求められます。
離婚の事実を金融機関に隠し続けることは、常に一括請求のリスクを抱え続けることに他ならず、自身を極めて不安定な状態に置く危険な行為です。
「離婚前の別居の注意点」の解説

新規ローンの審査に影響が出る
ローン滞納が長期化すると、信用情報機関に記録され(いわゆる「ブラックリスト」)、クレジットカードが使えなくなったり、新たなローンが組めなくなったりと、生活に支障が生じる危険があります。ペアローンの名義人である限り、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)にペアローン残高が登録され続け、今後の新たなローン審査にも影響します。
このことは、将来新しい家を購入するとき審査に通らなかったり、自動車ローンや教育ローン、事業資金の融資など、あらゆる与信審査に影響します。
ペアローンを残すことは、あなたの「信用力」を、離婚後も元パートナーに握られ続けることを意味します。新しい生活における経済的な自由や可能性を、制限されることに他なりません。
「借金を理由とする離婚」の解説

ペアローンを離婚時に清算する解決策

次に、ペアローンを離婚時に清算するための具体的な方法を解説します。
ペアローンのリスクを無くすには、離婚時に「不動産の共有状態」と「連帯債務者・連帯保証人としての地位」のを解消することが不可欠です。
家を売却する
最も確実でトラブルが少ないのは、不動産を売却し、その代金でペアローンを完済する方法です。この方法なら、不動産の共有状態も、連帯債務者や連帯保証人の地位も、一括で解消できます。
その後の流れは、具体的には次の通りです。
- アンダーローンの場合
売却価格がローン残高を上回る場合(アンダーローン)、ローンを完済し、残った利益は、夫婦の協力により築いた財産(共有財産)として、原則2分の1ずつ分け合います。なお、頭金が特有財産から支出されていた場合には考慮するのが通例です。 - オーバーローンの場合
売却価格がローン残高を下回る場合(オーバーローン)、家を売ってもローンは完済できず、債務が残ります。金融機関の同意を得て家を売却し(任意売却)、残った債務は、夫婦で負担割合を決め、分割で返済していくことになります。
どうしても今の家に住み続けたい場合、一度売却した後、買主と賃貸借契約を結んで、家賃を払いながら住み続ける「リースバック」の手法もあります(ただし、所有権は失われ、家賃支払が困難になれば退去しなければなりません)。
なお、売却には不動産会社に支払う仲介手数料、登記費用などの費用がかかること、売却益には譲渡所得税が課されることなど、費用負担も考慮すべきです。複雑なケースでは、弁護士や税理士に確認しておいてください。
「離婚計画の立て方」の解説

どちらかがローンを一本化して住む
夫婦の一方が家に住み続けることを希望する場合、ローンを一本化する手もあります。不動産と債務の名義を集約し、ペアローンを解消する方法です。具体的には、住み続ける側がペアローンの残債総額を借り換えして完済し、同時に、財産分与として元パートナーの共有持分を買い取ります。
ただし、この方法は、融資審査を通過するのが大きな課題です。夫婦二人分の収入を前提として組んだペアローンを、離婚後の単独の収入で返済する能力を認めてもらわなければならないので、ハードルは高いと言わざるを得ません。
「分割払いの交渉をする方法」の解説

ペアローンを離婚時に清算しない解決策

次に、推奨はできませんが、ペアローンを清算せずに離婚する選択肢を解説します。
やむを得ない事情で、どうしても離婚時にペアローンを清算できない場合には、将来起こり得るリスクを理解し、可能な限りの対策を講じておくことが不可欠です。
共有名義のままどちらかが住み続ける
第一に、共有名義のままどちらかが住み続ける方法です。
この場合、ペアローンも残り続けるので、離婚してもなお、元配偶者との関係が残り続けるリスクを覚悟しなければなりません。
- 相手の債務を肩代わりさせられるリスク
自分のローンを返済しても、相手が滞納したり破産したりした場合、残債務の返済義務が降りかかる危険があります。 - 不動産を自由に売却・処分できない
共有状態のままなので、売却や大規模なリフォームには相手の同意が必要です。関係が悪化していたり、連絡が付かなくなったり死亡したりすると、問題は複雑化します。 - 将来のローン審査で不利になる
あなたの信用情報にペアローンの負債全額が登録され続けるため、新たな住宅ローンや教育ローンなどの審査において、著しく不利な状況が続きます。
このように、共有名義と連帯債務の関係を維持したままでは、将来にわたり元パートナーの経済状態や意向に人生を左右され続けることになります。
「離婚までの流れ」の解説

共有名義のまま賃貸に出す
第二に、共有名義のまま賃貸に出す手もあります。
ただ、住宅ローンは「契約者本人の居住」を前提に低金利となっているので、金融機関の承諾なく第三者に賃貸するのは契約違反となります。
また、賃貸経営は「事業」であり、経営リスクも伴います。借主が見つからない(空室リスク)、家賃を滞納される(滞納リスク)、故障や経年劣化で修繕が必要となる(費用負担リスク)などです。これらのリスクについて、共有者である元配偶者と協議して進める必要があります。
「賃貸借契約」の解説

ペアローン離婚で子供がいる場合はどうすべき?

次に、子供がいる家庭でペアローンの問題を解決する際の注意点を解説します。
子供に与える影響を最小限に抑えるには、金銭面だけでなく精神面のケアも不可欠です。安心して新生活をスタートできるよう、慎重に判断しましょう。
養育費とローン返済は別問題
法律上、「養育費」と「住宅ローン返済」は、その性質も根拠も全く異なります。
例えば、離婚時に夫から「養育費の代わりにペアローンを全額払う」と提案される例もありますが、応じてはなりません。夫がペアローンを滞納すると支払いの責任を負うだけでなく、本来もらえたはずの養育費も受け取れない二重苦となります。
養育費は、親の扶養義務の一環となる金銭であり、子供のための制度です。一方、ローン返済は、金融機関との契約上の債務であり、夫婦間においては財産分与の問題として処理すべきです。
この二つは完全に切り分け、それぞれ協議しなければなりません。特に、養育費が未払いとなるおそれもあるので、離婚協議書を公正証書化し、万が一支払いが滞った際に、裁判を経ずに相手の財産を差し押さえられるようにしておくのが確実です。
「養育費が支払われないときの対応」の解説

子供の生活環境を優先する
ペアローン付き住宅の扱いを決める際は、夫婦の損得勘定だけでなく、「子供の幸せのために何が最善か」を考えるべきです。これは、親としての責任であると同時に、万が一裁判になった場合に裁判所が用いる判断基準でもあります。
子供の生活環境を維持するには、「今の家に住み続ける」のが理想かもしれません。
住み慣れた家や学校、友人関係を維持することは、離婚という変化の中で子供に安心感を与えます。しかし、これを実現するには、住み続ける側の経済力と、元パートナーの協力が不可欠です。
一方で、家を売却すると、多くの場合、子供に転校を強いることになります。環境の変化を伴うので、負担を和らげるための心のケアが必須です。なぜ引っ越す必要があるのかを丁寧に説明し、子供の不安な気持ちを受け止めなければなりません。
絶対の正解はありませんが、感情的にならず、それぞれのメリット・デメリットを比較し、子の福祉を最優先にして検討することが大切です。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

面会交流などのルールを明確に定める
家の扱いと面会交流のルールは、密接に関連しています。
例えば、家を売却して、金銭的・法的な関係を完全に清算した上で、お互いが近隣に住めば、家を巡る争いを避けつつ、子供が両親と柔軟に会える環境を整えられます。ローンを一本化して家に住み続けるなら、その家を安定した面会交流の拠点とすることも可能です。
しかし、ローンや不動産の名義を共有のまま残すことは、将来に火種を残します。居住や費用負担について、離婚後に新たな対立が生じれば、面会交流の実施の障壁にもなりかねません。
重要なのは、家の問題と面会交流の具体的なルール(頻度、時間、場所、連絡方法など)について、離婚協議の場でしっかりと話し合うことです。住環境と面会交流について事前に決めておけば、より現実的で無理のない面会交流のルール作りが可能になります。
「子供のために離婚しない」の解説

ペアローン離婚の協議を始める前の準備

次に、ペアローンがある離婚を有利にするための事前準備を、ステップで解説します。感情的にならず、客観的な事実に基づいて協議を進めましょう。
契約内容を正確に確認する
金融機関と交わした「金銭消費貸借契約書」を取り寄せ、ペアローンの内容を隅々まで確認してください。特に重要なのは次の項目です。
- 契約形態
自分が連帯保証人なのか、それとも連帯債務者なのか。どちらの形態でも債務全額の責任を負うのは共通ですが、相手が支払いをやめた場合に金融機関が他方に請求できる範囲などが異なります。 - 正確なローン残高と返済状況
最新の返済予定表や残高証明書を取得し、ローン残高を正確に確認します。これは財産分与額を計算する上での必須の情報です。 - 期限の利益喪失条項
契約者が特定の義務に違反した場合に「分割で返済できる権利(期限の利益)を失い、金融機関から一括返済を請求される事由」が列挙されています。離婚したことを報告しなかったり、金融機関の承諾なしに名義変更や売却を行うことが、これに該当しないかを確認します。
客観的な情報を事前に整理しておくことが、自分の立場を明確にし、解決策を検討するための土台となります。
「相手の財産を調べる方法」の解説

共有財産をリストアップする
「共有財産」とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産のことです。所有名義が共有のものだけでなく、いずれか一方の名義のものも含みます。
- 預貯金(夫婦それぞれの名義分)
- 不動産(土地や建物)
- 生命保険・学資保険など(解約返戻金)
- 有価証券(株式、投資信託など)
- 自動車
- その他(退職金、年金など)
離婚時の財産分与を公平に行うため、全てを網羅し、財産目録にリスト化することが重要です。離婚に向けて協議を始めると、財産を隠す人もいるので、協議を切り出す前に証拠となる資料を確保しておくことが重要です。
「共有財産」の解説

不動産の価値を査定する
財産分与の対象となる不動産の価値は、業者の査定書で認定することが多いです。特に、アンダーローンかオーバーローンかにより、離婚後の扱いは大きく変わります。
財産分与では、不動産の価値の評価は、離婚時を基準に決めるのが通常です。必ず複数の不動産会社に依頼し、おおよその市場価値を客観的に把握しておきましょう。
「財産分与の基準時」の解説

ペアローンについての離婚協議の注意点

次に、ペアローンについて相手と協議する際の注意点を解説します。
財産分与とセットで話し合う
財産分与は、婚姻中に協力して形成・維持された財産の公平な分配を目的とします。ペアローン付きの不動産は、プラスとマイナスの価値が混在しているので、扱いに注意を要します。
交渉を進める際は、事前に作成した財産リストをもとに、不動産だけでなく夫婦の財産全体を見なければなりません。例えば、「相手が不動産と残ローンを取得する代わりに、こちらは預貯金をより多くもらう」「家を売却して得た利益と、夫婦の預貯金を合算し、その総額を公平に分配する」といった提案を検討するにも、全体の把握が欠かせません。
ペアローンの問題という一部のみ見て交渉するのでなく、「財産分与」の全体から、過不足を調整するようにするのが、公平な解決に至るためのポイントです。
「離婚に伴うお金の問題」の解説

特有財産の扱いを明確にする
夫婦の一方が結婚前から持っていた預貯金や、親から贈与・相続された財産などは、「特有財産」として財産分与の対象外です。このことは、ペアローンの問題を考える際にも重要です。
例えば、住宅購入時の頭金400万円のうち、300万円を妻の親からの贈与で賄った場合、この300万円は妻の特有財産であり、分与の際には控除すべきと考えられます。
特有財産を主張するには、客観的な証拠が不可欠です。親から自身の口座への振込履歴が記載された通帳のコピーや、贈与契約書などを準備する必要があります。
「特有財産」の解説

合意内容は公正証書で残す
離婚協議で合意した金銭の支払いについて、口約束だけでは守られない危険があります。
そのため、将来支払いが滞った場合に備えて、離婚協議書を作成し、公正証書にしておくことがお勧めです。公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておけば、相手が支払いを怠った場合に、裁判を経ることなく直ちに給与や預貯金などを差し押さえる「強制執行」の手続きができます。
公正証書は、約束が破られた際に、権利を迅速かつ確実に実現するための強力な武器です。作成には費用がかかりますが、将来の紛争を予防するための「保険」と考えるべきです。
「離婚協議書を公正証書にする方法」の解説

ペアローン離婚でよくある質問
最後に、ペアローンを抱えた状態で離婚を検討する方からよくある質問に回答します。
離婚後、住宅ローン控除はどうなる?
住宅ローン控除の扱いは、離婚後の状況によって変わります。
- 家に住み続ける側
居住要件を充足するため、引き続き住宅ローン控除を受けられる可能性あり。単独名義に借り換えた場合も、新たなローンの条件で控除の対象となります。 - 家を出ていく側
退去した場合は居住実態がなくなるので、離婚後は住宅ローン控除の対象外。
税務のルールは複雑であり、個別の契約内容や借り換えの時期によっても異なるので、正確に進めるには、必ず税務署や税理士に確認してください。
相手が話し合いに応じない場合は?
相手方が協議に応じない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
ペアローンを含めた住宅の問題は感情的になりやすく、話し合いでは解決できないこともあります。調停では、中立な立場の調停委員が間に入り、双方の主張を聞いて解決案を提示してくれます。
離婚が先に成立したが、共有不動産のペアローンが残ってしまった場合、「共有物分割請求訴訟」を提起する方法もあります。この手続きは、調停と異なり、裁判所の判断で強制的な解決が可能です。ただし、離婚調停係属中に共有物分割請求を提起すると、場合によっては権利濫用と判断されるので(東京地裁平成29年12月6日判決)、まずは離婚調停の中で財産分与の問題として解決するのが基本です。
「離婚調停を弁護士に依頼するメリット」の解説

ペアローンのリスクを抑えるには?
ペアローンは借入可能額が増えるなどのメリットがある一方、離婚時には責任が拡大するリスクがあります。契約前にリスクを抑えるには、以下の点に注意してください。
- 収入に見合った住宅を購入する
どちらかの収入が途絶えても、他方が返済を続けられる程度の無理ない計画を立てることが、将来の破綻リスクを回避する上で重要です。 - 頭金を多めに用意する
頭金を多く入れることで借入を圧縮できます。借入が少なければ、将来不動産を売却するにしてもオーバーローンになりづらくなります。 - 借入期間を短期に設定する
借入期間を短くすれば、ローン残高の減少ペースが速まるため、将来オーバーローン状態になるリスクを抑える効果があります。
離婚時の法的なリスクを完全に無くすことはできないものの、トラブルになった際の損害を最小限に抑え、円滑に解決するための有効な手段です。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

まとめ

今回は、ペアローンを組んでいる夫婦が、離婚時に注意すべきポイントを解説しました。
重要なのは、ペアローンを放置することのリスクを理解し、契約書や財産リストの作成、不動産査定といった事前準備を徹底して行うことです。交渉で解決するにも、事前準備は不可欠です。その上で、家を売却するのか一方が住み続けるのかといった、具体的な対応を検討してください。
万が一話し合いが進まない場合は、調停や訴訟といった法的な解決手段もあります。しかし、手続きが紛糾すれば、解決のためにかかる時間も費用も精神的な負担も大きくなります。
当事者では解決が困難な場合、できるだけ早い段階で弁護士に相談するのがお勧めです。専門家である弁護士に相談することで、あなたの状況を法的に整理し、取り得る選択肢と、それぞれのメリット・デメリットを冷静に比較検討することができます。後悔のない形で問題を解決し、新しい生活への一歩を踏み出すために、ぜひ一度ご相談ください。
財産分与は、結婚期間中に形成された資産を整理し、公平に分割するための重要な手続きです。財産の評価方法や分割の割合などが争われると、法律知識に基づいた解決が必要となります。
トラブルを未然に防ぐために、以下の「財産分与」に関する詳しい解説を参考に対応してください。
財産分与は、結婚期間中に形成された資産を整理し、公平に分割するための重要な手続きです。財産の評価方法や分割の割合などが争われると、法律知識に基づいた解決が必要となります。
トラブルを未然に防ぐために、以下の「財産分与」に関する詳しい解説を参考に対応してください。


