企業の資金調達、個人の借金など、お金を借りる際に避けて通れないのが「保証契約」。保証契約は、ビジネスでも個人の生活でも身近な契約類型ですが、保証人の負担は非常に重いものです。特に、継続的な取引から生じる債務を一括して担保する「根保証契約」は、一度サインすると大きな債務を背負うおそれがある、リスクの高い契約です。
企業の借入では経営者、個人の借金では親族が保証人となる例が多いですが、そのリスクを理解し、契約の締結は慎重に検討しなければなりません。また、2020年4月1日施行の民法改正では、極度額の設定や情報提供義務など、保証人を保護するためのルールが新設されました。
今回は、保証契約の基本と改正法のポイント、実務対応の注意点について、弁護士が解説します。
- 保証は法人・個人に身近な契約だが、経営者保証の負担は重い
- 2020年施行の改正民法で、個人根保証には極度額の定めが必須となった
- 連帯保証契約の責任は重いので、保証契約の締結には慎重になるべき
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
保証契約とは

保証契約とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、保証人がその責任を代わって負うことを約束する契約です(民法446条)。
保証契約は、債権者・債務者・保証人の三者が関連しますが、契約の締結は債権者と保証人となる者との間でされ、書面でしなければ効力を生じないといった特徴があります。
保証契約は、例えば、次のケースで活用されます。
- 企業が銀行融資を受ける際の経営者保証
- 賃貸オフィスや店舗、個人の住居の賃貸借契約の連帯保証人
- 取引先への掛取引(与信枠)設定時の根保証
通常の保証では、債権者はまず債務者に請求する義務(催告の抗弁)、債務者の財産から先に執行する義務(検索の抗弁)があります。しかし、連帯保証では、この2つの抗弁は排除され、債権者が直ちに保証人へ請求、強制執行できる点で、保証人の負担が格段に重い契約です(民法454条)。
実務上、経営者保証などの場合、連帯保証とされるケースが一般的です。
保証契約が成立する要件
保証契約が有効に成立する要件は、次の通りです。
- 書面または電磁的記録による契約であること
民法は、保証人保護の観点から、保証契約は書面によることを要件としています。この要件を欠き、口頭で約束された保証契約は無効です。 - (事業債務の個人保証の場合)公正証書による保証意思の確認
事業によって生じる債務を個人が保証する場合、保証契約締結の1ヶ月以内に作成された公正証書により、保証意思を確認する必要があります(民法465条の6)。経営者保証の場合に、より厳格に保証人の意思を確認する趣旨です。 - 主債務の存在(付従性)
保証債務には「付従性」があるので、主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅します。
保証人の責任の範囲
保証契約を締結すると、保証人は、主たる債務についての責任を負います。
保証債務の「付従性」から、保証債務は主債務に従属し、主債務が消滅すれば保証債務も消滅します。また、保証人は、主債務の範囲内でのみ責任を負うので、債務者が弁済や相殺によって主債務を減縮させたときは、その分だけ保証人の負担も軽減されます。
また、保証人は、主債務者に代わって弁済したときは、債務者に対して支払い額を請求(求償)することができます(民法459条)。
根保証契約の意味と規制
保証契約の中で、継続的な取引から生じる不特定多数の将来債務を一括して担保するものを、根保証と呼びます。例えば、売掛取引や、運転資金枠を設定した継続的な融資を行い、それらの債務を「まとめて」保証するケースが該当します。
根保証を設定すれば、債権者は、債務の内容が変わるたびに再契約する手間が省け、債務者としても迅速に資金の供給を受けられるメリットがあります。一方で、元本が確定するまでは新たに債務が発生するごとに保証範囲が拡大し、保証人の負担が予想できない点がデメリットです。
根保証は、保証人の責任が拡大しやすいので、「極度額」「元本確定日」などを正しく設定・把握しなければなりません。また、2020年4月施行の民法改正では、個人が根保証人となる場合には極度額の定めが義務となり、設定されなければその根保証契約は無効となります(「個人根保証に極度額の定めを義務化」で後述)。
2020年の民法改正による保証契約の変更点

2020年4月1日に施行された民法改正では、保証契約、特に根保証のルールが大きく変更されました。この改正によって保証人の保護は強化され、債権者には新たな義務が課されました。
改正の背景として、日本では中小企業の融資にあたって経営者などの個人が連帯保証するのが慣例でしたが、取引先の倒産や事業失敗によって生活の基盤を失う事例が後を絶たず、制度の見直しが求められていた事情があります。
個人根保証に極度額の定めを義務化
2020年施行の民法改正により、個人が根保証契約を締結する場合、必ず「極度額(上限額)」を定めることが義務化され、極度額を定めない個人根保証は無効となりました。改正前の民法では、極度額の義務化は、貸金債務等を個人が根保証する場合に限られていましたが、改正後は、全ての個人根保証契約について極度額が義務化されました(民法465条の2第2項)。
また、個人根保証契約の責任範囲について、主たる債務の元本だけでなく、利息、違約金、損害賠償、その他の従たる債務についても、全て極度額を限度とすることが定められました(民法465条の2第1項)。
「民法改正(2020年4月施行)」の解説
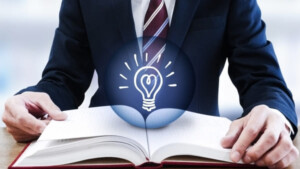
元本確定事由と元本確定期日の導入
根保証は一定期間に発生した債務の保証であるところ、保証人がいつまで責任を負うのか不明確だと負担が過大になるおそれがありました。そのため、改正民法では、元本の確定についてのルールが明確化されました。
根保証人の改正民法における元本確定事由は、次の通りです。
- 個人根保証契約(民法465条の4第1項)
- 保証人についての強制執行、担保権実行の申立て
- 保証人についての破産手続開始決定
- 主債務者または保証人が死亡
- 個人貸金等根保証契約(民法465条の4第2項)
上記の3つに加え、主債務者についての強制執行、担保権の実行、破産手続開始決定
また、保証人と債権者との間で、元本確定日を契約で定めることが可能ですが、保証人保護のため、個人貸金等根保証契約の場合、契約締結から5年以内で元本を確定しなければ、以降に発生する債務は保証の対象外となることが定められています(民法465条の3)
保証意思宣明公正証書の新設
民法465条の6は、保証意思宣明公正証書に関する条項を新設しました。
具体的には、事業のために負担する貸金等の債務について個人が保証する場合、契約前に公証人の面前で保証意思を明示する「保証意思宣明公正証書」が必要とされます。公正証書は、保証契約の締結前1ヶ月以内に作成しなければならず、公正証書がない場合は保証契約が無効となります。
そもそも保証契約は書面または電磁的記録による必要がありますが、中小企業の経営者や親族が保証人となる場面は、特に保証人の保護を要すると考えられたためです。
ただし、主たる債務者が法人である場合の取締役や執行役、これに準じる者、株式の過半数を有する者が保証人となる場合や共同事業者、事業に従事している配偶者については、保証人となるニーズがあることから本条の適用はありません(民法465条の9)。また、あくまで個人保証人の保護のためなので、保証人が法人の場合にも適用されません(民法465条の6第3項、465条の8第2項)。
情報提供義務の強化
改正民法は、保証人を保護するため、様々な情報提供義務を強化しています。これにより、保証人は、リスクを正確に把握して保証契約を締結することができます。
保証契約締結時の主債務者の情報提供義務
民法465条の10は、事業のために生じる債務の個人保証を依頼するときは、主債務者は保証人に対して、財産や収支の状況、主債務以外に負担している債務の状況、担保の提供などについて情報を提供する必要があることを定めています。主債務者が説明しなかったり、事実と異なる説明をしたりした場合、債権者が不実の説明があったことを知っていたか、または知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができます。
主債務の履行状況に関する債権者の情報提供義務
民法458条の2は、保証人が主債務者の委託を受けて保証した場合に、保証人の請求があったときは、債権者は保証人に対して、主債務の元本や利息、損害賠償など、主たる債務に関する全ての債務について、不履行の有無、残額、履行期限が経過している債務額などの情報を提供しなければならないことを定めています。
この規定に違反しても罰則はないものの、債権者が保証人かから、債務不履行責任を追及される可能性があります。
主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務
民法458条の3は、主たる債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2ヶ月以内に、その旨を通知しなければならないことを定めています。債権者が、通知を怠った場合、保証人に対して、期限の利益喪失時から通知までの間に生じるはずであった遅延損害金についての保証債務の履行を請求することができません(同条第2項)。
まとめ

今回は、保証契約の基本と民法改正のポイントについて解説しました。
民法改正によって、個人の根保証契約について保証人を保護する規定、保証契約を締結する際の情報提供義務など、個人保証人の保護と取引の透明性が大きく強化されました。これまで、連帯保証人となることには多大なリスクがありましたが、極度額、公正証書、情報提供義務という本改正のチェックポイントを押さえれば、保証契約の危険性は軽減することができます。
したがって、債務者や保証人の立場では、民法改正の内容をよく理解し、法律に適合した保護を受けられるよう注意すべきです。そして、債権者の立場でも、保証契約書を改正民法に対応した内容に修正する必要があります。
保証契約をめぐる法的なトラブルに巻き込まれそうなときは、早めに弁護士に相談して、アドバイスを受けるのがお勧めです。
- 保証は法人・個人に身近な契約だが、経営者保証の負担は重い
- 2020年施行の改正民法で、個人根保証には極度額の定めが必須となった
- 連帯保証契約の責任は重いので、保証契約の締結には慎重になるべき
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
民法の改正は、契約や取引、債権債務など、生活や企業経営に密接に関わります。改正の内容を正しく把握しなければ、思わぬトラブルを招くおそれもあります。
適切な権利行使をするためにも、民法改正に関する解説記事を通じて、最新のルールを理解しておいてください。


