結婚は、愛情だけでなく法的なつながりでもあります。
「夫婦になる」ということは、お互いが一定の義務を負うことを意味し、その義務は法律によって明確に定められています。結婚後に負う義務の代表例が、同居義務・協力義務・扶助義務・貞操義務の4つであり、これらは夫婦関係を築くうえでの基本ルールともいえます。
結婚によって負う義務を正しく理解しないと、知らないうちに法律違反となり、離婚要求や慰謝料請求といった深刻な問題に発展するおそれがあります。これから結婚を視野に入れている人はもちろん、既に結婚している人も、夫婦関係を見直しておいてください。
今回は、結婚による4つの義務について、その内容や法律上の根拠、違反した場合のリスクを、弁護士がわかりやすく解説します。
- 夫婦は法律上、同居・協力・扶助の義務を負う
- 不貞行為は、貞操義務の違反となり、離婚や慰謝料請求の原因となる
- 夫婦の義務に違反することは、調停や裁判で不利益に働くおそれがある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
結婚によって法律上の義務が生じる理由

結婚は、単なる感情的な結びつきではなく、法律上の義務を伴います。これらの法的義務に性差はなく、夫も妻も対等に負います。
法律婚をした夫婦に課される義務は、民法に次のように定められています。
- 民法752条
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」(同居義務・協力義務・扶助義務) - 民法760条
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」(婚姻費用分担請求権)
※ 貞操義務は明文化されていませんが、多くの裁判例により確立され、不貞行為(配偶者以外の異性と性的関係を持つこと)は不法行為(民法709条)となるほか、「法定離婚事由」にも該当します。
結婚から生じる法的な義務は、夫婦関係の安定と家庭の保護を目的としています。あくまで、法律婚によるものなので、恋愛関係や同棲、事実婚(内縁関係)では生じません。
そして、義務が果たされなければ、法的にも一定の影響があります。夫婦の義務が果たされない場合、日常生活に支障をきたすだけでなく、法的なトラブルに発展することもあります。例えば、「貞操義務違反(不貞行為)」に代表されるように、夫婦の義務への違反は、家庭裁判所における調停や裁判でも大きな争点となり、慰謝料請求や離婚の理由として主張されます。
なお、結婚そのものは義務ではなく、生涯独身を貫くのも個人の自由です。
「離婚までの流れ」の解説

同居の義務

まず、夫婦の「同居義務」について解説します。
同居義務の内容
同居の義務は、民法752条に次のように規定されています。
民法752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法(e-Gov法令検索)
この条文により、結婚した夫婦は、原則として同居する義務があります。この「同居」は単に同じ場所に住むだけではなく、夫婦として協力し、実質的に共同生活を送っている状態を指します。つまり、寝食を共にし、生活費を共有し、家庭を築いていることが前提となります。
同居は、夫婦の信頼関係を育み、生活を協力して成り立たせる基礎となります。そのため、後述の「協力」「扶助」といった義務の前提として重要視されます。
ただし、夫婦がお互いに合意して別居しているなら、同居義務違反とはなりません。また、以下のよう場合は、別居に正当な理由があるものとして、同居義務違反にならないことがあります。
- 単身赴任や転勤による別居
- 長期入院などの健康上の理由による別居
- 里帰り出産による一時的別居
- 親族の介護などの事情のある別居
- DVやモラハラによる安全確保のための避難
このような場合、同居していなくても、直ちに法的責任を問われるわけではありません。
「勝手に別居すると不利?」の解説

同居義務の違反と法的効果
相手の同意や承諾のない別居は、同居義務違反となるおそれがあります。
特に、相手の生活費を一切負担せずに連絡を断つと、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)となり、婚姻関係を破綻させた責任がある配偶者(有責配偶者)とされる危険もあります。
別居の理由、期間、相手の態度など、具体的事情によっても判断は分かれますが、夫婦が別居を開始した全てのケースが、同居義務違反となるわけではありません。実際のところ、「夫婦喧嘩をして家出した」「一緒にいるのが辛いので実家に帰った」といった家庭は珍しくなく、同居義務違反のみを理由に慰謝料を請求するのは難しいです。
相手が一方的に家を出た場合、家庭裁判所に同居を命じる調停や審判を申し立てることも可能ですが、同居の強制は現実的に難しいでしょう。実務上は、別居の背景となった理由に基づき、離婚の協議を進めていく例が多いです。以下の裁判例も、婚姻関係が破綻している場合に、同居義務の履行は難しいことを示しています。
夫婦の同居義務は、夫婦という共同生活を維持するためのものであるから、その共同生活を維持する基盤がないか又は大きく損なわれていることが明白である場合には、同居を強いることは、無理が避けられず、したがって、その共同生活を営むための前提である夫婦間の愛情と信頼関係が失われ、裁判所による後見的機能をもってしても円満な同居生活をすることが期待できないため、仮に、同居の審判がされ、当事者がこれに従い同じ居所ですごすとしても、夫婦が互いの人格を傷つけ又は個人の尊厳を損なうような結果を招来する可能性が高いと認められる場合には、同居を命じるのは相当でないと解される。
なお、別居状態が長期にわたり、夫婦間の信頼関係が損なわれた場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があると判断されるケースもあります。例えば、数年にわたって別居を続け、互いに連絡を取らないケースでは、裁判所も離婚を認める傾向があります。
「離婚成立に必要な別居期間」の解説

協力の義務

次に、夫婦の「協力義務」について解説します。
協力義務の内容
民法752条は、夫婦に「同居、協力、扶助」の義務を課しています。この中で「協力」とは、夫婦生活を営むにあたり、互いに支え合うことを意味します。具体的には、家事や育児の分担はもちろん、経済面・生活面・精神面など、あらゆる場面で協力し、家庭を維持することが求められます。
例えば、次のような協力が考えられます。
- 経済面での協力
- 一方が収入を得ている場合や、収入に差がある場合、生活費を提供すること
- 共働きでも、収入を持ち寄って生活費を分担すること
- 家計を共有すること
- 一方が失業した場合に他方が助けること
- 家事・育児など生活面での協力
- 日常的な家事労働(炊事・洗濯・掃除など)を分担すること
- 育児を分担すること
- 一方が病気になった場合の看病や介護をすること
- 精神的なサポート
- 困難な状況でも相手に寄り添うこと
- 互いに悩みを共有すること
- 重要な意思決定を相談して行うこと
共働き夫婦や、男性の育休取得も増えており、深い協力関係を築く家庭もあります。
なお、協力義務があるからといって、家事や育児の全てを均等に担当しなければならないわけではありません。夫婦が話し合って役割分担を決めているなら、例えば「夫が外で働き、妻が家事育児をワンオペで担う」という分担も、必ずしも協力義務違反にはなりません。
重要なのは、一方が全てを放棄している状態ではないかという点です。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

協力義務の違反と法的効果
一方が全く家事・育児をしない場合、協力義務違反と判断される可能性があります。
特に、共働きで子供がいる家庭なのに、夫が「家事や育児は自分の仕事ではない」という態度だと、夫婦関係の破綻に繋がりやすくなります。夫が高収入なのに、家計にお金を一切入れず、趣味やギャンブルにのみ使っている場合、経済的な協力義務に反すると評価されるでしょう。
これは、経済的DVと評価される可能性があり、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)として離婚要求や慰謝料請求の理由となることもあります。
実際に、協力義務違反とされるのは、次の例です。
- 生活費を全く入れない。
- 家庭の経済状況を全く開示しない。
- 家事・育児に一切関わらず、家庭に無関心。
- 妻の出産や病気の際に精神的・物理的な支援をしない。
協力義務違反は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)と判断されるケースもあります。例えば、夫が「家事は女の仕事」などの暴言を吐くような状況は、婚姻関係が破綻していると評価されても仕方なく、離婚請求が認められる可能性があります。協力義務違反による精神的な苦痛がある場合は、慰謝料が認められることもあります(家事や育児の放棄、経済的DVなどの場合、慰謝料の相場は50万円〜300万円が目安)。
なお、離婚や慰謝料の請求を考えていない場合、当事者同士の解決が難しいなら、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てる方法も検討してください。
「円満調停」の解説

扶助の義務

次に、扶助義務と、それに基づく婚姻費用の分担義務について解説します。
扶助義務の内容
「扶助」とは、相手を経済的に支えるという意味で、主に2つに分類されます。
- 生活保持義務
相手が自分と同程度の生活を送れるよう配慮する義務 - 生活扶助義務
経済的に余裕があれば、相手に対して最低限の経済的援助を行う義務
民法760条は、夫婦は互いに婚姻から生じる費用を分担する義務があることを定めます。これは、生活費や日常の支出(食費・光熱費・家賃など)といった家庭を維持するための経済的支援を相互に行う義務であり、協力義務と共に夫婦の基本的な義務の一つです。
特に、一方が専業主婦(主夫)の家庭では、経済的な扶助義務は、主に働いている配偶者が負担します(専業側は、家事・育児などを通じて協力しています)。また、扶助義務には、日常の生活費の分担だけでなく、病気や失業などで収入が減少した場合の救済や、相手が高齢な場合の介護や生活支援も含まれています。
「離婚に伴うお金の問題」の解説

扶助義務の違反と法的効果
扶助義務違反にあたる具体例には、次のものがあります。
- 配偶者に生活費を一切渡さない。
- 相手の同意なく別居し、お金を家に入れない。
- 家計への貢献を完全に拒否する。
- 子供の養育・教育にかかる費用を一切負担しない。
悪質な場合、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)と判断され、婚姻生活の維持を困難にする行為として法的な責任を認めた裁判例もあります。
夫は半身不随であり、日常生活もままならない障害者の妻を正当な理由なく自宅に置き去りにして長期間別居を続けた。さらに、別居中に夫は妻に一切生活費を送金していなかったことから、これが扶養義務違反かつ悪意の遺棄に相当すると判断した。
相手が生活費を払わない場合には、家庭裁判所に対して婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます(調停で合意できない場合にも審判に移行し、家庭裁判所の判断が下されます)。
調停や審判で決定された婚姻費用には強制力があり、支払われない場合は強制執行の手続きによって相手の給与や預貯金、不動産といった財産を差し押さえることが可能です。
「別居中の生活費の相場」の解説

貞操の義務

次に、夫婦の「貞操義務」について解説します。貞操義務とは、結婚している限り不貞な行為(浮気や不倫)をしてはいけない義務のことです。
貞操義務の内容
実は、貞操の義務について直接定めた民法の条文はありません。
裁判例では、不貞行為とは、自分の意思で配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことです(最判昭和48年11月15日など)。そして、民法770条1項1号は、離婚が認められる条件に「配偶者に不貞な行為があったとき」を挙げています。
したがって、夫婦間に貞操義務があることは明らかです。この義務は、婚姻した夫婦の信頼と、精神的な安定を保つために必要な法的義務として確立されたものです。
貞操義務の中心は、配偶者以外との性的関係を禁止することです。不貞は、婚姻関係における信頼関係を破壊する行為として、離婚や慰謝料請求の根拠となります。
一方で、貞操義務は法律に明文化されていないため、範囲や程度は裁判所の判断に委ねられます。そのため、どのような行為が違反となるかもケースバイケースです(例えば、肉体関係はないがキスやハグをした場合、マッチングアプリや風俗を利用した場合、同性間で肉体関係を持った場合など)。なお、実務上は、不貞行為に該当しなくても、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)と判断されるケースもあります。
「不倫相手に慰謝料を請求する方法」の解説

貞操義務の違反と法的効果
不倫・浮気とされる行為として、具体的には以下のものが挙げられます。
- 肉体関係があった。
- 性行為に類似する行為があった。
- ホテルに二人で長時間滞在していた。
- 二人で宿泊を伴う旅行をしていた。
- 不倫相手と同棲していた。
これらの行為があったことを立証できれば、貞操義務違反として、慰謝料請求や離婚要求などの形で相手(夫・妻)や不貞相手の責任を追及できます。ただし、不貞行為の立証は難しいため、以下の証拠をできるだけ多く集めるのが重要です。
- 二人でホテルに出入りする写真や動画
- 肉体関係をうかがわせるメールやLINEでのやり取り
- 探偵や興信所の調査報告書
- 手紙やメモ
- クレジットカードの利用明細
- 配偶者の行動を記録した日記
- 交通系ICカード、ETCカードやカーナビの利用履歴
不貞の慰謝料は、離婚するかしないかでも異なりますが、相場としては100万円〜300万円程度が目安とされています。夫婦間の協議で合意できない場合は調停、裁判と進んでいき、不貞行為は法定離婚事由に該当するので、証拠があれば離婚が認められる可能性は高いです。
なお、不貞行為が禁止される裏返しとして、夫婦間には性行為を求める権利と応じる義務があるとされています(ただし、嫌がっているのに無理やり行為に及ぶことは認められません)。
「離婚裁判で証拠がないとき」の解説

義務に違反することの法的リスク

民法に定める4つの義務に違反した場合、さまざまな法的リスクが生じます。最後に、夫婦の義務に違反した場合の具体的なリスクについて解説します。
離婚原因になる
民法770条は、裁判において離婚が認められる理由(法定離婚事由)を定めます。今回解説した夫婦の義務への違反が、離婚原因となるのは、次のようなケースです。
- 正当な理由なく、長期間の別居を継続した場合(同居義務違反)
- 家事や育児を放棄し、相手に全く配慮がなかった場合(協力義務違反)
- 生活費を全く入れなかった場合(扶助義務違反)
- 不貞行為を行った場合(貞操義務違反)
これらの義務違反により、婚姻関係が破綻している場合、裁判所は離婚を認める傾向にあります。
ただし、義務違反を理由に離婚を要求する側は、調停や訴訟に進んだ際に裁判所を説得するためにも、これらの義務違反を立証するための証拠を準備しておかなければなりません。裁判所は、義務違反の有無だけでなく、その期間や頻度、影響の程度などを総合的に評価します。短期間の違反や軽微な不履行だけでは離婚が認められないこともあるので、継続性を示せるよう、証拠はできるだけ多く集めるに越したことはありません。
「法定離婚事由」の解説
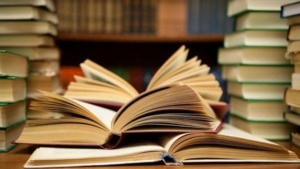
慰謝料を請求される
義務違反によって配偶者に精神的苦痛を与えた場合、慰謝料請求の対象となります。
例えば、全く理由のない長期間の別居、不貞行為によるストレスなどは、慰謝料請求の根拠となります。ただし、一定額の慰謝料が認められるには、相応の頻度や回数、程度が必要であり、単なる「夫婦喧嘩」の範囲に過ぎないものでは、慰謝料は認められません。
慰謝料の額は、以下の要素を考慮して算出されます。
- 違反行為の回数、頻度
- 義務違反の悪質さ
- 行為が続いた期間の長さ
- 配偶者に生じた精神的苦痛の程度
- 婚姻年数や子供の有無
慰謝料請求は、まずは夫婦間で話し合い、合意ができない場合には離婚調停(離婚と一緒に解決しない場合には慰謝料請求訴訟)を申し立てます。調停で合意に至れば、取り決めた内容に従って離婚しますが、合意に至らない場合は離婚裁判(離婚訴訟)に進みます。
慰謝料が争点となる離婚のトラブルは、互いに感情的な対立が生じやすく、長期化、複雑化してしまいがちです。法律知識に基づいて妥当な解決を得るには、早めに弁護士に相談してください。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

調停や裁判で問題視される
夫婦の義務に違反があることは、裁判所から悪い心証を抱かれる原因ともなります。
調停や訴訟において裁判所は、義務を守らなかった側の責任を考慮して、生活費や慰謝料、離婚条件などを調整するからです。そのため、夫婦の義務に違反したことによって、離婚調停の中で調停委員が味方になってくれなかったり、離婚裁判(離婚訴訟)において裁判官から不利な和解案を提示されたりといったケースもあります。
また、義務違反の内容によっては、「子供の養育に非協力的である」と評価されて、親権や監護権の決定に悪影響を及ぼすおそれもあります。
このようなリスクやデメリットがあるため、相手から離婚を求められた際、「自分側に義務違反がある」といった後ろめたい思いがあるなら、速やかに弁護士に相談して、対策を講じておかなければなりません。
「離婚調停を申し立てられたら?」の解説

まとめ

今回は、結婚によって生じる4つの義務について解説しました。
結婚をすると、夫婦には、同居・協力・扶助・貞操という4つの義務が法的に課されます。これらは単なる道徳的な約束ではなく、民法で定められたルールであり、違反すれば、相手から離婚を要求されたり、慰謝料その他の損害賠償を請求されたりする危険があります。
一方で、夫婦関係は、法律のみによって縛られるものではありません。その意味で、夫婦というのは、互いに信頼し、支え合いながら生活を営むことが最低限のルールとなります。義務の内容を正しく理解することは、夫婦間のトラブルを避け、より良い関係を築く役に立ちます。
夫婦関係に不安を抱えている場合、一人で悩まず弁護士に相談してください。法的な視点から冷静に状況を整理し、将来のトラブルを減らすアドバイスが可能です。
- 夫婦は法律上、同居・協力・扶助の義務を負う
- 不貞行為は、貞操義務の違反となり、離婚や慰謝料請求の原因となる
- 夫婦の義務に違反することは、調停や裁判で不利益に働くおそれがある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
離婚問題を迅速に解決するには、離婚理由(離婚原因)についての知識が重要です。裁判では不貞やDV、悪意の遺棄などの一定の事情がなければ離婚が認められないところ、交渉や協議でもこれらの事情が重視されます。
「離婚理由」の詳しい解説を理解し、戦略的に進める参考にしてください。


