離婚は、人生の中でも大きな転機となる出来事なので、計画的に進めるべきです。
そこで役立つのが「離婚計画」です。離婚計画は、離婚後の生活を見据え、必要な準備や合意事項を整理することで精神的・経済的な不安を減らし、円満な離婚を実現する手助けとなります。
子供がいる場合や、長年築き上げてきた家庭を解消する場合、離婚が大きな争いとなることは避けられないケースもあります。離婚計画をしっかり立てておけば、法的なポイントを踏まえ、自分にとって有利に進めていくことができます。
今回は、離婚を検討し始めたときに考えるべき、離婚に向けた計画の立て方、離婚計画書の作成方法について、弁護士が解説します。
- 離婚は、感情任せにせずに、計画的に進めることが重要
- 離婚計画を作成する際は、冷静な判断と入念な準備が成功のポイントとなる
- 離婚計画書を弁護士に見せて相談すれば、法的なリスクを回避できる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
離婚計画とは?

はじめに、離婚計画の意味と、その重要性について解説します。
離婚計画とは、離婚を前提として必要な情報を集め、冷静に話し合い、夫婦間で合意事項を整理していくための事前の計画のことです。
離婚は、人生における大きな転機の一つ。思いつきや一時的な感情で突き進むと、後悔しかねません。「どのように離婚を進めるか」をあらかじめ検討し、将来を見据えた計画を立てることは、スムーズな協議のために不可欠です。
思い立ったら初めに離婚計画を立てる
「もう離婚しかない」と思ったら、最初にやるべきは「感情から距離を置き、冷静に見つめ直すこと」です。怒りや悲しみなど、一時的な感情ではなく、心から離婚したいのか、見極めてください。
夫婦喧嘩は、どの家庭でも起こります。喧嘩の直後や、疲れてストレスが溜まっているときは、冷静な判断ができません。離婚は、人生に大きな影響を与える決断なので、立ち止まって、自分の本当の気持ちを見つめ直しましょう。
その上で、離婚後の生活を、具体的に思い描いてみてください。
住まい、収入、子育てや学校、生活環境など、現実的な生活設計を想像しましょう。離婚の現実味をより正確に把握できたら、「いつ、どのような条件で離婚するのか」、具体的な計画を立てます。相手に離婚の意向を伝えるより前に、準備をしっかり整え、必要な情報を集めて見通しを立てることは、話し合いを優位に進めるのに不可欠です。
「離婚までの流れ」の解説

離婚計画を立てることの重要性
感情に任せ、無計画に離婚を進めると、後悔が残ったり、紛争が長期化したりします。
例えば、離婚までの資金繰りが苦しいと、相手が足元を見てきた結果、納得いかない不利な条件で離婚せざるを得なかったり、最悪は離婚をあきらめるしかなかったりする人もいます。
そのため、離婚では、計画を立てることが特に重要です。離婚計画を早めに立てれば、感情を排除し、客観的な視点から、計画に従って淡々と進めることができます。その結果、納得感のある離婚を実現しやすくなるでしょう。
離婚の意思を伝えると、相手も警戒したり、好戦的になったりするおそれもあるので、離婚計画は必ず、離婚の意思を表明するよりも前に立てることが重要です。
離婚を思い立った時点で弁護士に相談しておくことで、法律知識に基づき、調停や訴訟の見通しを予想した上で、実効的な計画を立てることができます。
「モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

離婚計画にかかる準備期間

次に、離婚計画にかかる期間について解説します。
離婚を決意してから成立までには期間を要します。離婚計画の際は「いつから」「どれくらいの期間をかけて」進めるか検討しましょう。離婚時期の目標を設定し、そこから逆算して「いつ、何を準備すべきか」を考えてください。
一般に、離婚の準備には数ヶ月〜1年程度かかることが多いとされます。
次章「離婚計画で決めておくべきことは?」の準備を入念にするには、最低でも3ヶ月、丁寧に進めるなら半年〜1年を目安にするのが現実的です。
「すぐにでも離婚したい」と焦るのも分かりますが、無計画に進めると感情的な対立を拡大させ、離婚が難航します。仮に短期で離婚できても、条件の再交渉がトラブルを再燃させることもあります。
揉めるケースほど、期間も長めに見るべきです。協議で解決できるなら3ヶ月〜6ヶ月、調停に移行すれば更に3ヶ月〜6ヶ月、裁判なら1年〜2年を要するケースも珍しくありません。
子供や家族の事情に配慮するため、ライフイベントも考慮すべきです。子供の入学・卒業シーズンを避けたり、住宅ローンの返済状況を加味したりと、離婚の影響を最小限に抑える工夫をしましょう。無理に急がず、自分と家族にとって影響が少ないタイミングを見極めることも、後悔しない離婚計画のポイントです。
なお、法定離婚事由が存在せず、「長期の別居」を離婚理由として主張するケースでは、通常は3年〜5年、有責配偶者は8年〜10年の別居が目安とされます。
「離婚を◯年後に」と決める必要はないですが、無理ない計画を立てましょう。離婚までのスケジュールは、例えば、次のイメージです。
- まずは6ヶ月かけて資産を整理し、住居を準備する。
- 次の1ヶ月で証拠を収集する。
- 次の3ヶ月で、離婚条件について相手と話し合う。
- 1ヶ月ほどで離婚協議書の作成、離婚成立。
上記の例は、決断から離婚成立まで、約1年間の離婚計画となります。
調停や訴訟は更に時間を要するので、例えば「10年後に離婚したい」と考えるなら、6年目頃から準備し、7年目で別居、といった進め方となります。「5年で離婚したい」と思うなら、遅くとも4年目には離婚を切り出しましょう。
早めに計画しておくことが、最短で進める役に立ちます。
「離婚成立に必要な別居期間」の解説

離婚計画で決めておくべきことは?

次に、離婚計画において決めておくべき基本的な事項について解説します。
離婚に向けた具体的な計画を立てる際は、重要な離婚条件について事前に検討しておく必要があります。感情に流されず、冷静に「何をどう決めておくべきか」を把握することで、離婚手続きやその後の生活がスムーズに進められます。
離婚意思の確認
離婚計画を立てる際、大前提として「本当に離婚したいか」確認してください。
夫婦間のトラブルが重なると、感情的に「もう離婚したい」と思うことは少なくありません。しかし、一時的な感情に任せて決断するには大きすぎる選択です。経済面・精神面・子供への影響なども含め、「本当に離婚すべきなのか」、よく自問自答しましょう。
自身の離婚意思が固まったら、次は、相手との協議で離婚が可能か、それとも調停や裁判が必要か、相手の離婚意思の有無もまた、離婚計画に大きな影響を及ぼします。
「好きな人ができたので離婚したい」の解説

離婚理由の明確化
離婚に至る理由はそれぞれですが、計画段階で必ず明らかにしておきましょう。
典型的には、性格の不一致、家庭内暴力(DV)、不貞行為(浮気・不倫)、借金や金銭トラブル、精神的虐待などが挙げられます。自分にとっての「離婚の理由」を、離婚計画において具体的に整理しておけば、今後の争いの軸を明らかにすることができます。
特に、相手が離婚を望まず、裁判に発展するおそれのある場合、これらの事情が民法770条1項に定める「法定離婚事由」に該当するかどうかの確認が不可欠です。
離婚に向けた情報収集
有利な条件で離婚するには、知識と準備が求められます。
財産分与や養育費、親権、面会交流、年金分割など、離婚に伴って決めるべき各項目について、計画段階で基本的な法律知識を身につけておくことが重要です。あわせて、有利に離婚できるよう、証拠を収集してください。
協議離婚・調停離婚・裁判離婚といった離婚までのプロセスの違いや流れも把握しておくと、今後の手続きを適切に選択できます。情報の不足を補うには、弁護士に早めに相談してアドバイスを受けておくことが有益です。
「離婚に伴うお金の問題」の解説

離婚後の経済的な準備
離婚後の生活を安定させるには、経済面での計画も欠かせません。
離婚後に必要となる生活費を見積もり、現在の家計や相手の収入、資産状況を洗い出しておきましょう。預貯金、不動産、保険、年金、株式などの資産は、財産分与の対象になるかを精査し、全て把握しておいてください。離婚で転居を伴うなら、引越し費用や新居の家賃、保証人の有無なども事前に計画に盛り込まなければなりません。
子供がいる場合、教育費や養育費を考慮する必要があります。これらを踏まえて、具体的な収支計画を立てることで、離婚後の生活に必要な資金を確保しやすくなります。
「別居中の生活費の相場」の解説

子供への配慮
離婚後、子供の親権をどちらが持つかは、家庭裁判所でも大きな争点になります。
監護実績、生活環境、育児能力や子供との関係性などを考慮して、最終的には「子の福祉(子の利益)」を最優先にして判断されます。子供の年齢や性格によっても、必要な配慮が異なります。幼児期の離婚は不安定になりやすく、思春期に差し掛かる頃からは反発を示すこともあり、発達段階に応じた対応が求められます。
また、面会交流の方法(対面・電話・オンラインなど)、頻度、受渡し方法などを取り決めておくことも、離婚後のトラブル予防に繋がります。
場合によっては、子供の心理的ケアのため、スクールカウンセラーや児童相談所、医師の支援を検討すべきケースもあります。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

離婚計画書の作成方法
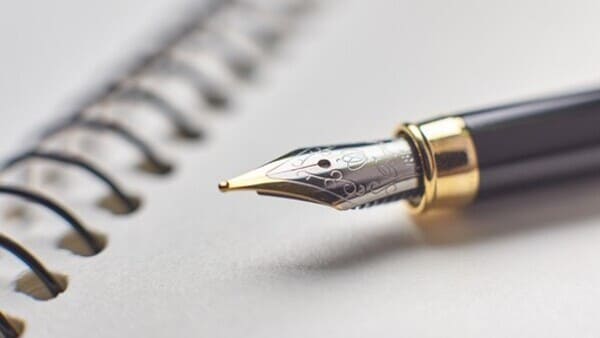
次に、離婚計画書の意味や書き方、記載すべき項目や作成のポイントを解説します。
離婚を計画的に進めるには、思考を整理し、今後の方針を明確にすることが不可欠で、これに役立つのが「離婚計画書」です。離婚計画書は、法律上必須の書類ではありませんが、自身の考えや希望、計画をまとめるのに役立ちます。
離婚計画書とは(書式)
離婚計画書とは、離婚に向けた自分の希望、どのような方針で進めたいかなどを整理した計画書です。つまり、自分用の「離婚の台本」と言えます。
混同されやすい「離婚協議書」は、離婚することとその条件について、合意内容を記した書面です。離婚計画書は、それとは異なり、あくまで個人的なメモに過ぎません。法的効果はないものの、自分の考えを可視化することで冷静に準備を進める役に立ちます。
書式に決まりはなく、ノートに手書きでも、WordやExcelでも構いません。内容も自由に決めてよく、状況に応じて更新や追加も可能です。例えば、次のテンプレートを参考にしてください。
離婚計画書
【離婚の方針】
- 離婚の目標時期: 年 月頃
- 別居期間 :
- 離婚の原因 :
(証拠となる資料 ) - 自分の名字:元の名字に戻る・結婚後の名字にする
【離婚後の生活】
- 住居:
- 当面のお金の工面:
- 離婚直後の収入:
【財産に関する方針】
- 財産分与:希望する・しない
(請求したい財産: ) - 慰謝料:希望する・しない
- 年金分割:希望する・しない
【子に関する希望】
- 親権・監護権:希望する・希望しない
- 養育費:希望する・希望しない
(月額 円程度) - 面会交流:希望する・しない
計画書を持参して相談すれば、計画の問題点を指摘してもらったり、離婚をスムーズに進めるためのアドバイスを受けたりできます。まだ離婚の気持ちが固まっていなくても、計画の段階から気軽に弁護士に相談することは有益です。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

離婚計画書に書くべき内容(一覧)
離婚計画書には、離婚までの予定を具体的に落とし込んでおくことが大切です。
必ず書かなければならない内容はありませんが、例えば、以下の項目をリストでまとめておくと、交渉や手続きに迷いがなくなります。
- 離婚の目標時期(例:子どもの卒業後、◯年◯月末など)
- 財産分与の希望(不動産・預貯金・自動車・保険など)
- 養育費の希望額・支払方法・期間(毎月◯円、大卒まで)
- 親権者・監護者の希望
- 面会交流の頻度・手段と費用負担(対面・オンライン、月に◯回など)
- 年金分割の取り扱い
- 退職金など将来の資産の取り扱い
- 離婚後の住居(名義変更、転居先、家賃やローンなど)
- 名義変更が必要なものの確認(車、免許証、保険、公共料金、銀行口座など)
- 氏・戸籍の変更に関する意思(婚氏続称、子の姓など)
- SNS上での振る舞い(SNSで離婚に触れないor発表するなど)
- 離婚後の連絡手段
これらの各事項について、事前に自分の希望を明文化しておくことで、相手と話し合う際や弁護士に相談する際に話がぶれにくくなります。また、心理的な不安を減らし、主導権を持って手続きを進めることにもつながります。
「離婚で弁護士を立てるタイミングは?」の解説

離婚計画の失敗と注意点

最後に、離婚計画にありがちな失敗と、その対策について解説します。
どれほど離婚を計画的に進めようとしても、実際には、想定外の事態や準備不足は、どうしても生じます。離婚計画における失敗例を事前に知れば、「やってはいけない点」や「見落としがちな点」を防ぐことができます。
離婚計画でよくある失敗
離婚の話し合いは、どうしても感情が先立ちやすい場面です。しかし、感情に任せて行動すれば、後から「不公平だった」「もっと慎重にすべきだった」と不満が生じるでしょう。
また、相手と口約束だけで条件を決めて、後日その内容を否定されて揉めるケースも非常に多いです。養育費や財産分与といった重要な取り決めこそ、書面に残して証拠化しておかなければ、後で未払いが生じて悔やむこととなります。
離婚計画を立てず、突発的に離婚を切り出してしまった結果、住居や収入の見通しが立たずに、離婚前後で生活が困窮してしまう人もいます。自分の離婚に集中するあまり、子供の不安や混乱に気付けず、親の都合で子供の心に深い傷を残してしまう危険もあります。
離婚は「別れ」ではなく「その後の人生の再設計」です。目の前の問題解決だけに集中するのではなく、俯瞰した視点で、計画的に進めなければなりません。
「離婚調停中にやってはいけないこと」の解説

離婚計画について弁護士に相談するメリット
離婚計画について失敗しないために、最も安心なのは弁護士に相談することです。
法律の専門家である弁護士は、財産分与や親権、養育費といった複雑な離婚条件についての知識を有し、正確なアドバイスを提供してくれます。法律相談の際、事前に作成した計画書の内容を見せながら説明すれば、状況を把握してもらいやすくなります。
相手との連絡がストレスになる場合、弁護士が代理人として対応することで、精神的な負担も大幅に軽減できます。特に、相手の態度が強硬なケースや、DV・モラハラのように身の安全に関わる場合、弁護士を通じたやり取りが安全です。調停や裁判といった法的手続きに進むにしても、弁護士と準備を進めることでスムーズに対応できます。
「離婚の弁護士費用の相場」の解説

まとめ

今回は、離婚計画についての基礎知識を解説しました。
離婚は感情だけで決断すべきものではなく、将来を見据えて計画的に進めることが大切です。そして、離婚に伴う手続きや合意事項は多岐に渡ります。そのため、冷静に離婚の計画を立てることでトラブルを防ぎ、自分や子供の生活を守るべきです。
離婚を考え始めた際にまず立てるべき計画と、具体的な内容、離婚計画書の作成方法を知っておくことは、円滑に離婚を進める助けとなります。
離婚を決断したら、一人で悩みを抱え込まず、必要に応じて弁護士など専門家の力を借りることも、後悔のない離婚のための大切な選択肢です。
- 離婚は、感情任せにせずに、計画的に進めることが重要
- 離婚計画を作成する際は、冷静な判断と入念な準備が成功のポイントとなる
- 離婚計画書を弁護士に見せて相談すれば、法的なリスクを回避できる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚条件に合意し、離婚届を提出することで成立します。この手続きは比較的簡単で迅速に進められる一方、難しい法律問題があっても自分達で乗り越えなければなりません。
合意内容が曖昧なままだと後にトラブルが生じるおそれがあるので、「協議離婚」の解説を参考にして進めてください。


