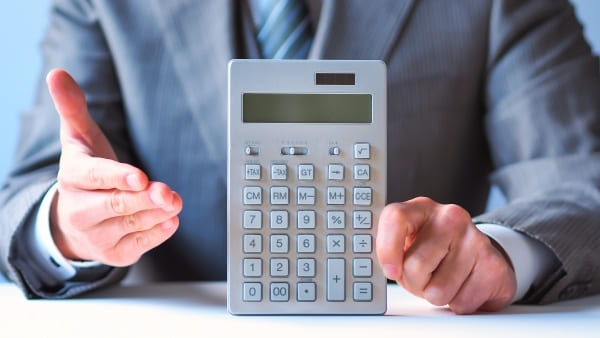残業代を請求する際には、正しい計算方法に基づいて正確に金額を算出しなければなりません。
計算を誤ると、本来受け取れるはずだった残業代を取り損ねるおそれがあります。残業代の計算方法は、労働基準法に定められていますが、正確に計算するには、法律の条文だけでなく、関連する政令や省令といった細かなルールも理解する必要があります。
実際に、労働者が残業代を請求した場合、企業側からは労働者とは異なる計算根拠をもとに反論されることが少なくありません。そのような場面では、法律知識に基づいて適切に再反論しなければ、正当な残業代を受け取れず損してしまいます。
今回は、未払い残業代を請求する上で必ず知っておきたい、残業代の計算方法と、その具体例について、弁護士が解説します。
- 残業代は、「基礎単価×割増率×残業時間」で計算される
- 残業代の基礎単価は、いわゆる「時給」であり、家族手当などは除外される
- 残業代の割増率は、時間外・休日・深夜という残業の種類によって異なる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
残業代の計算式

残業代の計算式は、次のとおりです(労働基準法37条1項)。
- 残業代 = 基礎単価(基礎賃金/月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間
関連する労働基準法の条文は、次の通りです。
労働基準法37条
1. 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1ヶ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2. (略)
3. (略)
4. 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
5. 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
残業代のことを、法律用語で「割増賃金」といいます。以下では、この計算式にある「基礎単価」「割増率」「残業時間」の各項目についてどう計算するか、順に解説します。
「未払い残業代請求」の解説

残業代の「基礎単価」

はじめに、残業代の計算式のうち「基礎単価」の計算方法を解説します。
残業代の基礎単価は、残業代の基礎となる賃金を、月平均所定労働時間で割ることによって求めることができます。これは、わかりやすくいえば「時給」を計算するということです。
- 基礎単価 = (給与 - 除外賃金) ÷ 月平均所定労働時間
上記は月給制の例ですが、それ以外の給与体系では、基礎単価は次のように計算します。
- 日給制のケース
日給額 ÷ 1日の所定労働時間数 - 週給制のケース
週給額 ÷ 1週間の所定労働時間数 - 日・週以外の一定の期間(半月給など)のケース
当該期間の給与額 ÷ 当該期間の所定労働時間数 - 出来高払制、請負制
算定期間の賃金総額 ÷ 総労働時間数 - 上記のうち複数からなる賃金体系
各部分につき、それぞれの計算方法で算定した金額の合計額
以下では、「残業代の基礎となる賃金と除外賃金」「月平均所定労働時間」について解説します。
残業代の基礎となる賃金と除外賃金
残業代の基礎となる賃金には、基本給や手当が含まれますが、次のものは、「除外賃金」とされ、残業代の基礎には含みません(労働基準法37条5項)。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
また、明示に「除外賃金」とはされませんが、あらかじめ残業代に充当する趣旨で支払われた金銭(例えば「固定残業代」「固定残業手当」「みなし残業代」「営業手当」)が残業代の基礎に含まれないのは当然です。これらを含んで計算すると、残業代が二重払いされてしまうからです。
家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当について
家庭の事情などを理由に支払われる、家族手当、通勤手当、住居手当、子女教育手当、住宅手当などの賃金は、残業代の基礎からは除外されます。
これらの除外賃金を残業代の基礎に含まないのは、いずれも労働時間に応じて払われるものではなく、労働者個人の事情によって払われるものだからです。そのため、これらの賃金を残業代の基礎に入れると、「家族の有無」「子供の有無」といった、労働の価値と無関係の理由で残業代の単価が変わり、公平性を欠いてしまいます。
なお、除外賃金に該当するかは、手当の名称ではなく実質で判断します。例えば、「住宅手当」と呼称されていなくても実質的に住宅費用に充当される手当は除外されますが、「家族手当」という名称でも全社員一律に支払われているなら含んで計算されます。
臨時に支払われれた賃金
除外賃金となる「臨時に支払われた賃金」の典型例は、賞与(ボーナス)です。また、慶弔手当、結婚手当、見舞金なども「臨時に支払われた賃金」に該当します。これらの費目は、事前に支払いが予想できず、必ず払われるわけでもないので、残業代の基礎とするのは不適切だからです。
行政通達(昭和22年9月13日発基17号)では、「臨時的、突発的事由に基づいて支払われたもの及び結婚手当等支給条件は予め確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するもの」と定義されています。
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
除外賃金となる「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」とは、「臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金」(労働基準法24条2項但書)と同じ意味です。1ヶ月を超えた期間ごとに払われるインセンティブや歩合給なども、除外賃金となります(一方、毎月支払われるインセンティブは、除外賃金ではありません)。
労働基準法施行規則によれば、次のものを指します。
- 賞与
- 1か月を超える期間の出勤成績に応じて支給される精勤手当
- 1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
- 1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当
これらの費目が残業代の基礎に含まれないのは、毎月の労働に対して支払われる金銭ではないからです。
なお、年俸制における賞与(ボーナス)は、あらかじめ支払われる金額が確定しているときは除外賃金とはならず、残業代の基礎に含まれます。
「年俸制の残業代」の解説

月平均所定労働時間
「所定労働時間」とは、会社が定める労働に従事すべき時間のことをいいます。すなわち、始業時刻から終業時刻までの間(休憩時間を除く)のことです。
1ヶ月の所定労働時間は、労働日数によって変わるので、残業代を計算するときには、年間の1ヶ月の所定労働時間の平均を計算する必要があります。
残業代の「割増率」

残業代の計算に用いられる「割増率」は、残業の時間帯に応じて次のように定められています。
なお、この割増率の定めはあくまで最低基準なので、就業規則・賃金規程にこれを超える割増率が定められている場合は、会社のルールに従った割増率で計算します。
| 労働の種類 | 割増率 | 内容 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 25%(月60時間超は50%) | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働 |
| 深夜労働 | 25% | 午後10時〜午前5時の労働 |
| 休日労働 | 35% | 法定休日(1週1日)の労働 |
これらの割増率は、併用して適用されます。例えば、「時間外労働かつ深夜労働」は50%、「時間外労働かつ休日労働」は60%、「休日労働かつ深夜労働」は50%となります。
「月60時間を超える」労働について適用される50%の割増率は、一定の基準を満たす中小事業主への適用が猶予されていました。しかし、働き方改革に伴う労働基準法の改正で、2023年4月1日以降は猶予措置がなくなり、中小企業も含めた全ての会社に適用されます。
「残業時間」の考え方

次に、残業代の計算式のうち「残業時間」について解説します。
「残業時間」とは、会社との間で約束した時間を超えて、実際に働いた時間のことで、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」である必要があります。
残業の種類に応じて、次のように定義されています。
- 時間外労働
法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働時間 - 休日労働
法定休日(1週1日もしくは4週4日)における労働時間 - 深夜労働
深夜の時間帯(午後10時以降、午前5時まで)における労働時間
重要なポイントは、残業代の対象となる「労働時間」といえるためには、「使用者の指揮命令下に置かれている」時間である必要があるという点です。
これは、必ずしも業務それ自体を行った時間と同じではなく、また、会社に滞在していた時間と同じでもありません。特に、仮眠時間、休憩時間、手待ち時間、移動時間、教育研修・教育訓練の時間、会社の飲み会など、本来の業務そのものではなくても、労働基準法上の「労働時間」にあたる可能性のある場合がある点に注意が必要です。
会社は、労働者の労働時間を把握しておかなければなりませんが、このように「労働時間」にあたるかどうかについて労使に対立が生じる可能性もあるため、労働者側としても、自分が「労働時間」と考える時間について、記録をとり、証拠化しておくことが大切です。
「労働時間に含まれるものとは?」の解説

残業代の計算方法【具体例】

残業代の計算方法を理解したところで、最後に、具体例でわかりやすく解説します。
残業代の計算は、次の順で行います。順番を逆にしてしまうと、計算結果が異なるおそれがあるので、必ず以下の手順で計算をしてください。
- 月給から除外賃金を差し引いて、残業の基礎となる賃金を算出する
- ①を月平均所定労働時間で割り、残業代の「基礎単価」を算出する
- ②に残業の時間帯に応じた「割増率」をかける
- ③に「残業時間」をかけ、残業代を算出する
では、残業代請求の具体的な方法をわかりやすく説明するため、事例で説明します。
以下の労働条件のケースで解説します。
- 基本給:30万円
- 営業手当:5万円 (就業規則・賃金規程に「営業手当は全額を時間外手当に充当する固定残業手当として扱う」と定められている)
- 家族手当:1万円 (就業規則・賃金規程に「家族手当は、扶養家族の人数1名につき1万円とする」と定められている)
- 通勤手当:実費相当額
- 歩合報酬:5万円 (就業規則・賃金規程に「歩合報酬は3ヶ月の営業成績をもとに、売上に一定の割合をかけ、3ヶ月に1度支給する」と定められている)
私は今月、45時間の時間外労働と、8時間の休日労働を行いました。Y社の年間所定労働日数は240日、Y社の所定労働時間は1日8時間、Y社の法定休日は週に1日(日曜日)でした。
私は、過酷な労働に対して、十分な残業代をもらえていないのではないかと疑問を抱き、弁護士に相談して残業代請求する決意をしました。
【1】残業代の基礎となる賃金を算出
相談者の月給のうち、残業代の基礎となる賃金は基本給だけです。
残業代に充当される営業手当、扶養家族数に応じて払われる家族手当、実費支給である通勤手当、3ヶ月ごとに支払われる歩合報酬はいずれも「除外賃金」であり、残業代の基礎からは除外されます。
したがって、残業代の基礎となる賃金は30万円となります。
【2】残業代の「基礎単価」を算出
所定労働日数、所定労働時間から、月平均所定労働時間は160時間となります(8時間(1日の所定労働時間)×240日÷12ヶ月)。したがって、残業代の「基礎単価」は1,875円(30万円÷160時間)。
【3】残業代の「割増率」をかける
残業代の「基礎単価」1,875円に、残業の時間帯に応じた割増率をそれぞれかけあわせると、次のようになります。
- 時間外労働(60時間以下):1,875円 × 1.25 = 2,343.75円 → 2,344円
- 休日労働:1,875円 × 1.35 = 2,531.25円 → 2,531円
なお、残業代の「基礎単価」の端数は50銭未満を切り捨て、50銭以上1円未満を1円に切り上げることが許されています。
【4】「残業時間」をかけ、残業代を算出
上記の時間外労働、休日労働の各単価に対し、残業時間をかけあわせ、残業代を算出します。
- 時間外労働(60時間以下):2,344円 × 45時間 = 10万5,480円
- 休日労働:2,531円 × 8時間 = 2万0,248円
最後に、残業代に充当するためにあらかじめ払われていた営業手当5万円を差し引いた金額が、最終的な請求額です。
- 10万5,480円 + 2万0,248円 - 5万円 = 7万5,228円
1ヶ月8万円弱の請求額があるとして、残業代の時効は「3年間」なので、ずっと同じ働き方をしてきた方であれば、288万円(8万円×36ヶ月)の請求が可能ということになります。
まとめ

今回は、労働基準法に基づく残業代の計算方法について、具体例を交えて解説しました。
計算方法の順序を誤ったり、適用すべき割増率を間違えたりすることで、最終的に請求できる残業代の金額に大きな差が生じる可能性があります。
残業代請求をめぐるトラブルでは、まず労働者側で、請求すべき残業代を計算し、その証拠を収集しなければなりません。そのため、どれくらいの残業代を請求できるのかを把握し、適切に計算することが重要です。正確な計算方法に基づかなければ、本来請求できるはずの残業代の一部を請求し損ねてしまうおそれがあります。
- 残業代は、「基礎単価×割増率×残業時間」で計算される
- 残業代の基礎単価は、いわゆる「時給」であり、家族手当などは除外される
- 残業代の割増率は、時間外・休日・深夜という残業の種類によって異なる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
残業代の未払いは、労働者の正当な権利を侵害する重大な問題です。
違法な未払いに泣き寝入りせず、労働基準法の知識に基づいた計算で、しっかりと請求することで、正当な対価を取り戻すことが可能です。
残業代請求の解説を通じて、必要な手続きや対処法をご理解ください。