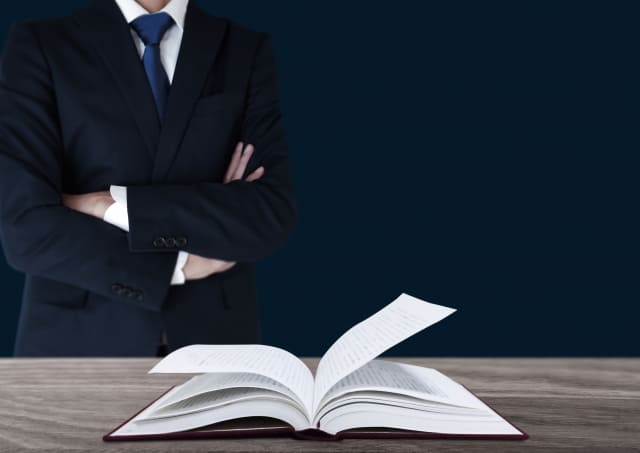委任契約は、人に仕事を依頼したいときの契約のことです。
弁護士や税理士、コンサルタントなどの専門家への依頼はもちろん、近年では副業や業務委託のフリーランスが増える中、ビジネスの世界では委任契約を締結する機会が増えています。他人や他社に業務を頼むことは、広い意味で「委任契約」となります。
一方で、委任のルールについて、民法の定めをよく理解しなければなりません。請負契約や雇用契約との区別も明確にしなければ、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。更に、2020年4月に施行された改正民法では、委任契約のルールにも重要な変更が加えられています。
今回は、委任契約の基本的な意味や仕組みと、民法改正のポイント、委任契約書を作成する際の注意点などを、弁護士が解説します。
- 委任契約における認識違いを避けるため、業務範囲は具体的に明記する
- 委任者は善管注意義務を負うため、有償・無償を問わず誠実に遂行する
- 委任契約が終了する際、報酬や費用、損害などの金銭トラブルに注意
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
委任契約とは

委任とは、当事者の一方が、他人に法律行為を委託することを指し、そのような当事者間の合意が「委任契約」です。
委任によって他人に法律行為を依頼する際は、結果を保証しない点に特徴があります。そして、民法には、委任の報酬や責任についてのルールが定められています。トラブルを未然に防ぐために重要なポイントは、類似の契約である「雇用契約」や「請負契約」との区別を理解し、適切な委任契約書を締結することです。
委任について定める民法643条は、次の通りです。
民法643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法(e-Gov法令検索)
「法律行為」とは、意思表示によって法律上の効果を発生させる行為のことで、委任の例には次のようなケースがあります。
- 弁護士に訴訟手続きを依頼する。
- 税理士に税務申告を依頼する。
- 不動産会社に売買仲介を委託する。
- コンサルティング業務を委託する。
- 医師と診療契約を締結する。
頼む内容が「法律行為」の場合を「委任契約」と言うのに対し、「事実行為」を委託することを「準委任」と呼び、区別することがあります(準委任にも、委任の規定が準用されます)。
委任契約の法的性質と特徴
委任契約には、次のような特徴があります。
委任契約の法的性質や特徴は、受任者(業務を引き受けた側)と委任者(業務を依頼した側)の責任分配や関係性を考えるのに重要なポイントとなります。
行為そのものの依頼である(結果は問わない)
委任契約は、「○○という行為をしてほしい」と頼む契約です。その行為そのものの依頼であり、結果の責任を負う契約ではない点が大きな特徴です。
例えば、弁護士への契約書チェックの依頼では、「契約書が適正なものかどうかを確認する」行為が依頼の対象であり、「訴訟に勝利する」「トラブルが起きない」ことを保証するものではありません。そのため、受任者は、委任された行為を遂行すれば、委任契約上の義務を果たしたことになります。
この点は、「仕事の完成」を目的とする請負契約との大きな違いです。
有償・無償のいずれでも成立する
委任契約は、仕事として依頼を受ける場合には有償であることが多いですが、無償でも成立します。無償であっても委任契約が成立した以上、受任者は一定の義務を負います。
善管注意義務(善良な管理者の注意義務)
委任契約において、受任者は委任者に対して、善良な管理者としての注意をもって業務を遂行する義務(善管注意義務)を負います(民法644条)。
民法644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
民法(e-Gov法令検索)
この義務は、有償か無償かを問わず、受任者に課せられた義務である点に注意が必要です。他人のために行動する以上、最低限の注意を払うべきという趣旨であり、一般的に、例えば次のような配慮が求められます(弁護士、税理士など、立場によって特別な義務を負うこともあります)。
- 法令を遵守し、契約の規定に従った行動を取る。
- ミスをしないよう正確な業務遂行を心がける。
- 委任者にとって不利益となる事態を未然に防ぐ。
この義務を怠り、委任者に損害を負わせた場合には、受任者は債務不履行責任や損害賠償責任を問われることとなります。
類似の契約との違い
委任契約は、「人に依頼する」という点では「請負契約」「雇用契約」と混同されやすいですが、それぞれの違いを明確に理解することがリスク回避のために重要です。また、人に頼むという意味では、「代理」と似た側面もあります。
請負契約との違い
請負契約は、仕事の完成を目的として、成果物の納品を伴う点が特徴です。
この点で、依頼された業務の遂行を目的とし、結果や成果を問わない委任と異なります。委任であれば、業務の遂行に応じて報酬が発生しますが、請負は、成果物が完成しなければ報酬を得られないのが原則です。
また、委任契約の受任者は善管注意義務違反の責任を負うのに対し、請負契約の請負者は、これに加えて成果物に関する契約不適合責任を負います。
「契約不適合責任」の解説

雇用契約との違い
雇用契約は、労働者を雇い、使用者の指揮命令下で働かせ、賃金を払う契約です。
委任との大きな違いは、使用者の指揮命令下で一定の拘束を受けることです。就業時間や場所を指定されるのが原則である代わりに、労働法による法的な保護を受けられます。例えば、雇用なら、最低賃金以上の対価が保証され、決められた時間以上に働けば割増賃金(残業代)を請求できるほか、一方的に辞めさせる「解雇」は制限されます。
なお、形式は「業務委託契約」とされても、実態として指揮命令関係にあれば、労働者性が認められて労働法による保護を受けられる場合があります。このような違法状態を「偽装請負」と呼びます。
「偽装請負の判断基準」の解説
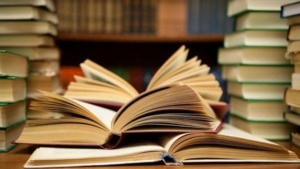
委任と代理の違い
代理とは、代理人が本人に代わって意思表示を行い、その効果を本人に帰属させる制度です。有効な代理となるためには、民法に定められたルールに従って「顕名(本人のために代理することを示すこと)」「代理権の授与」などの要件を満たす必要があります。
委任契約を締結するにあたり、合わせて代理権を授与することがあります。
ただし、全ての委任契約で代理権を授与するわけではなく、代理を伴わない委任もあります。また、法定代理人(例:未成年者の親権者、成年後見人など)のように、委任契約がなくても代理権が生じるケースもあります。
「代理の基本知識」の解説

委任契約を締結する際の注意点

次に、委任契約を締結する際に押さえておくべき注意点を解説します。
委任契約は、「契約自由の原則」に従って、委任する業務の内容や報酬の条件について、当事者が自由に決めることができます。ただし、柔軟である反面、内容が曖昧なまま契約してしまうと、「どこまでやってくれるのか」「報酬はいつ、いくら発生するのか」といった疑問が生じ、トラブルの原因ともなりかねません。
特に、2020年の民法改正によって委任のルールは変更されたため、従前の委任契約書のひな形を流用している企業では、契約書の整備と見直しが必須となっています。
書面で契約内容を明確にする
委任契約は、口頭でも成立しますが、委任契約書を作成することをお勧めします。
契約に関する重要な事項は、契約書に記載することで明確化し、当事者間に認識のズレが生じないように配慮すべきです。委任の際に作成する契約書は、「委任契約書」「業務委託契約書」といった名称とするのが通例です。
委任契約は成果物の納品がないため、「どの範囲の業務を任せていたか」「業務を適切に遂行したのか」といった点が曖昧になりやすく、当事者間の期待値に差があると紛争化しがちです。少なくとも以下の内容は明記しておいてください。
- 委任する業務の内容と範囲
- 報酬の条件(金額・支払条件など)
- 経費負担に関する取り決め
- 契約期間と終了条件、更新の有無
- 秘密保持に関する規定
- 契約違反の責任追及(解除・損害賠償など)
委任契約書の書式は、例えば次の通りです。あくまで文例・ひな形であり、個別のケースに合わせて修正・追記が必要となります。
委任契約書
◯◯◯◯株式会社(以下「甲」という)と、△△△△株式会社(以下「乙」という)とは、甲が乙に対して業務を委任するにあたり、以下の通り委任契約を締結した。
第1条 甲は乙に対し、別紙一覧記載の業務(以下「本業務」という)を委任し、乙はこれを受任した。なお、業務の進め方は、本契約書に定めるほか、乙の裁量に委ねるものとする。
第2条 甲は乙に対し、本業務の対価として、月額◯◯円(消費税込)を、毎月末締め、翌月末日払いとして、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う(振込手数料は甲負担)。なお、本業務の遂行に必要な交通費、通信費その他の実費は、甲の事前承諾を得たものに限り甲の負担とする。
第3条 本契約の期間は、20XX年XX月XX日から3ヶ月とする。期間満了の1ヶ月前までに甲乙のいずれかが異議を述べない場合には、同条件で更に3ヶ月間更新されるものとし、以降も同様とする。なお、契約期間途中で終了した場合には、暦日数に応じた報酬を請求できるものとする。
第4条 乙は、善良な管理者の注意をもって本業務を誠実に遂行するものとし、甲の書面による事前承諾を得ない限り、本業務の再委託は禁止とする。
第5条 甲及び乙は、相手方に対し、30日前までに書面で通知することで、本契約を解除することができる。ただし、解除に伴って相手方に損害が生じた場合には、賠償する義務を負うものとする。
第6条 乙は、本業務の遂行に際して知り得た甲の営業上・技術上の一切の秘密情報を本業務遂行以外の目的に使用せず、正当な理由なく第三者に漏洩・口外してはならない。この義務は本契約終了後も存続する。
第7条 甲及び乙は、本契約の違反によって損害が生じた場合は、その損害の賠償を請求できるものとする。ただし、乙の賠償責任の範囲は、受領した報酬額を上限とする。
第8条 本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【作成日・署名】
報酬と費用負担を取り決める
委任契約は無償でも成立しますが、ビジネスの場面で用いられるとき、大半は有償契約となります。この際、報酬の定め方が曖昧だと、トラブルの元となります。
そのため、委任契約書には、次の内容を具体的に記載しておく必要があります。
- 報酬の金額(または算定方法)
- 報酬の支払い時期(例:月末締め翌月末払い)
- 報酬の支払い方法(例:振込、手渡しなど)
- 交通費・通信費その他の実費の負担者
- 成果完成型の場合の成果物・支払条件(民法648条の2)
なお、委任契約が中途で終了する場合に備え、契約期間の途中で終了した際の報酬の支払いや費用の精算についても明記しておくとトラブルの予防に効果的です。
委任の終了事由を定める
民法上、委任契約は原則として各当事者がいつでも解除できます(民法651条1項)。
これは、委任関係が当事者の信頼関係に基づくので、信頼が損なわれた場合にまで維持するのは適切ではないからです。しかし、実務では、委任者による身勝手な解除が受任者の業務に支障を生じさせたり、逆に、受任者による解除で代替の手配が困難となったりしてトラブルになるおそれがあります。このリスクを避けるため、以下の条項を明記することが重要です。
- ○日前の予告による解除が可能。
- 不利な時期の解除は損害賠償責任を伴う(民法651条2項)。
- 双方協議によって解除することができる。
- 解除する際は引継ぎや資料の返還義務を負う。
なお、不利な時期の解除のほか、受任者の利益も目的とする委任についても、生じた損害を賠償する義務が生じる可能性があります(「解除に伴う効果の明記」で後述)。
秘密保持義務・損害賠償条項を検討する
委任契約を遂行するに際しては、しばしば企業秘密や個人情報のやり取りが発生します。そのため、特に受任者に対して、秘密保持義務を課す条項が必須となります。
秘密保持条項に盛り込むべきポイントは、以下の通りです。
- 対象となる「秘密情報」の定義
- 情報の使用目的(委任業務の範囲内に限定する)
- 第三者への漏洩禁止
- 契約終了後の資料の返還や廃棄の義務
- 違反時の損害賠償または違約金
委任者は、できるだけ責任追及を容易にしておきたいでしょうが、一方で、受任者としては不注意や過失によって大きな賠償義務を負ってしまわないよう、責任の範囲を限定したり、賠償額に上限を設定したりといった委任契約書の修正を要望することも検討すべきです。例えば、受任者の立場では「重過失のある場合に限る」「通常損害の賠償に限る」「損害賠償の上限は報酬総額までとする」といった規定を提案してください。
2020年の民法改正による委任契約の変更点

2020年4月1日に施行された改正民法は、契約実務に大きな影響を与えており、その中で、委任契約に関する条文にも変更が加えられています。改正法を理解することは、委任者・受任者のいずれの立場でも重要となります。
以下では、改正のポイントと、それに伴う実務上の影響を解説します。
受任者の自己執行義務の明文化
改正前の民法は、受任者自らが契約内容を実行すべき義務は明記されていませんでした。
しかし、委任契約は当事者間の信頼を基礎としており、代理のルールは別に設けられていることから、委任では受任者自身が処理するのが原則と解釈されていました。このような解釈から、受任者が第三者に処理を任せる「復委任」は、例外であると考えられてきました。
しかし、解釈に頼るのは明確さを欠き、「誰が委任事務を遂行するか」「責任を誰が負うのか」が不透明となるおそれがありました。このリスクを解消するため、改正後の民法は、委任契約において受任者が自ら委任事務を処理する義務(自己執行義務)を規定しました。
したがって、改正後は、委任契約は受任者が自ら遂行するものとし、例外的に「委任者の許諾を得たとき」「やむを得ない事由があるとき」に限って副受任者を選任できます(民法644条の2第1項)。
また、復委任が許される場合に、復受任者は委任者に対し、受任者と同一の権利を有し、義務を負うことが明記されました(民法644条の2第2項)。
「民法改正(2020年4月施行)」の解説
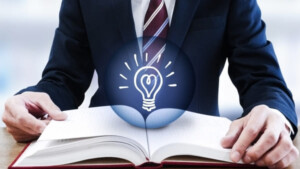
中途終了の場合の報酬ルールの整理
改正前民法では、受任者の「帰責事由(落ち度)」なく委任契約が中途で終了した場合、既に行っていた委任事務の割合に応じて報酬を請求できることとされていました。しかし、その他の理由で中途終了した場合の報酬のルールはなく、個別の事案に応じて判断されていました。
改正後の民法では、委任契約が中途終了した場合の報酬のルールが整理されました。
改正後の民法は、委任契約を「履行割合型」と「成果完成型」に分類し、この類型ごとに報酬に関するルールを定めています。
履行割合型の報酬について
履行割合型の委任契約とは、事務処理そのものに対して報酬を支払う場合です。例えば、月々一定の作業を依頼し、月額報酬を支払うケースが該当します。
履行割合型の委任契約の場合、民法648条3項の通り、委任者の帰責性なく委任事務が履行できなくなったときや、委任の履行が中途で終了したときは、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」と定められています。したがって、履行割合型の委任契約が中途で終了した場合の報酬ルールをまとめると、以下のようになります。
- 中途終了の責任が委任者にあるとき
報酬を全額請求できる。 - 中途終了の責任が受任者にあるとき
既に行った履行割合に応じて請求できる。 - 中途終了の責任がいずれにもないとき
既に行った履行割合に応じて請求できる。
成果完成型の報酬について
成果完成型の委任契約とは、事務処理の成果に応じて報酬を支払う場合です。例えば、一定の成功を獲得した場合に報酬を払うことを約束したケースが該当します。成果完成型は、仕事の完成後に報酬を請求できる点で、請負契約と似た性質があります。
成果報酬型の報酬について、改正前は法律の定めがなかったところ、2020年施行の民法改正で新設されました(請負に関する規定が準用されています)。
成果完成型の委任契約の場合、民法648条の2の通り、報酬は成果の引渡しと同時に支払われることになっています。また、請負に関する民法634条が準用され、注文者の帰責性なく仕事が完成できないときや、請負が仕事の完成前に解除されたときは、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できます。したがって、成果完成型の委任契約が中途で終了した場合の報酬のルールをまとめると、以下のようになります。
- 中途終了の責任が委任者にあるとき
報酬を全額請求できる。 - 中途終了の責任が受任者にあるとき
利益の割合に応じて請求できる。 - 中途終了の責任がいずれにもないとき
利益の割合に応じて請求できる。
ただし、利益の割合に応じて請求するには、成果が可分で、かつ、その成果が委任者にとって利益があることが要件となります。
解除に伴う効果の明記
改正民法においては委任の解除のルールも明確化されました。
民法651条は、委任契約は、各当事者がいつでも解除できることを定めると共に、相手方に不利な時期に解除したときや、受任者の利益をも目的とした委任を解除したとき、相手方の損害を賠償しなければならないことを定めています(ただし、やむを得ない事由があった場合を除く)。
この規定は委任契約に関する従来の裁判例(最高裁昭和56年1月19日判決)を踏まえ、解除による不利益については損害賠償で調整することを示したものです。委任契約解除についてのルールを整理すると以下のようになります。
- 原則:いつでも解除可能
- やむを得ない事由があるとき
損害賠償の必要はない。 - やむを得ない事由がない場合
- 相手方に不利な時期に解除したとき
→損害賠償しなければならない。 - 受任者の利益をも目的とした委任を解除したとき
→損害賠償しなければならない。
- 相手方に不利な時期に解除したとき
委任契約に関するよくあるトラブルと対策

最後に、委任契約に関するよくあるトラブルと対策を解説します。
委任契約は、柔軟で汎用性の高い契約形態ですが、それゆえに、契約内容が曖昧なまま契約されやすく、トラブルを招きがちです。委任契約を軽く見ることなく、法的な紛争に発展するおそれのあるケースでは、できるだけ早めに弁護士に相談するのがお勧めです。
業務範囲に関する認識の違い
委任の範囲が不明確だと、委任者としては「ここまでやってくれると期待していた」、受任者からすれば「この報酬では、その業務は範囲外だ」というように考えが対立し、その結果、委任の報酬が未払いとなるなど、トラブルになります。
委任契約は、「成果」ではなく「行為」に報酬が払われるからこそ、業務の範囲が曖昧なまま、受任者の判断に委ねるのは非常に危険です。
トラブルが起こらないように対策を講じるには、委任契約書に具体的な業務内容、業務の範囲を明記するようにします。単に業務名として特定するだけでなく、業務仕様書や作業スケジュールを別途添付する方法も効果的です。第三者との間で、委任を受けた範囲を明らかにするために、委任状を作成しておくのもよいでしょう。
委任契約書のリーガルチェックを行う
委任契約に伴うトラブルを防ぐには、契約締結時点でのリーガルチェックが重要です。
インターネット上にある委任契約書のテンプレートは便利ですが、民法改正に未対応だったり、個別の事情に応じたリスクが反映されていなかったりするので、そのまま使用するのは危険です。関係性にもよりますが、委任者側が契約書を準備することが多いので、その取引に特有のリスクをきちんと回避できる契約書となるよう、弁護士に作成を依頼するのが賢明です。
また、委任契約書を提示された受任者の側でも、契約書のチェックを行い、自身に不利な条項がないか、重すぎる義務や責任を負わされていないかを確認してください。
弁護士に早めに相談する
前章のように、委任契約をめぐるトラブルを避けるには、契約を締結してしまう前にリーガルチェックをすべきであり、それには豊富な法律知識を必要とします。そのため、契約書のチェックは弁護士に依頼するのがお勧めです。
顧問弁護士として日常的に相談している専門家に依頼すれば、自社の業務内容や取引先との力関係など、個別の事情を加味してカスタマイズしてもらうことができます。
契約交渉の段階から弁護士が関与することで、リスクを事前に洗い出し、交渉方針を立てやすくなります。また、弁護士のチェックを受けた契約書で取引を進めれば、いざ紛争化した際にも、交渉や訴訟などの手続きをサポートしてもらうことができます。
「顧問弁護士の費用(顧問料)」の解説

まとめ

今回は、委任契約と、委任契約書の注意点について解説しました。
委任契約は、日常的な業務の委託から専門家への依頼まで、「人に頼む」際に幅広く活用される契約形態です。委任契約の際は、委任の範囲や報酬、終了時の対応などを明確にしておかないと、後にトラブルに発展するおそれがあります。これらの点は、委任契約書に具体的に明記すべきです。
2020年4月に施行された民法改正を踏まえて、適切な委任契約書を締結することが、委任で失敗しないための重要なポイントとなります。これまでのひな形の流用だと、改正法に対応していないおそれがあります。契約を結ぶ際は、契約書の内容をしっかりと確認し、不安な点があれば弁護士のリーガルチェックを受けるのがお勧めです。
委任に関する法律の定めを正しく理解し、適切に対処すれば、信頼関係のある業務委託関係を築くことができます。
- 委任契約における認識違いを避けるため、業務範囲は具体的に明記する
- 委任者は善管注意義務を負うため、有償・無償を問わず誠実に遂行する
- 委任契約が終了する際、報酬や費用、損害などの金銭トラブルに注意
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
民法の改正は、契約や取引、債権債務など、生活や企業経営に密接に関わります。改正の内容を正しく把握しなければ、思わぬトラブルを招くおそれもあります。
適切な権利行使をするためにも、民法改正に関する解説記事を通じて、最新のルールを理解しておいてください。