代理は、「人の代わりに法律行為をすること」で、暮らしやビジネスの現場でも、日常的に多く活用されます。しかし、代理行為が有効となるためには、法律に定められた要件を満たさなければならず、代理の要件を満たさない場合は、法律行為が無効となるおそれもあります。
また、代理人が自己の利益のために権限を濫用したり、本来の代理権を逸脱した行為を行ったりすると、思わぬトラブルに発展する危険もあります。この場合、問題ある代理行為によって害される第三者の保護も必要となります。
今回は、代理の基本的な仕組みや、代理行為が有効となるための要件、代理権を逸脱・濫用した場合の法的な扱いについて弁護士が解説します。なお、2020年の民法改正で変更された点もあるので、あわせて紹介します。
- 代理行為は、本人に代わってその名で法律行為をし、効果は本人に帰属する
- 代理権がなければ原則無効だが、追認や表見代理で有効になる可能性あり
- 2020年4月施行の改正民法で、代理のルールがより明確化された
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
代理とは
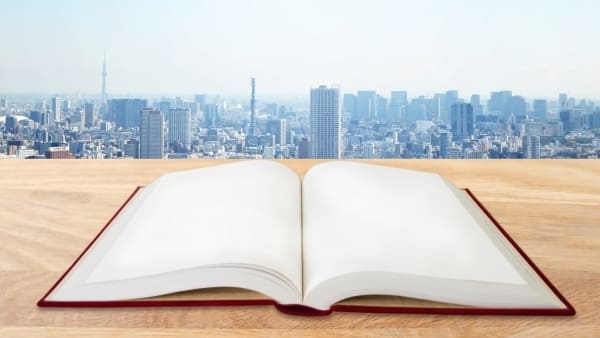
代理とは、代理人が、本人の名で代わりに意思表示を行い、その法律効果を直接本人に生じさせる制度です。民法99条は、代理について次のように定義しています。
民法99条(代理行為の要件及び効果)
1. 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2. 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
民法(e-Gov法令検索)
例えば、「本人Aの代理人として、あなたと売買契約を締結します」と意思表示をして契約を締結するケースが典型例で、この場合、契約の効果(所有権の移転や代金の支払い義務など)は、代理人ではなく本人Aに帰属します。
法的な意思表示は、本来、当事者が自らの意思で行うのが原則です。しかし実際は、本人が全ての取引に直接関与するのが難しいケースも少なくありません。例えば、会社の代表者が出張中で契約に立ち会えないケース、高齢者が不動産売買するにあたり親族の助けを借りたいケースなどは、代理を活用することでトラブルを未然に防ぎ、取引をスムーズに進めることができます。
代理制度の目的
民法に定められた代理の制度には、大きく2つの目的があります。
取引の円滑化
社会生活やビジネスで、本人が常に契約や手続きの現場に立ち会えるとは限りません。
代理制度を活用すれば、代理人が本人の代わりに意思表示を行い、その効果を本人に帰属させることで、時間的、物理的な制約を度外視して取引することが可能となります。特に、ビジネスの場面では、社長に代わって担当者や支店長が、事業に関する重要な決定や契約を行う裁量を与えられていることが多いです。
本人の保護
一方で、民法に定められた代理制度のルールは、本人を保護する手段でもあります。
例えば未成年者や認知症の高齢者など、自ら法律行為を適切に行うことができない人を保護するためにも、代理を活用することができます。特に、弱者保護の観点では、親権者や成年後見人などが「法定代理人」として、民法上の要件を満たす場合に法律行為を代わりに行ったり、取消権を行使したりなど、本人の財産や法的地位が不当に害されないよう保護する役割を果たします。
代理と似た他の制度との違い
代理について正しく理解するために、似た制度である「使者」や「委任」との違いを知っておくことが重要です。
使者との違い
使者とは、本人の意思をそのまま第三者に伝える人のことです。
代理が、本人に代わって意思決定まで行うのに対し、使者に意思決定権はなく、本人が決定した意思をそのまま届けるだけの役割を担います。例えば、「この契約書を渡してほしい」「◯◯と伝えてほしい」というのが使者であり、「代わりに契約をしてきてほしい」というのが代理人です。
したがって、代理と使者の違いは「意思決定を委ねられているか」という点にあります。
委任との違い
委任とは、民法の定型契約のうち、委任者が受任者に一定の法律事務の処理を依頼する契約です。つまり、「私の代わりに◯◯をしてほしい」という意味である点で、代理と共通する部分があります。
委任は、委任者と受任者の内部的な契約関係であるのに対し、代理は、対外的な第三者との関係を規律するルールです。
委任契約を結ぶことで受任者に一定の代理権を与えることがあるので、重複する部分はありますが、「委任=代理」ではありません。委任契約を結んでも、代理権を与えない(もしくは範囲を制限する)ことがあり、代理権のいない事項について受任者といえど本人の名で契約を結ぶことはできません。逆に、法定代理であれば委任契約がなくても代理できます。
代理行為の要件

次に、代理行為が有効と認められる要件と、満たさなかった場合の効果を解説します。
代理人が行った意思表示の効果を本人に帰属させるには、法律の定める要件を満たす必要があります。この要件を満たさなければ有効な代理行為とはならず、代理の効果が本人に帰属しない「無権代理」となります。
代理行為の成立に必要な3つの要件
民法上、代理行為が有効に成立するためには、以下の3つの要件が必要です。
顕名
代理人が行為をする際、「自分は本人のために行っている」と第三者に明らかにすることを「顕名」といいます。例えば、「Aの代理人として、Bと売買契約を締結します」と言って契約するケースが典型例です。
顕名がないと代理であることがわからないので、代理人自身のために行ったものとみなされ、本人に効果が帰属しません。ただし、相手方が代理であることを知り、又は知ることができたときは、顕名が形式的に欠けていても有効な代理行為になります(民法100条)。
代理権の存在
代理人は、本人から適法に代理権が授与されている必要があります。代理権が授与されていない、または、授与された権限を超えた行為は、「無権代理」として無効です(民法113条)。例えば、代理権を与えられていないのに「A代理人」と称して契約を結んだ場合、本人はその契約に拘束されません。
なお、無権代理でも、本人が追認した場合には有効な代理としてその効果が本人に帰属します。また、本人に外観を作出した責任があるなど一定の場合には「表見代理」となります(詳細は「要件を満たさない「無権代理」は無効」参照)。
代理権の種類には、任意代理と法定代理があります。
法律行為であること
代理は「売買契約」などの法律行為が対象となります。
法律行為とは、意思表示によって法律上の効果を生じさせる行為のことで、単なる事実行為は代理の対象とはなりません。つまり、代理人が「本人に代わって法律効果を生じさせる意思表示を行う」という性質の行為にのみ、代理制度が適用されます。
要件を満たさない「無権代理」は無効
代理の3つの要件のいずれかを欠くと、「無権代理」として無効になります。
無権代理の効果は、本人には帰属しません。代理権が存在しない場合や、代理人が代理権の範囲を逸脱した越権行為を行った場合、無権代理となり、相手は本人に契約の履行を求めることはできません。ただし、本人がその行為を追認すれば有効な代理行為となります(民法116条)。
一方で、代理人に代理権がなく、本人も追認をしなくても、「表見代理」の場合には相手方は代理人に対して一定の責任(履行または損害賠償)を追及できる場合があります(詳細は「表見代理の要件」参照)。
代理権の逸脱や濫用があった場合

次に、代理権の逸脱・濫用があった場合の効果について解説します。
代理制度では、代理人に一定の権限を与えることで、本人に代わって法律行為を行えます。その一方で、代理人がその権限を越えた行為をしたり(逸脱)、与えられた権限を悪用したり(濫用)した場合、その代理行為の有効性が問題となります。
代理権の逸脱や濫用があると、「無権代理」として無効になるのが原則ですが、本人と第三者の保護の調整から、例外的に「表見代理」として効力を有する場合があります。
代理権の逸脱・濫用は無権代理となる
代理権の逸脱・濫用は、いずれも無権代理として無効になるのが原則です。逸脱と濫用の違いは、次のように区別されます。
- 代理権の逸脱
代理人が、与えられた代理権の範囲を越えた行為(越権行為)をした場合。例えば、本人が「不動産の賃貸契約を代理してほしい」と権限授与したのに、代理人がその不動産を売却してしまったケースです。 - 代理権の濫用
代理人が、形式的には代理権の範囲内で行為していても、本人ではなく自己または第三者の利益を図る目的で行為した場合。例えば、「本人のために金銭を借りる」代理を依頼されたのに、自身の借金返済に充てようとして消費貸借契約を締結したケースです。
代理権の逸脱・濫用はいずれも無権代理となり、本人が追認しない限り無効です。つまり、本人が「その契約を有効なものとして認める」と意思表示しなければ、その契約は履行されません。
無権代理が行われると、相手方となった人の地位が不安定になる危険があります。そのため、相手方の保護のため、次の2つの制度が設けられています。
表見代理の要件
無権代理であっても、一定の要件を満たすと「表見代理」として代理人による意思表示が有効になることがあります。表見代理は、外見上は代理行為が有効に行われているように見えたため、それを信じた相手方を保護するための制度です。
表見代理が成立するには、外観を作出したことについて本人に一定の帰責性があり、相手方が善意無過失であることが必要となります。表見代理が成立すると、本人に効果が帰属します。
本人の帰責性について、表見代理が成立する場面ごとに、次の3つの類型があります。
代理権授与の表示による表見代理
民法109条は、本人が代理人に代理権を与えたことを第三者に示した場合、(たとえ実際には与えていなくても)その代理権の範囲内で責任を負うことを定めています。なお、表示した代理権の範囲外の行為には、次の民法110条が重畳適用されることがあります。
権限外の行為による表見代理
民法110条は、実際に代理権はあるが、その権限外の行為をした場合に、第三者が代理人の権限があると信じるべき正当な理由があるとき、本人が責任を負うことを定めます。
代理権消滅後の表見代理
民法112条は、かつて存在していた代理権が、消滅したことを過失なく知らなかった第三者に対して、本人がその責任を負うことを定めています。なお、存在していた代理権の範囲外の行為については、上記の民法110条が重畳適用されることがあります。
代理制度に関する民法改正のポイント(2020年4月施行)

次に、代理制度について、2020年4月1日施行の改正民法による変更点を解説します。
代理人が制限行為能力者である場合の規定
法律行為を一人で有効に行う能力を「行為能力」といい、行為能力が制限された人を「制限行為能力者」といいます。代理行為の効果は本人に帰属し、代理人には生じません。そのため、代理人は不利益を受けないので、民法改正前後を問わず、制限行為能力者でも代理人になることは可能です(代理人として行った法律行為は、制限行為能力を理由に取り消すこともできません)。
改正後の民法102条は、「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない」と定めました。つまり、制限行為能力者が、他の制限行為能力者の法定代理人となった場合には、その代理行為は取り消せることが新たに規定されました。
これは高齢化社会に対応したもので、例えば、認知症の高齢者の成年後見人もまた判断能力の乏しい配偶者だった場合を想定し、社会的弱者の保護を強化するためのものです。
「民法改正(2020年4月施行)」の解説
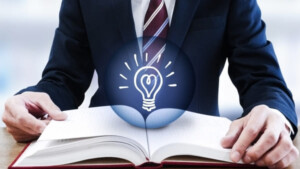
復代理人を選任した任意代理人の責任
代理人が選任した代理人を、「復代理人」と呼びます。
改正前の民法では、復代理人を選任する場合、本人の許諾か、やむを得ない事由が必要とされ、また、復代理人の行為による責任も限定的に解釈されていました。具体的には、復代理人の不注意などによって本人に損害を与えた場合でも、任意代理人は「復代理人の選任、監督に関する責任」を負うだけでした。また、本人の指名に従い復代理人を選任した場合は、「不適任・不誠実であることを知りながら、本人にその旨を通知すること、復代理人を解任することを怠った場合」にのみ責任を負うこととなっていました。
これに対し、改正後の民法は、復代理人の選任は代理人が自己の責任で行うものとし、その際の責任は軽減されないことを定めています(やむを得ない事由がある場合に限って、選任と監督の責任のみを負う)。改正に伴い、代理を活用する場合、代理権授与を定める契約書で、復代理の可否、その際の責任範囲や責任制限を厳密に定める必要性が増しました。代理人就任後も、復代理人を選ぶ際は軽率な選任を避け、監督を怠らないことが大切です。
自己契約・双方代理
自己契約とは、自分が当事者となる契約について相手方の代理人となること、双方代理とは、当事者双方の代理人となることを指します。
改正前の民法には自己契約及び双方代理をした場合の効果に関する規定がありませんでした。改正民法では、自己契約、双方代理は、無権代理として無効になると定めました。加えて、改正民法では、従来の判例を明文化し、形式的に自己契約や双方代理を禁止するだけでなく、実質的な利益相反も、本人の許諾がない限り禁止であると定められました(民法108条)。
代理を有効活用するための注意点

最後に、代理を活用する際に、本人・代理人・相手方のそれぞれの立場で注意すべきポイントを解説します。代理制度は、本人が第三者との取引に直接関与しなくてもよい便利な仕組みですが、その反面、無権代理になるなどトラブルに発展するリスクもあります。
代理権の有無と範囲を明確化する
まず、本人の立場では、相手方との間で誤解が生じて思わぬ責任を負わされないよう、代理権の有無と範囲を明確化することを心掛けてください。任意代理の場合、代理権の授与は口頭でも可能ですが、証拠を残すために書面(委任状や契約書など)に明記しておくべきです。
少なくとも、次の事項については、書面で明確化しておいてください。
- 代理人の氏名・住所
- 代理権の具体的な内容と範囲
- 代理可能な期間
- 復代理人の選任の可否
重要な法律行為を任せる場合には、より正式には、委任状に実印を押し、印鑑証明書を添付する方法がお勧めです。
相手方は代理権の確認を怠らない
代理人と契約を結ぶこととなった相手方の側でも、不安定な立場に立たされないよう、その人に代理権があるのか、そして代理権の範囲内なのかを慎重に確認すべきです。特に、以下の場面で注意を怠ると、大きな損失を被ってしまいかねません。
- 高額な取引(例:不動産の売買、事業譲渡など)
- 過去に取引履歴のない代理人
- 契約内容が不自然である(例:あまりにも有利である、不利であるなど)
確認の手段としては、代理人に委任状の提示を求めることが第一です。その上で、心配なときには本人に連絡を取って確認する作業を怠ってはなりません。相手方の代理権の有無を確認せずに取引をした場合、「過失がある」と評価され、表見代理の保護を受けられないおそれがあります。
代理人も違法行為をしないよう注意深く行動すべき
代理人となった場合にも注意深く行動しなければ、逸脱・濫用をしてしまいかねません。万が一、相手方との契約が無権代理になると、本人が追認しなければ契約は無効です。この場合、代理人が相手方から、契約が無効となったことで損害賠償を請求される危険があります。
逸脱・濫用を防ぐためにも、代理人もまた本人との間で代理権の範囲を明確化しておく努力をすべきです。また、代理行為が継続的に行われる場合には、定期的に報告をし、本人の監督を受けておくのが安全です。
まとめ

今回は、代理に関する法律知識を解説しました。
本解説は、「代理人」の立場となる方はもちろん、代理人を使って契約をしようとする人、相手が代理人を立ててきたときの対応など、全ての人に知っておいてほしい内容となっています。
代理は、本人が直接関与しなくても、代理人を通じて法律行為を行うことのできる、便利な仕組みです。しかし、代理行為を有効にするには、「代理権が存在し」「顕名を行う」といった要件を満たす必要があります。これらの要件を欠けば、「無権代理」として無効になる危険もあります。また、代理権の範囲を逸脱した行為や、代理権の濫用があった場合にも、契約の効力が否定される可能性があり、本人・代理人・相手方のいずれの立場でも、慎重な対応が求められます。
2020年4月施行の民法改正のルールを知ることは、無権代理や表見代理の問題を解決するにも大切です。代理の関わる契約行為について不安のある方は、ぜひ一度弁護士に相談してください。
- 代理行為は、本人に代わってその名で法律行為をし、効果は本人に帰属する
- 代理権がなければ原則無効だが、追認や表見代理で有効になる可能性あり
- 2020年4月施行の改正民法で、代理のルールがより明確化された
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
民法の改正は、契約や取引、債権債務など、生活や企業経営に密接に関わります。改正の内容を正しく把握しなければ、思わぬトラブルを招くおそれもあります。
適切な権利行使をするためにも、民法改正に関する解説記事を通じて、最新のルールを理解しておいてください。


