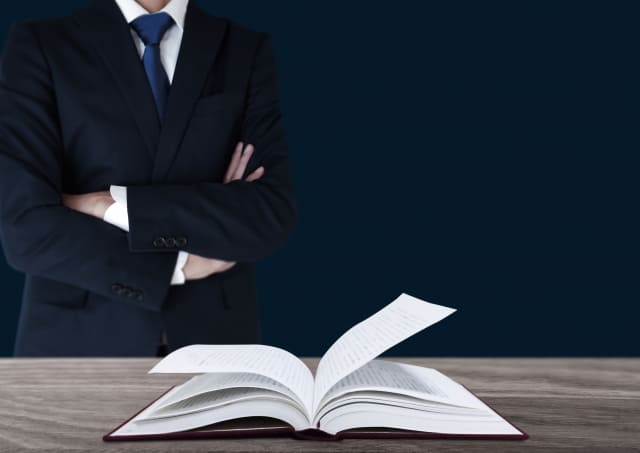2020年4月1日に施行された民法の改正により、従来「瑕疵担保責任」と呼ばれていた制度が、「契約不適合責任」という新たなルールへと生まれ変わりました。この変更で、売買契約や請負契約など、商品や成果物を納品する契約では、買主や注文者が、売主や請負人の責任を追及しやすくなりました。一方で、企業のリスク管理のためには、より丁寧な契約書作成が求められます。
とはいえ、「契約不適合責任」という言葉はまだ馴染みが薄く、その意味や責任の内容、追及方法や期間制限などの法律知識をよく理解しなければなりません。
今回は、契約不適合責任に関する知識について弁護士が解説します。取引におけるトラブルを未然に防ぐために、ぜひ参考にしてください。
- 契約不適合責任は、2020年の民法改正で瑕疵担保責任に代わって導入された
- 契約に不適合かどうかを判断するため、契約内容の特定が重要となる
- 売主側では免責条項が重要、買主側は契約内容をよくチェックすべき
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
契約不適合責任とは

はじめに、契約不適合責任の基本的な法律知識を解説します。
契約不適合責任の定義と内容
契約不適合責任とは、売買契約や請負契約において、売主や請負人が引き渡した目的物が「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に、債務不履行の責任を負う制度です(民法562条以下)。2020年4月1日施行の民法改正によって、従来の「瑕疵担保責任」は廃止され、契約不適合責任に一本化されました。
契約不適合責任について定める民法の条文は、次の通りです。
★ 契約不適合責任に関する民法の条文
民法562条(買主の追完請求権)
1. 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2. 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
民法563条(買主の代金減額請求権)
1. 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。2. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3. 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
民法564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。民法565条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。民法566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
民法(e-Gov法令検索)
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
契約不適合責任は、わかりやすく説明すると、買主などが契約内容と異なる物を受け取ったときに、売主などの責任を追及する制度です。改正前の瑕疵担保責任が「隠れた瑕疵」に限定されたのに対し、契約不適合責任は、引き渡された目的物が「契約の内容に適合しているかどうか」を重視します。そのため、責任を検討する際は「契約で合意された内容」が重視されます。
契約に適合しているかどうかの判断では、当事者の合意や契約の趣旨、契約に至った経緯などが考慮されます。
契約不適合責任は、法定責任(無過失責任)とされた瑕疵担保責任とは異なり、債務不履行責任の特則と位置づけられます。つまり、民法の契約責任のルールに基づいて判断されるので、実務においても、改正後は契約書の内容の重要性がより高まります。
買主や注文者は、契約不適合がある場合、次の4つの救済手段を選択できます。
- 履行の追完請求(修補や代替物の引渡し)
- 代金減額請求
- 損害賠償請求(売主に帰責事由がある場合)
- 契約の解除(重大な不適合で目的が達成できないとき)
このように、契約不適合責任は、旧法の瑕疵担保責任よりも柔軟で、実務に沿った内容となっています。その分、当事者の合意内容や、それに適合した履行がされたかどうかを慎重に判断しなければなりません。
契約不適合責任が適用されるケースの例
契約不適合責任は、主に以下の契約において適用されます。
売買契約
契約不適合責任の中心となるのが売買契約です。
動産・不動産を問わず、引き渡された物が契約の定める仕様・数量・品質などに適合しない場合、契約不適合責任を追及できます。例えば、土地の売買契約で想定外の地中埋設物が発見されたケース、購入した製品が仕様書通りに動作しないケースなどが該当します。
請負契約
請負契約においても、完成した仕事の成果物を納品します。このとき、成果物が契約内容に適合していない場合には、請負人は契約不適合責任を負います。
例えば、建築請負で建設された建物が設計図通りではなかったケース、ITのシステム開発で仕様書通りでなかったケースなどは、契約不適合であると判断されます。
M&A(株式譲渡契約・事業譲渡契約など)
株式や事業を譲渡する契約も、対象会社や資産、債務の内容が表明保証に違反する場合、契約不適合とみなされることがあります。ただし、M&Aは取引額が高額となりやすく、民法における契約不適合責任に加えて、契約書に表明保証条項などを定めるのが通例であり、契約上の責任が優先されます。
ビジネス取引の場合
商人間での売買契約においても、契約不適合責任が適用される場合があります。
ただし、商人間での「BtoB」の取引では、民法に優先して商法が適用されます。その結果、買主は受領時に検査をすべき点(商法526条1項)、契約内容に適合しないことを発見した時は直ちに通知しなければならない点(直ちに発見できないとしても、受領後6か月以内に発見して通知する必要がある)といった注意が必要です(商法526条2項)。したがって、商人間の取引の方が、契約不適合責任の追及のハードルが高くなっています。
その他の有償契約
契約不適合責任は、対価の発生するその他の有償契約にも適用されます。例えば、交換契約や消費貸借契約、賃貸借契約などでも、目的物が契約に適合しない場合には、契約不適合責任を検討することができます。
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い

次に、契約不適合責任と旧法の瑕疵担保責任の違いについて解説します。
契約不適合責任は、2020年4月1日の民法改正によって、従来の瑕疵担保責任に代わって導入された制度です。両者はいずれも、目的物に問題があった際の売主などの責任ですが、その内容や要件には違いがあります。
瑕疵担保責任の特徴
改正前の民法における瑕疵担保責任には、次の特徴があります。
- 対象は「隠れた瑕疵」に限られる
瑕疵担保責任では、通常備えるべき性能・品質を欠く瑕疵が存在し、かつ、買主が契約時点でその存在を知らなかった(善意無過失)場合に限って責任追及が可能とされていました。そのため、買主が瑕疵を知っていた場合や、注意すれば発見できた場合は、売主は瑕疵担保責任を負いません。 - 無過失責任である
瑕疵担保責任は、売主の過失を要しない「法定責任」とされ、売主に落ち度がなくても責任追及が可能でした(なお、免責の特約を設けることは可能)。 - 主に特定物売買に適用される
改正前の民法は、「特定物売買は、引渡しによって履行済みとなる」と考えられていたため、瑕疵担保責任は債務不履行ではなく、特別な担保責任とされていました。 - 救済手段が限定的である
瑕疵担保責任で買主に認められているのは、「損害賠償請求」か「契約解除」に限られ、追完請求や代金減額請求などの柔軟な救済手段は、法律に定めがありませんでした。 - 通知期間が除斥的だった
瑕疵担保責任は、瑕疵発見から1年以内に請求しなければなりません。また、単に「通知」するだけでなく、請求の意思を表示することが必要とされていました。
これらの瑕疵担保責任の特徴はいずれも、旧制度の弊害として責任追及をしづらくしており、契約不適合責任に変更される理由となっています。
契約不適合責任の変更点
瑕疵担保責任と比べると、契約不適合責任には次のような特徴があります。
- 判断基準は「契約内容に適合するかどうか」
「瑕疵」という抽象的な基準を改め、「契約で定めた内容(種類・品質・数量など)に適合しているかどうか」を基準に判断されます。これにより、当事者間で合意した仕様や性能と異なれば、「瑕疵」かどうかにかかわらず責任追及が可能となります。 - 「隠れた瑕疵」に限定されない
買主が契約締結時に不適合を知っていた場合でも、それが契約の内容として容認されていたと解釈されない限り、契約不適合責任の追及が可能です。つまり、買主の善意無過失は不要となり、責任の追及がしやすくなりました。 - 追完請求・代金減額請求が明文化された
改正民法では、修補や代替物引渡しによる「履行の追完請求」、不適合の程度に応じた「代金減額請求」が明文で認められ、買主の救済手段が大幅に拡充されました。また、損害賠償請求と契約解除についても、債務不履行のルールが適用されます。 - 通知義務の緩和
買主は不適合を知ったときから1年以内に「通知」すれば足り、旧法のように明確な権利行使までは要求されていません。更に、売主に故意または重過失がある場合は、通知義務自体が不要とされ、買主保護が図られています。
民法改正による実務上の影響
2020年4月施行の民法改正で、瑕疵担保責任が契約不適合責任に改められたことは、企業の契約実務に大きな影響を及ぼしています。
契約不適合責任では、「契約内容に適合しているか」が責任の基準となるので、契約書や仕様書、設計図などに、目的物の要件を明確に定めておくことがこれまで以上に重要となります。また、契約による定めが優先されるため、特に売主の立場では、責任の範囲や期間の限定、免責の特約を設けるといった方法により、リスクをコントロールする意識が不可欠です。
以上の点から、改正前に使用していた契約書は、アップデートが必要となります。単に「瑕疵担保責任」と書かれた部分を「契約不適合責任」と書き換えるだけでなく、その根本にある考え方をよく理解して、現在の法制度と整合した内容に修正しなければなりません。
「民法改正(2020年4月施行)」の解説
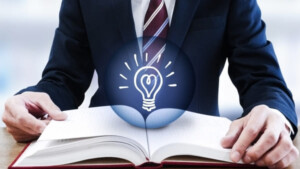
契約不適合責任を追及する具体的な方法
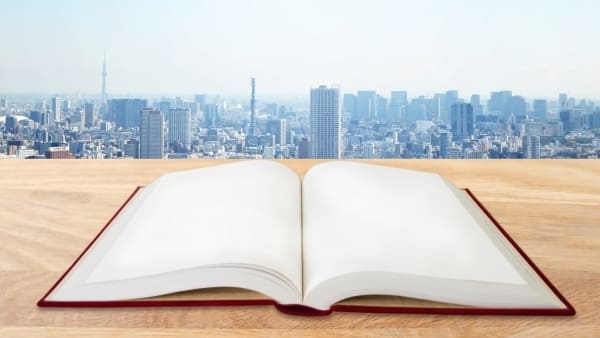
次に、契約不適合責任を追及する方法と、その要件や期間について解説します。
契約不適合責任が認められる場合、買主や注文者は民法の定めに基づき、複数の手段から救済を選択して実行することができます。
契約不適合責任に基づいて行使できる法的手段
民法562条から564条の規定によって、契約不適合責任が認められる場合に行使できる法的手段は、以下の4つが定められています。
履行の追完請求(民法562条)
買主は、目的物が契約に不適合であるとき、売主に対し、履行の追完を請求できます。履行の追完は、具体的に次の方法で請求します。
- 修補(欠陥の修理や改修)
- 代替物の引渡し
- 不足分の引渡し
この追完請求は、売主の帰責性を問わず請求可能であり、契約本来の内容に適合する給付を受ける権利です。したがって、明らかに価値が異なる製品を要求するなど、買主に不相当な負担を課すことは許されません。
なお、不適合が買主の責めに帰すべき事由(例:買主の指示ミスや仕様変更)によって生じた場合、追完請求権は認められません。
代金減額請求(民法563条)
買主が相当の期間を定めて履行の追完を催告しても、その期間内に売主が履行しないときは、代金の一部の減額を請求することができます。この際、不適合の程度に応じた金額を協議によって決めるのが原則です。
例えば、「1週間以内に、契約の内容に基づいてあと◯個追完するように」と指示しても、期日通り履行されなかったときに減額請求をする例があります。
なお、追完が不能、または売主が明確に拒絶している場合は、催告せずに減額請求をすることが可能です。
損害賠償請求(民法564条、415条)
損害賠償請求は、契約不適合が売主に帰責性のある債務不履行に該当する場合に行うことができます。この際に請求できる損害は、履行利益(契約が履行されれば得られた利益)と信頼利益(契約が有効と信じたことによる出費など)に分けられます。
損害賠償請求をするには、売主の帰責事由(故意または過失)が必要なので、不可抗力や第三者の原因による不適合では請求できません。また、請求できる賠償の範囲は、通常損害(債務不履行により通常生じる損害)と特別損害(逸失利益などの特別の事情によって生じた損害)に分けられます。特別損害を請求するには、当事者がその事情を予見すべきであったといえる必要があります(民法416条2項)。
なお、損害が買主側の過失で拡大した場合は、過失相殺(民法418条)によって減額されることがあります。
契約解除(民法564条、541条・542条)
契約不適合が、契約の目的を達成できない程度に重大である場合は、買主は契約を解除することができます。解除の原則に従って、まず履行を催告し、相当期間内に履行がないことを条件としますが(民法541条)、以下の場合には無催告解除が可能です(民法542条)。
- 履行が不能な場合
- 売主が履行を拒絶している場合
- 履行を受けても契約目的が達成できない場合
解除によって契約は遡及的に消滅し、代金の返金や目的物の返還といった原状回復義務が生じます。
「契約の解除」の解説

権利行使期間と通知義務
契約不適合責任を追及するには、買主による通知が必要です。民法566条は、買主が契約不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主に通知することが必要としています。
この通知は、権利行使そのものではなく「不適合の事実を知らせる」旨で足りるので、改正前の民法に比べて要件が緩和されています。期間内の通知を怠れば、履行の追完請求、減額請求、損害賠償請求、解除のいずれも行使できなくなります。
ただし、以下のケースでは例外的に、期間の制限を越えて責任追及できます。
- 売主が契約不適合を知りながら告げなかった場合
売主が悪意であるとき、1年の通知期間にかかわらず買主の権利行使が認められます。 - 数量不足や権利の不適合の場合
同条文の文言上、通知期間の制限は適用されません。
また、契約不適合責任に基づく請求権について、一般の債権と同様に消滅時効(知った時から5年間、または権利発生から10年間)が合わせて適用されます(民法166条)。
契約書で特約を定めた場合
法律には、当事者の合意によっても変更できない「強行規定」と、当事者の合意が優先する「任意規定」があります。
契約不適合責任は任意規定なので、当事者の合意によって特約を定めることができます。例えば、契約書に定められることの多い特約には、次のものがあります。
- 契約不適合責任を免除・制限する特約
責任を免除、制限する特約も原則として有効です。ただし、売主が不適合を知りながら黙っていた場合は、免責は無効となります(民法572条)。 - 通知期間を短縮・延長する特約
通知期間を契約で変更することも可能です。ただし、あまりに短い期間は買主に酷であり、消費者契約法や信義則を理由として無効となる可能性があります。 - 損害賠償の範囲や金額を制限する条項
例えば、直接損害に限ること、逸失利益を除外すること、損害賠償に上限を設けることといった特則が考えられます。
このように、契約書の文言次第で契約不適合責任の範囲・期間・内容は大きく変動します。特に、法人間取引(BtoB)では詳細な責任分配の交渉・記載が不可欠です。
契約不適合責任が免責される場合
次に、例外的に、契約不適合責任が免責される場合について解説します。
契約書に免責条項がある場合
前述の通り、契約不適合責任は任意規定なので、契約書で責任を制限したり、免除したりすることができます。例えば、次の文言があるケースです。
- 「売主は本物件について契約不適合責任を一切負わない」
- 「引渡し後◯か月以内に通知がなされた場合に限り、契約不適合責任を負う」
- 「契約不適合責任の内容は、修補対応に限る」
- 「請負者の損害賠償義務は、請負報酬を上限とする」
ただし、民法572条は、売主が不適合を知りながら告げなかったときには免責の特約が無効となることを定めています。また、契約不適合によって生じた損害のうち、「生命・身体に対する損害」など特に重大なものまで免責する規定は、公序良俗違反(民法90条)として無効となる可能性があります。
また、消費者契約法、宅建業法など、弱者を保護するための特別法が適用される場合には、免責条項は更に厳格に制限されます。例えば、宅建業法40条は、不動産取引で売主が宅建業者のとき、引渡しから2年以内の契約不適合責任を免除できないことを定めます。消費者契約法10条は、「消費者の利益を一方的に害するもの」は無効であると定めており、買主を不当に害する特約は無効となります。
買主・注文者側に過失がある場合
契約不適合の原因が、買主や注文者自身の指示や過失によるものである場合にも、契約不適合責任は生じません(民法562条2項、563条3項)。例えば、以下のケースでは免責が認められます。
- 注文者が誤った仕様書や設計図を提供した場合。
- 契約時の容認事項となっていた場合。
- 契約内容として折り込み済みの不具合だった場合。
なお、不適合を買主が知っていただけでは、契約不適合責任の発生を妨げませんが、それが契約内容に含まれていた(黙示の合意があった)と評価される場合、責任を負わないこととなります。
納品後の改変や使用による不具合の場合
売主が引渡した時点では契約に適合していた場合、その後の変化による不具合は、契約不適合責任の追及が難しいことがあります。例えば、以下のケースでは免責が認められます。
- 精密機器を適切でない環境下で使用して故障した場合。
- 建築物に買主が独自の改修工事をした結果、不具合が発生した場合。
- 長期間経過による自然劣化や消耗(経年劣化)。
これらの場合、売主としては、契約時点で目的物が適合していたことと、その後の不具合が買主側の誤使用や不注意、経年劣化によることを証明するため、証拠の収集が欠かせません。
契約不適合責任をめぐるトラブルと契約書の注意点

最後に、契約不適合責任に関するトラブルと、未然に防止するための契約書上の注意点について解説します。契約不適合責任は、特に、建築や不動産、IT開発、製造業といった分野でよく争点となるので、未然に防止するには専門家の視点で契約書チェックをするのが有効です。
契約不適合責任をめぐるトラブルの例
契約不適合責任をめぐるトラブルの具体例は、次の通りです。
中古不動産の売買後、地中埋設物が発見された事例
土地の売買契約で、引渡し後に地中から産業廃棄物が発見された事例。
買主は、契約書の内容に適合していないと主張して、売主に対して損害賠償請求をすることができます。地中埋設物の存在は、通常の不動産取引では想定されておらず、買主も容認していないと考えるのが通常です。
ITシステム開発で、仕様の不適合が発覚した事例
ITシステム開発で、発注者が求めていた機能の実装がなく、当初予定していた目的に合わせた運用が不能となった事例。
ベンターが「要件定義通り」と反論することが多いですが、この際、委託契約の内容に適合しているかどうかの基準は、契約書のほか、仕様書や開発時のミーティングの議事録などの証拠によって証明されるのが通例です。
リフォーム工事での施工不良があった事例
内装業者にリフォーム工事を依頼したところ、引き渡し後に雨漏りが発覚した事例。
施工業者からは「引渡し前に検査済みである」と反論することがありますが、図面や設計図などに示された契約内容に適合していない場合には、契約不適合責任の追及が可能です。不適合が軽微であれば、補修や損害賠償の請求で対応するケースが多いです。
契約書上の注意点と予防策
契約不適合責任は、契約交渉から履行に至るまで、様々な場面で問題となります。ただ、紛争は、契約書の作成時に注意しておけば防げるものも多くあります。
- 契約書・仕様書の記載を明確にする
目的物の種類や数量、品質、性能など、適合する基準を具体的に記載するよう注意してください。抽象的な記載をすると、「不適合かどうか」を判断する基準も曖昧になってしまいます。 - 検収と通知義務に関する条項を設ける
検査方法や期間、合否判定の基準を明確化しておく必要があります。また、実際に責任追及するための通知方法を定めることで、トラブルを防止できます。 - 責任範囲の限定や免責条項を設ける
責任を負う売主側では、修補対応に限定したり、責任を免除したりといった条項を設けることも検討してください。また、知りながら告げなかった場合には免除条項が無効となってしまうため、開示義務を果たすことも重要となります。 - 表明保証条項を設ける
特にM&Aなどの複雑な取引では、表明保証条項を設けて、責任追及を詳細に定める必要があります。この場合、契約不適合責任との重複を防ぐために、責任の範囲や優先順位も規定しておくことが多いです。
また、契約書をしっかりと整備しても、実際の運用を怠っては意味がありません。そのため、万が一にトラブルが生じたときの体制整備も欠かせません。弁護士などの専門家と連携して、いざトラブルとなった際に迅速に調査、是正などの対処ができるよう準備してください。
まとめ

今回は、契約不適合責任の考え方について、民法改正を踏まえて解説しました。
契約不適合責任は、民法改正によって新たに導入されたルールであり、従来の瑕疵担保責任よりも柔軟で、契約実務に即した制度となっています。具体的には、契約内容に適合しない目的物が引き渡された場合に、売買契約の買主や請負契約の注文者は、追完請求・代金減額・損害賠償請求・契約解除といった様々な手段で売主や請負人の責任を追及することができます。
一方で、責任追及に制限があるほか、契約書の内容によって免責される場合があります。責任追及を受ける側もまた、特に不動産など高額な取引になるケースほど、民法改正を踏まえた適切な契約書を用意することでリスクを軽減する必要があります。
契約不適合責任を正しく理解することで、万が一トラブルが起きた際にも適切に対処し、法的リスクを最小限に抑えることができます。法改正を踏まえた契約書チェックに不安があるときは、早めに弁護士に相談してください。
- 契約不適合責任は、2020年の民法改正で瑕疵担保責任に代わって導入された
- 契約に不適合かどうかを判断するため、契約内容の特定が重要となる
- 売主側では免責条項が重要、買主側は契約内容をよくチェックすべき
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
民法の改正は、契約や取引、債権債務など、生活や企業経営に密接に関わります。改正の内容を正しく把握しなければ、思わぬトラブルを招くおそれもあります。
適切な権利行使をするためにも、民法改正に関する解説記事を通じて、最新のルールを理解しておいてください。