交通事故後の治療は、被害回復のための重要なプロセスです。しかし、保険会社から「治療費の打ち切り」を通告されると、通院や治療を継続できるのか、その際の治療費についてどのように対応すべきか、疑問が生じることでしょう。
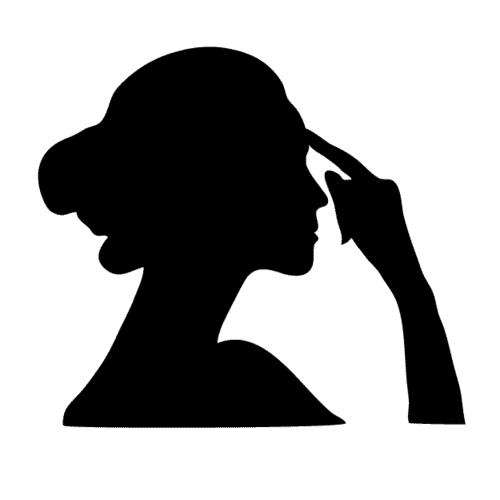 相談者
相談者保険会社に「治療費は3ヶ月まで」と言われた
 相談者
相談者まだ痛みが引かないから通院し続けたいのに…
加害者側の保険会社は、できるだけ支払う賠償額を抑えるために、事故から3ヶ月、6ヶ月といった節目のタイミングで「治療費の立替払いを打ち切る」という通告をしてきます。しかし、あくまで保険会社の立替払いが止まるだけで、通院や治療は継続するのが正しい対応です。保険会社の言うなりになって通院をやめれば、将来得られる賠償額が下がってしまうからです。
本来、治療の必要性は医学的に判断すべき、かつ、治療費や慰謝料などの損害額は裁判所が判断すべきであり、保険会社が決めるものではありません。
今回は、治療費が打ち切りとなる理由や保険会社の判断基準、そして、治療を継続するための方法について弁護士が解説します。
- 加害者側の保険会社から治療費打ち切りを言われても、通院を継続する
- 治療費を打ち切りにされないためには、診断書と弁護士の交渉がポイント
- 治療費の打ち切り後も通院し、後から適正な損害賠償を請求する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
交通事故の治療費の打ち切りとは

はじめに、交通事故の治療費の打ち切りとはどのような意味か、解説します。
交通事故の治療費の打ち切りの問題とは、事故後に保険会社から「治療費の立替払いを打ち切る」と通告されることで起こる法的トラブルです。事故の態様や症状にもよりますが、むちうちのケースだと3ヶ月〜6ヶ月程度で「打ち切り」の連絡が来ることが多いです。
重要なのは「治療費の打ち切り後も通院は継続すべき」の通り、保険会社による治療費の立替払い終了後も、通院や治療は継続すべきである点です。
保険会社が治療費打ち切りを通告する理由
保険会社が、治療費の支払いを途中で終了する背景には、次の理由があります。
保険会社側では、不要な支出を防ぐために、戦略的に治療費の打ち切りを通知してきていることを理解してください。
支払う賠償額を抑えたい
交通事故による治療期間が長引くと、治療費が増加するのは当然、それだけでなく通院交通費、休業損害、入通院慰謝料といった賠償額も増加し、最終的な支払い総額が高くなります。加害者側の保険会社としては、できるだけ自社の負担を抑えようとして、治療費の打ち切りを通知します。
保険会社(任意保険)としては、自賠責保険から一定の金額を回収できますが、その上限は120万円とされており、これを超える分は自社の負担です。そのため、交通事故による追加の支払いリスクを回避することが、治療費打ち切りの背景にあります。
不適切な治療を防ぎたい
治療費の打ち切りを通知するのは、必要以上に長期間の治療が行われることを防ぐ意味があります。交通事故の被害者の中には、症状がないのに「詐病」で通院を継続して、過大な賠償金の獲得を目指す人がいます。
したがって、治療費の打ち切りを言い出す保険会社には、実際の通院の必要性を見極め、不要な治療はさせず、不正な賠償金請求を排除する目的があります。
治療費の打ち切りを通知されるタイミング
以上の通り、治療費の打ち切りは、保険会社の考えとして「これ以上の治療は不要」と評価できるタイミングで行われるのであり、実際の治療の必要性とは整合しないことがあります。
例えば、治療費の打ち切りを通知されやすいタイミングは、以下の通りです。注意して通院や治療を行い、できるだけ打ち切りを避けるよう行動するのがよいでしょう。
平均的な治療期間を越えたとき
平均的な治療期間の相場を超えると、保険会社から打ち切りを言われやすいです。
持病や既往症などで、特に長い治療が必要となる場合、「特別な損害」として賠償の対象とならない可能性があります。また、長過ぎる治療は「詐病」を疑われる原因となります。保険会社としては、通常は症状が安定したり改善したりするであろうと思われる期間ごとに、治療費の打ち切りを通知してくるのが一般的です。
とはいえ、被害の状況は事故態様や被害者ごとに異なるので、まだ治療が必要な場合には、医師の診断書などをもとに支払いを継続するよう交渉すべきです。
治療の間隔が空いたとき
通常、事故直後の治療は、連続的に行われることが望ましいです。
そのため、治療の間隔が空くと、「もはや必要性が薄れている」または「症状が十分に改善されている」と見られ、治療費の打ち切りを通知されるリスクがあります。また、しばらく期間が空いてから治療を再開した場合、その後の治療は「交通事故による被害ではないのでは」というように因果関係を疑われるおそれもあります。
リハビリに移行したとき
リハビリテーションへの移行は、事故直後の急性期治療が一段落し、患者の症状がある程度落ち着いたと判断されるサインと評価されることがあります。そのため、リハビリに移行すると、治療は終了して症状固定となったとされ、保険会社から追加の治療費を打ち切られるおそれがあります。
治療費の打ち切り後も通院は継続すべき

交通事故から一定の期間が経過すると、保険会社から治療費の打ち切りを通告されることがありますが、その後も通院を継続するのが適切な対応です。というのも、保険会社の言うなりになって通院を止めてしまうと、被害者にとって次のような不利益があるからです。
保険会社による治療費の打ち切りは、あくまで「保険会社による立替払いの終了」を意味するに過ぎないので、治療の必要性があるときは通院を継続してください。
治療費や休業損害が請求できなくなる
通院を止めてしまうと、その後の治療費や休業損害が請求できなくなります。治療の必要性があるなら通院を継続し、立替払いされなかった治療費や、支払いを拒まれた休業損害は、症状固定後にまとめて交渉や裁判で請求すべきです。
症状固定と判断されやすい
通院を止めると、その時点で症状固定となったと判断されやすいです。
症状固定は、「これ以上治療しても症状が改善しない状態」であり、「完治」とは異なります。交通事故の賠償は、症状固定までは治療費や休業損害を請求でき、症状固定後は治療費が払われない代わりに、後遺症が残存した場合に後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。
症状固定が早まると、その後の治療費や休業損害を請求できないだけでなく、後遺障害が認められづらくなる危険があります。
入通院慰謝料が低額となる
入通院慰謝料は、交通事故による入院・通院によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料で、入通院の期間が長いほど高額となります。したがって、治療費の打ち切りを通告されたからといって通院を止めると、通院期間は短くなり、入通院慰謝料が低額になってしまいます。
後遺障害等級の認定が得られない
後遺障害等級の認定判断は、継続的、かつ長期間通院を続けているほど、より高い等級の認定を得やすく、請求できる慰謝料や逸失利益を増額することができます。特に、「他覚的所見のないむちうち」では、症状の残存を認めてもらうには継続的な通院が必要です。
例えば、むちうちは第14級9号「局部に神経症状を残すもの」、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の認定が検討されますが、第12級を勝ち取るには、事故当初から一貫した症状を訴え、適切な頻度で治療を継続した事実が重要です。
「後遺障害慰謝料の請求方法」の解説

治療費の打ち切り後も通院を継続する方法

交通事故の治療費について、加害者側の保険会社に打ち切りを通告されても、適切な対応を取ることで通院を継続できる可能性があります。立替払いがないと自費の治療となり、後から回収できるにしても直近の負担が大きく、治療をあきらめてしまう方もいます。
以下の方法を参考に、通院を継続する努力をしてください。
医師に意見書を書いてもらう
保険会社は、事故の状況や症状などから想定される治療期間をもとに判断するに過ぎません。そのため、治療費の打ち切りは、あなたの具体的な症状や回復状況を加味していません。
今後も治療を継続する必要がある場合、まずは主治医に相談し、医学的な見地から「治療の必要性」を確認しましょう。医師が「引き続き治療が必要」と判断するなら、診断書や意見書を作成してもらい、保険会社に提出して交渉を行います。
主治医が治療の必要性を認めない場合や、交通事故の後遺症に詳しくない場合には、セカンドオピニオンを求めることも検討してください(ただし、事故直後からの一貫した治療経過も重要なので、主治医を変更することは慎重に判断すべきです)。
弁護士に交渉を依頼する
治療の必要性があるのに保険会社が治療費の立替払いを打ち切る場合、弁護士に交渉を依頼する方法も有効です。特に、むちうちのように画像診断で異常が確認されづらいケースでは、通院を継続していた事実が重要な証拠となります。
弁護士が介入することで、保険会社の圧力に負けずに自身の主張を伝えられます。その結果、治療費の支払い延長が認められるケースも少なくありません。示談交渉をしたり裁判に発展したりする場合、医学的知識に加えて法的な観点の主張も必要であり、弁護士のサポートが欠かせません。
整骨院ではなく病院に通う
保険会社は、過去の交通事故対応の経験をもとに治療費の支払いを判断し、「不適切である」と考える通院方法があると治療費の打ち切りを通告します。
次のような通院方法は、打ち切りの判断をされやすいので注意してください。
- 事故態様に対して、被害者が訴える症状が重すぎる。
- 通院頻度や回数が少なすぎる。
- 事故から期間が経過してから通院を開始した。
- 医師の診断と被害者の訴える症状が食い違う。
治療費の打ち切りを避けるには、医師の指示に従い、適切な頻度で通院することが重要です。湿布や塗り薬など簡易な治療ではなく、電気治療などを受けるのも有効です。整骨院を利用する場合も、必ず病院(整形外科など)の治療を並行して受けてください。
更に、医師が正しい判断をするためにも、自覚症状を明確に伝えることが大切です。診療時に具体的な症状や痛みの変化をしっかり説明することで、治療の必要性が適切に評価され、治療費の支払い継続につながる可能性が高まります。
治療費打ち切り後の適切な被害回復

最後に、治療費打ち切り後の適切な被害回復の方法について解説します。
保険会社から治療費の打ち切りを通告された場合でも、適切な対応を取ることで、必要な治療を継続し、適正な損害賠償を受け取ることが重要です。
医師の指示に従って治療を続ける
保険会社が治療費の支払いを打ち切ったとしても、症状が残存し、固定に至っていなければ治療を継続すべきです。症状固定したかどうかは医学的な判断によるもので、保険会社の決めることではありません。医師が「引き続き治療が必要」と判断するなら、保険会社の打ち切り通告にかかわらず、治療を継続すべきです。症状が改善する可能性がある以上「症状固定」ではありません。
症状固定後に後遺症が残るときは、後遺障害等級認定の申請を行います。実際に、治療費の打ち切り通告後も通院を継続したことで、高い等級認定を受けられたケースも多くあります。自身のからだのためにも、治療の必要性がある限り、適切な医療を受けることが大切です。
健康保険に切り替えて自己負担を軽減する
治療費打ち切り後も通院を続ける場合、一旦は自己負担で払うしかありません(事後に加害者に請求することが可能です)。この際、健康保険を利用することで医療費の負担を軽減できます。
健康保険を利用するには、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合または協会けんぽに提出する必要があります。これにより、交通事故による治療費でも健康保険への切り替えが可能となり、窓口負担を3割(自己負担割合による)に抑えることができます。
健康保険を使用することで、一時的な経済的負担を減らしながら治療を継続できるため、治療費の打ち切り後の対応として有効な手段です。
打切り後の治療費も加害者に請求できる
加害者側の保険会社が立て替えて払ってくれないとしても、治療の必要性が認められる場合、打ち切り後の治療費も「交通事故による損害」として加害者に請求できます。
治療費の打ち切りは、あくまでも保険会社の判断であり、法的な拘束力はありません。最終的に「かかった治療費が交通事故による損害として認められるか」は裁判所が判断します。治療費の打ち切りを言われるようなケースでは、その後にかかった治療費の必要性について争いとなる可能性があるので、裁判になる場合に備えて医療記録をしっかり証拠として保存しておくことが重要です。
診断書やカルテなど、治療経過を証明する資料があれば、治療の必要性について客観的に証明することができ、裁判において正当な請求をすることが可能です。
「交通事故で医療記録を入手する方法」の解説

まとめ

今回は、治療費の打ち切りを通告されたときの適切な対応を解説しました。
加害者側の保険会社は、自社の利益を優先して、治療費をできるだけ早く打ち切ろうと働きかけをしてきます。しかし、交通事故の治療費の打ち切りの問題は、あくまで保険会社の立替払いの終了であって、言うなりになって治療を止めてはいけません。
治療の必要性があるなら、医師の指示に従って治療を続け、事後にまとめて治療費を請求できます。この際は、治療を継続したことで、入通院慰謝料や休業損害、ケースによっては後遺障害慰謝料や逸失利益などもまとめて賠償請求できます。
加害者側の保険会社に治療費を打ち切られたら、裁判も見据えた対策を講じる必要があります。お悩みの方は、ぜひ一度弁護士に相談してください。
- 加害者側の保険会社から治療費打ち切りを言われても、通院を継続する
- 治療費を打ち切りにされないためには、診断書と弁護士の交渉がポイント
- 治療費の打ち切り後も通院し、後から適正な損害賠償を請求する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
後遺障害に関する問題は、事故後の生活や働く能力に深刻な影響を及ぼします。そのため、交通事故の被害に遭ったときは、法的な手続きや慰謝料請求の方法を知り、適切な被害回復を図らなければなりません。
後遺障害に関する解説記事を通じて、正しい対処法を理解してください。


