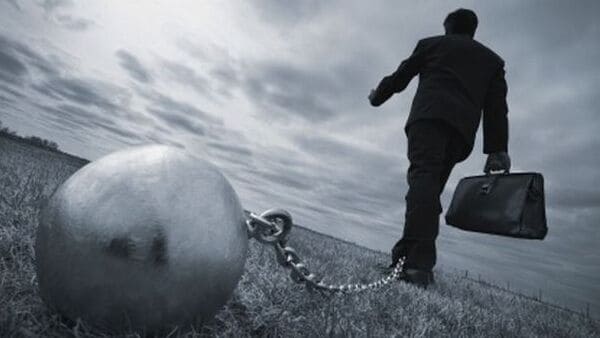「退職してください」と会社からの働きかけを受けたとき、それが「退職勧奨」なのか、それとも違法な「退職強要」なのかの見極めが必要です。
退職勧奨は、自主退職を勧めることですが、退職強要は、労働者の自由な意思を抑圧する違法行為です。近年は、人員整理やパフォーマンスの問題を理由に、解雇を避けるための「自主退職を促す行為」が増えていますが、その中には、実質的には退職を強制する違法なケースも少なくありません。企業側はトラブル回避のつもりが、損害賠償の請求などの争いに発展します。
退職強要は違法ですが、退職勧奨は適法です。したがって、退職を勧められた労働者は、適法な退職勧奨の範囲に留まるか、それとも違法な退職強要なのか、区別して対処しなければなりません。
今回は、退職強要と退職勧奨の違いと、どのような場合に違法となるのか、そして、労働者側の対処法について、弁護士が解説します。
- 退職強要と退職勧奨の違いは、労働者が自由な意思で判断できるかどうか
- 形式的には「退職勧奨」でも、退職を強制されたら違法となる
- 労働者側が、退職強要と退職勧奨のどちらに該当するかを見極めて対処すべき
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
退職強要と退職勧奨の違い

はじめに、退職強要と退職勧奨の違いについて解説します。
企業が、社員の退職について働きかけを行う場面は少なくありません。その中でも、退職強要と退職勧奨は、形式は似ていますが、違法性の評価が異なるので、区別の基準を知るべきです。
退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社が労働者に対し、「退職を検討してほしい」と提案する行為です。
退職勧奨はあくまで、労働者の自由な意思に基づく選択を前提としており、退職するかどうかは本人の判断に委ねられます。
会社が、退職勧奨を行う理由には、業績悪化による人員整理、問題社員対応、企業秩序の維持など、様々なケースがあります。本来は、一方的に解雇したいと希望する場面でも、解雇権濫用法理による厳しいルールの制限を受けるため、簡単には辞めさせられません。不当解雇は無効であり、労働者側に争われれば、会社が負けてしまいます。
そこで「解雇はできないけれど、社員には辞めてほしい」という場面で、その目的達成のために行われるのが、退職勧奨です。退職勧奨があくまで自由な意思を尊重して行われる限り、解雇の制限が適用されません。したがって、退職勧奨が適法とされる条件は、次の通りです。
- 本人に選択の自由があること(強制ではないこと)
- 働きかけが威圧的な言動によらないこと
- 退職を拒否する場合に不利益な扱いがないこと
退職勧奨は、企業の合理的な経営判断として一定程度認められますが、その手法を誤ると違法な「強要」と判断されるリスクがあります。
「退職勧奨を弁護士に相談すべき理由」の解説

退職強要とは
一方、退職強要は、「労働者を退職させる」という目的の達成のために、心理的な圧力や物理的な手段を用い、事実上強制する行為を指します。この場合、形式的には「退職届を出す」というように労働者の自発的な退職に見えても、会社の不当な圧力によるなら無効となる可能性があります。
よくある退職強要の手口には、次の例があります。
- 何度も面談を繰り返して退職を迫る(執拗な呼び出し)。
- 「辞めなければ降格になる」「周囲に迷惑がかかる」などと脅す。
- 職場で孤立させたり、仕事を与えないなどの嫌がらせをする。
- 退職届への署名を強要する、書くまで帰さない。
これらの行為があり、労働者の自由な意思を制圧している場合は、違法な退職強要と認定することができ、不法行為に基づく損害賠償請求の対象となります。直接的な言動によらなくても、違法なノルマを与えたり、いわゆる「追い出し部屋」に部署異動させたり、PIPや外部研修と称して能力の低い社員として扱ったりといった方法も、違法な退職強要の手段となることがあります。
退職強要と退職勧奨の見分け方と判断基準
退職強要と退職勧奨の違いは、紙一重ともいえる場面が多くあります。重要なポイントは、「労働者が退職を拒否する余地が残されているかどうか」という点です。
退職強要と退職勧奨の見分け方は、次の基準で検討してください。
意思表示の自由度
退職勧奨なら、辞める気持ちがないのであれば、退職を拒否することができます。労働者が自由に「辞めない」という選択をできる状態なら、退職勧奨だといえます。これに対し、拒否する余地がなく、事実上「辞めるしか選択肢がない」という状態は、退職強要と判断されます。
退職しないなら「居場所はない」などのプレッシャーも、自由な意思を妨げます。
働きかけの態様
会社による働きかけが、穏やかな説明や提案に留まるなら、退職勧奨といえます。
これに対し、威圧的な態度や脅迫的な発言、人格否定や侮辱、高圧的な言動が見られる場合、そのプレッシャーの強さによって労働者の自由な意思が制圧されれば、違法な退職強要です。この場合、不法行為として慰謝料その他の損害賠償を請求できるほか、強要がひどいケースは、暴行罪・脅迫罪・監禁罪などの犯罪に該当するおそれもあります。
退職を拒否したら評価や待遇が下がったとか、退職届の記入をその場で求められたといった事情も、退職強要であることを基礎づけます。
働きかけの回数・期間
退職に関する働きかけの回数や期間も、その違法性の判断基準となります。
退職勧奨なら、必要最小限の回数ないし期間で、本人に判断の時間を与えるのが通常です。これに対し、執拗に面談を繰り返したり、一日に何度も呼び出したり、短期間に何度も退職を迫ったりすると、そのプレッシャーから違法な退職強要と判断することができます。
何度も面談が繰り返され、断っても止まらないなら、それは違法な退職強要です。
「退職強要が違法となるケース」の解説

退職勧奨が違法となる基準
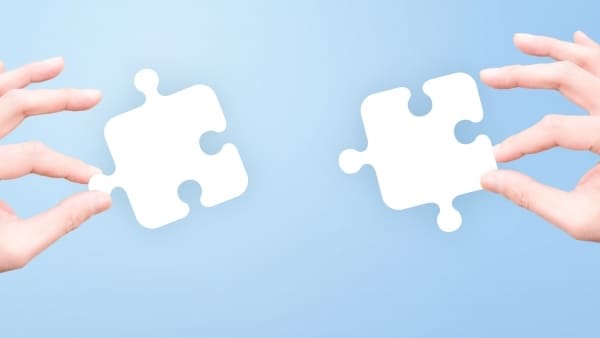
次に、退職勧奨が、どのような場合に「違法な退職強要」と判断されるかを解説します。
会社としては「辞めさせたい」という気持ちが先立ち、つい違法な行為をしてしまう危険があります。労働者側が、しっかりと退職強要と退職勧奨の違いを見極め、対処すべきです。
退職勧奨について判断した裁判例の基準
退職強要の違法性が争点となった裁判例の基準について解説します。退職勧奨について判断した下関商業高校事件(最高裁昭和55年7月10日判決)の原審が参考になります。
退職勧奨は、任命権者がその人事権に基づき、雇用関係ある者に対し、自発的な退職意思の形成を慫慂するためになす説得等の行為であって、法律に根拠を持つ行政行為ではなく、単なる事実行為である。従って被勧奨者は何らの拘束なしに自由にその意思を決定しうるこというまでもない
下関商業高校事件(最高裁昭和55年7月10日判決)
本裁判例も、退職勧奨は、自発的に退職してもらえるよう説得する行為であり、自由な意思決定を阻害してはならないと判断しています。つまり、説得の程度を超えれば、違法な退職強要となることが、裁判例でも示されているわけです。
本裁判例は結論として、違法な退職強要であるとして慰謝料請求を認めましたが、その判断では「退職勧奨によりその精神的自由を侵害され、また、受忍の程度を超えて名誉感情を傷つけられ、さらには家庭生活を乱されるなど相当の精神的苦痛を受けた」と判示しました。つまり、退職勧奨が、説得の程度に留まるなら、ある程度は労働者も受忍すべきケースもあるということです。退職勧奨には許される限界があり、これを超えるまでは、労働者としても会社の説得を聞かなければなりません(もちろん、退職に応じなければならないわけではありません)。
以上の裁判例から分かる通り、単なる「提案」を超えて、継続的に強い圧力をかける行為は違法と認定されるリスクが高いといえます。
違法にならない退職勧奨の条件
退職を提案すること自体が直ちに違法となるわけではありません。以下のような条件を満たしている場合には、適法な退職勧奨となります。
適切な説明義務を果たされている
「なぜ退職の働きかけをされているのか」、会社側の理由や背景が説明されており、労働者が納得できる機会を提供されていることが重要です。
拒否したら終了する
退職勧奨なら、あくまで説得であり、労働者は拒否できるのが基本です。
そのため、拒否したら、その後は続かず、ストップするのが適法な退職勧奨であり、逆に、拒否した後も繰り返し行われるのが違法な退職強要です。繰り返されると、強いプレッシャーやストレスを感じ、応じざるを得ない心境になってしまうことでしょう。
代替案や妥協案が提案されている
いきなり退職を迫るのではなく、異動や再配置などの選択肢が示されることも、適法な退職勧奨の特徴だといえるでしょう。
また、労働者が退職勧奨を断った後、新たな条件を示すことができるならば、すぐに働きかけを止めなくても、違法な退職強要とはならない場合もあります。つまり、会社側に、解決金の増額をはじめとした代替案・妥協案があるならば、ある程度の期間や回数、働きかけを続けても、適法な退職勧奨である可能性があります。
面談回数や時間が合理的である
面談が過剰に繰り返されると圧力とみなされるおそれがあるため、回数や時間は常識的な範囲にとどまっていなければ、適法な退職勧奨とは言えません。
拒否したことによる不利益がない
会社が退職勧奨のつもりでも、拒否したことによって労働者側に不利益があるのであれば、それは違法な退職強要です。退職勧奨はあくまで労働者の自由な意思を阻害してはならず、拒否して不利益があるのでは、自由な判断は難しいからです。
違法となるような不利益には、次の例があります。
- 退職勧奨を拒否したら懲戒解雇とする。
- 嫌がらせを行う。
- 無視する、仕事を与えない。
- パワハラ、職場いじめの対象として会社に居づらくする。
- 大幅に減給する。
労働者にメリットが提案されている
退職勧奨を行う際、応じてもらいやすくするために労働者にメリットを提示することがあります。退職に応じることが、労働者にとっても利益があるなら、適法な退職勧奨です。例えば、退職金の交渉、再就職先の斡旋、未消化の有給休暇の買取といった提案です。
労働者側でも、会社から提案されたメリットをじっくり検討し、退職するかどうかを判断できるなら、自由な意思は制圧されておらず強要ではありません。
労働者に検討の時間が与えられている
適法な退職勧奨によって会社を辞めるとき、労使間の合意を書面(退職合意書など)に残して証拠化するのが一般的です。
このとき、一度持ち帰って家族と相談するなど、労働者側に考える時間が設けられていることは、適法な退職勧奨とするために非常に重要なことです。
退職勧奨と失業保険
失業保険における退職の理由には、次の2つ種類があります。
- 自己都合退職
労働者の都合による退職(例:自主退職、辞職など)。 - 会社都合退職
会社側の都合による退職(例:解雇など)。労働者保護の必要があるために、失業保険の受給において労働者に有利な扱いとなります。
失業保険を受け取るとき、会社都合退職の方が労働者にとって有利です。具体的には、自己都合退職では退職してから7日間の待機期間と、1ヶ月の給付制限期間の後にはじめて支給開始となるところ、会社都合退職なら、7日間を経過したらすぐに支給されます。また、給付期間も、会社都合(90日〜330日の支給期間)の方が、自己都合(90日〜150日の支給期間)より長く設定されています。
退職勧奨は、違法な強要に至った場合はもちろん、そうでなくても「会社都合退職」として扱われます。会社からの説得や働きかけによって退職する点で、労働者の保護を要するからです。
まとめ

今回は、退職強要と退職勧奨の違いについて解説しました。
退職強要と退職勧奨は、一見似たような形式を取りますが、法律上は全く違った意味を持ちます。退職勧奨は、あくまで労働者の自由な意思を尊重して「退職するかどうか」を判断させるものですが、強制や威圧、ハラスメントなどがあれば違法な退職強要と評価されます。
労働者としては、退職勧奨なら自由に拒否できるのが基本です。会社からの「辞めさせたい」という強い圧力を感じたら、その証拠を残し、毅然とした態度で拒否することが大切です。企業側でも、トラブルを避けるには適正な手続きを踏み、労働者の意思を尊重すべきです。
退職強要と退職勧奨の違いを理解しておけば、退職する気がないなら違法な強要には屈する必要はないことが分かるでしょう。後悔のない判断を下すために、会社からの退職の働きかけに不安を感じたら、ぜひ弁護士に相談してください。
- 退職強要と退職勧奨の違いは、労働者が自由な意思で判断できるかどうか
- 形式的には「退職勧奨」でも、退職を強制されたら違法となる
- 労働者側が、退職強要と退職勧奨のどちらに該当するかを見極めて対処すべき
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
退職強要は、自主的な退職の形をとりながらも、実質的には不当な圧力によって辞めさせられます。違法な扱いには、冷静に法的対処をすることが不可欠です。
退職強要についての解説によって、自身の権利を守るための正しい知識を身に着けてください。