将来介護費とは、将来的に必要となる可能性のある介護費用のことです。
交通事故によって重い後遺症が残った場合、今後も継続的な介護費用の支出を余儀なくされるケースがあります。この場合、「実際に介護費用が発生した時点で請求するのではなく、現時点でまとめて損害賠償請求できるのか」という点が、将来介護費をめぐる重要な法律上の争点となります。
そして、将来介護費の請求を裁判で認めてもらうには、①将来の介護に必要性と、②将来介護費を支出する相当程度の可能性の2点が求められます。
今回は、将来介護費の問題について、具体的な目安や計算方法、裁判で認められるための要件などを弁護士が解説します。
- 将来の介護の必要性が認められるなら、将来介護費を請求できる
- 請求可能な将来介護費は、介護を要すると考えられる年数に応じて算出する
- 将来介護費には、一括払い・定期金賠償の2つの支払い方法がある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
将来介護費を請求できるケースとは

はじめに、将来介護費の請求が認められるケースについて解説します。
将来介護費とは
将来介護費とは、交通事故の被害者が、将来的に介護を要するときにかかる費用です。
特に、重度の後遺症が残ってしまったケースでは、今後も継続的に介護が必要になる可能性が高く、その費用を加害者に対して損害として請求できます。将来介護費を請求できる典型的な例として、以下のような重度の後遺障害を負ったケースが挙げられます。
- 遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)
- 失調麻痺
- 高次脳機能障害
- 脊髄損傷
将来介護費の問題は、「将来的に介護が必要となる可能性がどの程度あるか」が重要な判断基準となります。この点は裁判例でも判断が分かれており、認められる場合と認められない場合があります。
「後遺障害慰謝料の請求方法」の解説

将来介護を請求できる要件
将来介護費を「損害」として裁判所で認めてもらうには、「将来の介護の必要性が高い」と判断されることが必要です。既に支払った介護費用なら、問題なく加害者に請求できますが、将来介護費は実際にはまだ発生していない将来の費用の請求なので、「必要性」の立証が求められます。
自賠責保険の後遺障害等級において第1級、第2級に該当する場合、明文で「介護を要する」と規定されているので、これらの等級に認定されれば、将来介護費の請求は認められやすい傾向にあります。(なお、「介護」には日常生活動作における身体介護だけでなく、患者の動静の見守りや声掛けなども含まれます)。
自賠法施行令 別表第一
第1級
1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
実務上は、第1級・第2級以外の後遺障害等級であっても、具体的な状況に応じて介護の必要性が認められれば、将来介護費の請求が可能です。この判断にあたっては、以下の点が考慮されます。
- 被害者の身体の状況
- 残存する後遺症の内容や程度
- 日常生活動作(ADL)の制限の程度
例えば、後遺障害等級が第3級以下でも、高次脳機能障害など介護の必要性が高い症状がある場合は、生活への支障の大きさや、介護者の負担の大きさを主張することで、将来介護費の請求が認められる可能性があります。
将来介護費の金額の計算方法
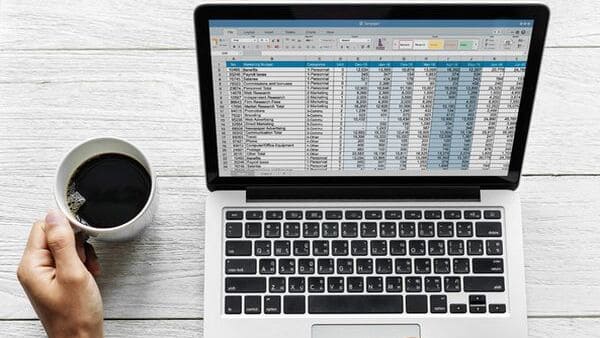
将来介護費を請求する際には、その金額をどのように算出するかが重要なポイントとなります。次に、裁判例を踏まえた将来介護費の計算方法について解説します。
将来介護費の基本的な計算式
将来介護費は、以下の計算式で求められます。
- 将来介護費 = 年間の介護費用 × 介護を要する年数(平均余命に対応したライプニッツ係数)
この計算では、まず年間の介護費用を算出し、それに平均余命に基づくライプニッツ係数をかけることで、将来の介護費の現在価値を求めます。以下、各項目について詳しく解説します。
年間の介護費用の算出方法
将来介護費の計算において、年間の介護費用は、1日あたりの介護費用(日額)を求め、これに365日をかけて算出します。日額は、介護の主体が家族・親族などが行う「近親者介護」なのか、介護職などの職業付添人が行う「職業介護」なのかで区別されています。
近親者介護の場合
1日8,000円程度を目安とします。ただし、後遺症の重度、介護の必要性のほか、1日のうち介護に要する時間の割合なども考慮して、具体的な看護状況によって増額・減額します。
家族の介護には「無償性」があるので、裁判で過小評価されるおそれがあります。また、家事労働と介護が混在する場合、介護費として認められる金額は低くなる傾向にあります。
職業介護の場合
原則として、実費全額を請求することが可能です。
ただし、将来的に介護費用は変動する可能性があるので、裁判所では実際の支払い額よりも少なく認定されることがあります。なお、裁判所の認定においては、現在払っている介護費、後遺症の程度、回復の可能性などが考慮されます。
近親者介護と職業介護の切り替え
長期間にわたる介護は家族に大きな負担をかけます。そのため、実務では、当初は近親者介護でも、一定の年齢(例:近親者が67歳に達した時点など)以降は施設介護へ移行するという前提で将来介護費を計算するケースが多いです。
介護形態(在宅介護・施設介護)の違い
将来介護費の算出にあたっては、在宅介護か施設介護かによっても費用が変わります。
在宅介護の場合には、近親者介護のみ、もしくは職業介護との組み合わせで算出します。これに対して施設介護の場合には、入所費用や医療費なども考慮されます。費用面だけでなく、被害実態に即した介護プランを策定するのも大切なポイントです。
将来介護費の決定にあたり裁判で考慮される事情
近親者の介護では、1日8,000円程度を目安としながら、介護の具体的状況を踏まえて金額が変動するため、しばしば裁判でその金額が争いになります。将来介護費は、あくまで予測にすぎないので、金額の決定においては様々な事情を総合的に考慮して決めるしかありません。
【被害者の状況】
- 後遺症の内容・程度(例:完全介助が必要か、見守り程度か)
- 日常生活の自立度(ADL:日常生活動作の制限の程度)
- 必要な介護の内容・頻度(例:常時介護か、随時介護か)
- 介護に要する時間
【介護環境】
- 介護者の属性(年齢、性別、健康状態など)
- 家屋が介護仕様かどうか(バリアフリー改修の必要性)
- 介護用具の使用状況(例:介護ベッド・車椅子の有無)
【常時介護と随時介護の違い】
- 常時介護が必要な場合、全額認められるケースが多い
- 随時介護の場合、介護の頻度・時間に応じて将来介護費が2分の1程度に減額されることが多い
将来介護費が問題となるケースの裁判は、重度の後遺症が残っていることから請求額は相当高額となり、争いは長期化します。できるだけ多くの将来介護費を認めてもらうためにも、後遺症がどれほど重度で、介護の必要性が高いかを立証するため、証拠の準備が欠かせません。
介護用品代・自宅改装費も請求できる
在宅介護では、介護用品代や自宅改装費など、介護に伴う諸費用についても損害賠償の対象となります。例えば、次のような費用が含まれます。
- 介護用品代
例:介護ベッド、車椅子、おむつ代 - 自宅改装費
例:自宅のバリアフリー化、スロープ設置
裁判所でこれらの費用を認めてもらうには、介護の必要性と、請求額の妥当性を証明する必要があります。既に介護を開始しているときは、介護実績を証明するための介護日誌や日記、介護用品や自宅改装に関する業者の見積書や領収書などが証拠となります。
公的扶助は控除されない
将来介護費の請求では、介護保険などの公的扶助は考慮されません。
介護保険などの公的扶助を実際に受けている場合には、その分は介護費から控除されます。利益のあった分を損失から控除する「損益相殺」の考え方があるからです。これに対し、将来介護費については損益相殺の対象とならず、公的扶助は考慮されないこととなっています。
裁判例でも、「公的扶助の制度が設けられているとしても、公的扶助を受ける義務を負うものではないし、同制度が将来にわたって存続する保障もない」(仙台地裁平成9年10月7日判決)と判断されています。つまり、将来、公的扶助を受けられない可能性がある以上、それを前提に損害額を減額する必要はないという考え方です。
介護を要する年数の算出(ライプニッツ係数の適用)
将来介護費の計算では、被害者の平均余命を基準として介護を要する年数を決定します。
ただし、健康状態によっては、平均余命まで生きる可能性が低いなどの特別な事情があるときは、より短い期間しか認められないこともあります。そして、将来分を現在に一括して受け取ることから、中間利息を控除し、現在価値に換算するために、ライプニッツ係数が適用されます。

平均余命より長生きしても将来介護費が増額されることはなく、早く亡くなっても将来介護費の返還は不要です(長生きするほど介護費がかかる「延命リスク」がある点で、次章「将来介護費の支払方法は、一括払いか、定期金賠償か」のように定期金賠償が議論されています)。
なお、2020年4月1日に施行された改正民法で法定利息の利率(法定利率)が年5%から年3%に変更されたのを受け、ライプニッツ係数も変更されています。
将来介護費の支払方法は、一括払いか、定期金賠償か

定期金賠償は、将来介護費をはじめとした将来発生する損害賠償額を、現在に一括で払うのではなく、毎月など定期的に分割して受け取る方法です。
交通事故の損害賠償では、時間の経過と共に随時発生する損害について、より実態に即した補償を行うために定期金賠償の方法が選択されることがあります。将来介護費は、長期にわたって継続的に支出される点で定期金賠償に適しており、実際に認めた裁判例も多くあります。
ただし、一時金賠償(一括払い)と定期金賠償のどちらを選ぶかによって、被害者にとってメリットとデメリットが異なるので、慎重に選択することが重要です
一時金賠償には、全ての賠償額を一括で受け取るため、将来未払いとなるリスクがないメリットがあります。加害者の無資力や保険会社の破綻リスクも回避できます。
これに対し、一括払いの場合には平均余命を基準に損害額を算出するので、これ以上に長生きすると、受け取れる金額が少なくなるデメリットがあります。
定期金賠償には、中間利息が控除されないために受取総額が多くなること、長生きした場合のリスクを回避できるメリットがあります。一方で、保険会社の倒産や加害者の無資力により、途中で支払いが途絶えるおそれがあります。また、被害者が平均余命より早く死亡した場合、実際に受け取れる金額が一括払いより少なくなるデメリットがあります。
「交通事故の定期金賠償」の解説

まとめ

今回は、交通事故被害のうち、将来介護費の問題について解説しました。
将来介護費は、交通事故で重度の後遺障害が残存するケースで重要な争点となります。余命が長いほど請求額が高額となるので、加害者やその保険会社との間で激しく争われる傾向があります。特に、高額な請求だと示談が成立しづらく、裁判での解決を余儀なくされます。
裁判では、介護の必要性や後遺障害の症状、介護の実態など、様々な要素が総合的に考慮されます。そのため、過去の裁判例を参考に、どのようなケースで将来介護費の請求が認められやすいのかを把握しておくことが必要です。
適正な賠償を受けるには、将来の介護に関する具体的な証拠や資料の準備が欠かせません。交通事故による介護費用の請求を検討している方は、早めに弁護士に相談してください。
- 将来の介護の必要性が認められるなら、将来介護費を請求できる
- 請求可能な将来介護費は、介護を要すると考えられる年数に応じて算出する
- 将来介護費には、一括払い・定期金賠償の2つの支払い方法がある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
後遺障害に関する問題は、事故後の生活や働く能力に深刻な影響を及ぼします。そのため、交通事故の被害に遭ったときは、法的な手続きや慰謝料請求の方法を知り、適切な被害回復を図らなければなりません。
後遺障害に関する解説記事を通じて、正しい対処法を理解してください。


