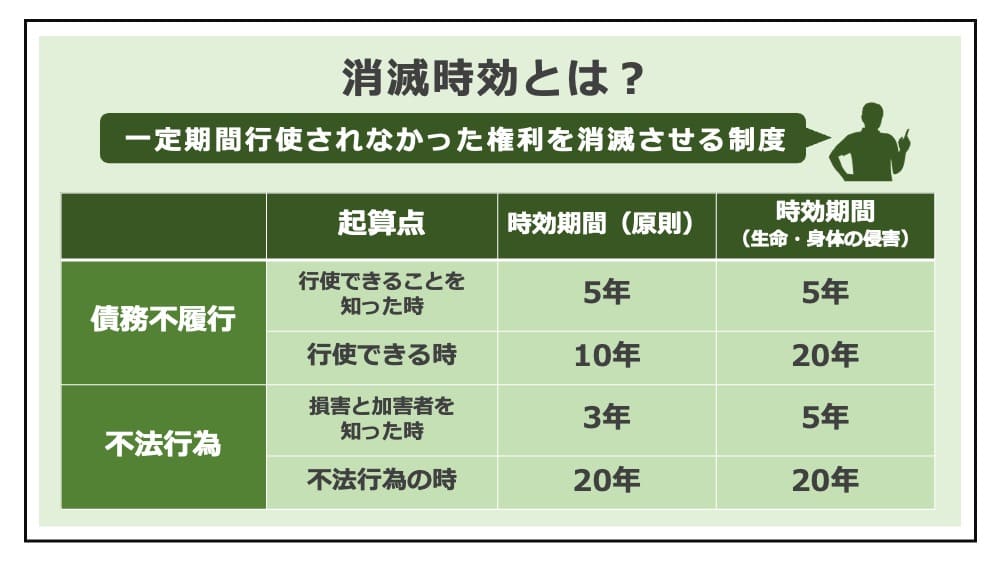交通事故でケガをすると、治療の終了後に症状が残ってしまうことがあります。
このように固定後も残存する症状のことを「後遺症」といいます。交通事故に遭った後、後遺症がもたらす身体的・精神的な影響は大きく、後遺障害等級の認定を受けることで「後遺障害慰謝料」を加害者に請求することができます。後遺障害には、第1級から第14級の等級があり、高い等級ほど重度の後遺症と評価され、後遺障害慰謝料が高額となります。
今回は、交通事故で後遺症が残ったときに、より高額の後遺障害慰謝料を請求するために知っておくべき法律知識について、弁護士が解説します。
- 交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を申請する
- 等級認定が得られれば、後遺障害慰謝料を請求することができる
- 後遺障害慰謝料の相場よりも低い保険会社の提案には、応じるべきでない
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
\ 動画解説(約4分) /
交通事故の後遺症と後遺障害慰謝料

はじめに、交通事故の後遺症と、後遺障害慰謝料について解説します。
交通事故の怪我は、骨折や捻挫、打撲などの外傷が多いですが、事故直後に現れなかった症状が、期間が経過してから生じることがあります。治療をしてもなお残る症状を「後遺症」と呼び、慢性的な痛みや運動障害、神経障害、精神的なトラウマなど、多岐にわたる影響を及ぼします。
交通事故で後遺症が残ってしまったときは、後遺障害慰謝料の請求を検討してください。
後遺障害等級の考え方
後遺障害等級とは、事故後に残る後遺症の重度に応じて、客観的に評価する指標です。
医師の診断や検査結果に基づいて、障害の程度を第1級(最も重度)から14級(軽度)までに分類します。等級ごとに慰謝料額の相場が決められているので、この認定によって後遺症の程度を明らかにし、適正な賠償額の基準を決める役割を果たします。後遺障害等級の分類は、障害の重さや日常生活への影響の大きさに応じて行われており、労災保険の基準と同じものです。
この等級を前提に交渉や裁判をすることで、公正な被害回復を実現することができます。
後遺症が残ったら慰謝料を請求できる
交通事故による後遺症が残った場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。
慰謝料は、交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対する賠償金ですが、「心身に及ぼす影響」を金銭に換算するために、後遺障害等級ごとに慰謝料の相場が定められています。後遺障害慰謝料は、被害者の苦痛や生活の質の低下に対する補填という意味合いがあります。
残った後遺症が重度だと、慰謝料も相当高額になる可能性があるので、適正な被害回復を図るためにも、慰謝料に関する正しい法律知識を理解しておかなければなりません。
後遺障害等級認定の仕組み

次に、後遺障害等級認定の仕組みについて解説します。
交通事故の被害者が、より高額の後遺障害慰謝料を得るには、後遺症の程度に合った適切な等級認定を受けることが重要です。その具体的な方法やプロセス、基準を理解してください。
後遺障害等級認定の申請をする条件
後遺障害等級認定の申請をするには、次の5つの条件を満たす必要があります。
- 交通事故によるケガであること
大前提として、交通事故とケガの間に因果関係が必要となります。 - 症状固定していること
症状固定とは、これ以上治療しても症状の改善が見込めない状態です。症状固定後に残存した後遺症があるとき、後遺障害等級認定の申請が可能です。 - 後遺障害等級認定表に記載された症状があること
等級認定を受けるには、各等級ごとに定められた具体的な症状に該当していることが必要です。 - 労働能力が低下していること
後遺症によって労働能力が低下している場合に、等級認定の申請をすることができます。 - 医師による医学的な証明があること
後遺症の症状について、病院や医師の診断を受ける必要があります。この際に重要な証拠となるのが「後遺障害診断書」です。
「交通事故で医療記録を入手する方法」の解説

後遺遺障害等級認定までの流れ
次に、後遺障害等級認定までの流れを理解しておいてください。
後遺障害等級認定の申請手順は、次の流れで進めます。有利な認定を得るのに重要なのは、主治医の指示に従い、「症状固定」と言われるまで適切な回数・頻度で治療を継続することです。
- 主治医に症状固定であると言われる。
- 後遺障害診断書を作成してもらう。
- 必要書類を自賠責保険会社に提出する。
- 損害保険料率算定機構が審査・認定を行う。
- 保険会社から認定結果が通知される。
後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
- 事前認定
加害者側の任意保険会社を経由して、自賠責保険会社に対して後遺障害認定の申請を行う方法。保険会社が協力してくれ分、手間が少なく済みますが、相手の保険会社が被害者にとって有利な主張を十分尽くすとは限りません。 - 被害者請求
被害者自身が、加害者の自賠責保険に対して直接保険金を請求し、その仮定で後遺障害等級認定の申請を行う方法。十分な証拠を添付して有利な主張をすることで、等級認定を受けやすくなり、慰謝料の増額が見込めます。
手間を惜しまないなら、慰謝料増額のためには、被害者請求をする方がお勧めです。弁護士に依頼して代わりに進めてもらうことで、スムーズに行うことができます。
等級認定に不服があるときの争い方
後遺障害等級認定の申請をし、その結果に不服がある場合、異議申立てが可能です。等級認定(もしくは不認定)に不服があるとき、異議申立ての方法は次の3つです。
- 自賠責保険へ異議申立する方法
費用がかからず、回数制限もないため、まずはこの方法を試しましょう。ただし、等級認定の結果が変更されない可能性があります。 - 紛争処理申請をする方法
- 裁判を起こして争う方法
中立的な期間である裁判所の審理を受けることで、適切な証拠を提出すれば、等級認定の結果にかかわらず慰謝料などについての法的判断を下してもらえます。事故態様や過失割合にも争いがあるなら、裁判を起こす方法がお勧めです。
後遺障害慰謝料の請求方法と慰謝料額の相場

最後に、後遺障害慰謝料の請求方法と、金額の相場について解説します。
交通事故の損害賠償には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)という複数の支払基準がありますが、最も高い弁護士基準(裁判基準)で請求すべきです。損しないためにも、保険会社の提案に安易に応じるのは控えなければなりません。
請求の基本的な流れ
後遺障害慰謝料を請求する手順は、交通事故における損害賠償請求の流れに従います。次のステップで順に進めてください。
証拠の収集
請求手続きにおいて最も重要なのは、適切な証拠を揃えることです。
交通事故直後から記録に残しながら治療を進めるようにし、医師による診断書や意見書、各種の検査や画像診断の結果、入通院の記録や処方薬の詳細などの資料を収集してください。
請求書の作成と送付
保険会社との示談交渉
請求書を送付したら、保険会社との示談交渉が始まります。
示談交渉では、証拠に基づいた具体的な後遺障害等級と、それに対応する慰謝料額を提示し、納得のいくまで話し合いましょう。「後遺障害慰謝料の額の相場」の通り、保険会社が提示する示談金額は相場より低いことが多いので、安易に応じてはいけません。
後遺症の慰謝料請求は、交通事故の専門的な法律知識を要するため、弁護士のアドバイスを受けるのが有用です。特に、後遺障害等級の認定結果に疑問があるときや、保険会社の提示額が低く交渉が難航する場合は、必ず弁護士に相談してください。
裁判で請求する
保険会社との示談交渉が難航する場合は、裁判に移行するケースもあります。裁判では、証拠に基づいて妥当な後遺障害慰謝料の金額を決定してもらうことができます。
裁判で請求する際は、後遺障害慰謝料以外にも、治療費や休業損害、逸失利益といった損害賠償について漏れなく請求しましょう。
後遺障害慰謝料の額の相場
慰謝料の相場は、後遺障害等級ごとに決められた基準額が参考にされます。重度の後遺症ほど高い等級に認定され、高額の慰謝料が認められます。
交通事故の損害賠償には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つの目安がありますが、裁判になれば獲得できる弁護士基準(裁判基準)こそが最も妥当であり、被害者として勝ち取るべき解決となります。保険会社から、自賠責保険基準や任意保険基準の慰謝料額しか提案されないときは、弁護士に依頼したり、裁判を提起したりすべきです。
自賠責基準の慰謝料計算
自賠責保険は、全ての車両が加入する法的義務のある強制保険です。
被害者救済のための最低限の補償であるため、自賠責保険から得られる慰謝料額は低額に抑えられており、補償しきれない損害は任意保険でカバーされます。自賠責保険の支払基準は、自動車賠償保障法の表によって、賠償額の上限が定められています。この上限は後遺障害慰謝料と逸失利益の合計額です。
<別表Ⅰ>
| 等級 | 支払基準 | 限度額 |
|---|---|---|
| 第1級 | 1,650万円 (1,850万円) | 4,000万円 |
| 第2級 | 1,203万円 (1,373万円) | 3,000万円 |
<別表Ⅱ>
| 等級 | 支払基準 | 限度額 |
|---|---|---|
| 第1級 | 1,150万円 (1,350万円) | 3,000万円 |
| 第2級 | 998万円 (1,168万円) | 2,590万円 |
| 第3級 | 861万円 (1,105万円) | 2,219万円 |
| 第4級 | 737万円 | 1,889万円 |
| 第5級 | 618万円 | 1,574万円 |
| 第6級 | 512万円 | 1,296万円 |
| 第7級 | 419万円 | 1,051万円 |
| 第8級 | 331万円 | 819万円 |
| 第9級 | 249万円 | 616万円 |
| 第10級 | 190万円 | 461万円 |
| 第11級 | 136万円 | 331万円 |
| 第12級 | 94万円 | 224万円 |
| 第13級 | 57万円 | 139万円 |
| 第14級 | 32万円 | 75万円 |
- ()内は、被扶養者が存在する場合の金額です。
- 後遺障害等級表には、別表Ⅰと別表Ⅱがあります。別表Ⅰは後遺障害によって日常的な介護を要する場合、別表Ⅱは日常的な介護までは不要な場合に適用されます。
任意保険基準の慰謝料計算
任意保険基準は、加害者が加入する保険から支払われる慰謝料の基準です。
自賠責保険は強制加入ですが、任意保険への加入は「任意」です。自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)には大きな開きがあるので、これを補うために任意保険に加入するのが通常です。
ただ、交通事故のとき、任意保険基準でも、弁護士基準(裁判基準)より低額となるのが一般的です。そのため、後遺症を負った場合、任意保険会社の提案する示談金をそのまま受け入れるのではなく、以下の弁護士基準(裁判基準)によって算出した適正額を支払うよう強く請求すべきです。
弁護士基準(裁判基準)の慰謝料計算
弁護士基準(裁判基準)とは、弁護士に依頼して裁判で請求をする際に認容される金額です。交通事故の訴訟は過去に数多く起こっているので、その判決を参考にした一定の相場が形成されています。
弁護士基準(裁判基準)は、「赤い本」(正式名称:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」日弁連交通事故センター東京支部)に、次の通り定められています。
| 等級 | 支払基準 |
|---|---|
| 第1級 | 2,800万円 |
| 第2級 | 2,370万円 |
| 第3級 | 1,990万円 |
| 第4級 | 1,670万円 |
| 第5級 | 1,400万円 |
| 第6級 | 1,180万円 |
| 第7級 | 1,000万円 |
| 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 |
| 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 |
| 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 |
| 第14級 | 110万円 |
まとめ

今回は、交通事故の後遺症と、後遺障害慰謝料について解説しました。
適正な後遺障害慰謝料を獲得し、交通事故の被害を回復するには、保険会社の提案に安易に応じず、後遺障害等級認定の申請とその後の手続きを進めなければなりません。保険会社は、自社の負担を抑えるために低額な提案をしてくるケースが少なくありません。後遺症が残るような重大な交通事故では、被害者側としても慎重に交渉することが、自身の権利を守るのに欠かせません。
後遺障害慰謝料をより多く獲得するには、有利な等級認定を得ることが不可欠です。そのために、事故直後から弁護士のアドバイスに従い、証拠を残しながら治療を受けるべきです。交通事故の被害者となり、後遺障害が残ってしまった被害者の方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
- 交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を申請する
- 等級認定が得られれば、後遺障害慰謝料を請求することができる
- 後遺障害慰謝料の相場よりも低い保険会社の提案には、応じるべきでない
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
後遺障害に関する問題は、事故後の生活や働く能力に深刻な影響を及ぼします。そのため、交通事故の被害に遭ったときは、法的な手続きや慰謝料請求の方法を知り、適切な被害回復を図らなければなりません。
後遺障害に関する解説記事を通じて、正しい対処法を理解してください。