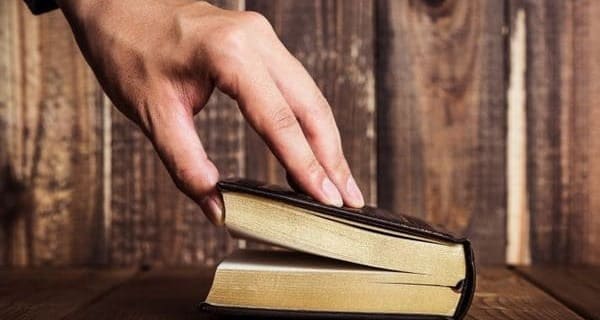利用規約は、ウェブサービスやアプリをローンチする際に必要不可欠な文書です。
規約には、ユーザーに向けたサービス利用のルールを示すと共に、事業者側の責任を定め、リスクを限定するなど重要な効果があります。スタートアップや中小・ベンチャー企業がサービスを開始するにあたって必須となる利用規約は、弁護士に作成を依頼するのがお勧めですが、資金的な余裕のないとき、類似サービスの利用規約をコピペして使う例が見受けられます。
しかし、類似サービスの利用規約のコピペやパクリは、違法となるおそれがあります。また、必ずしも違法でない場合でも、異なるサービスの規約を流用するリスクは大きいです。
今回は、類似のサービスの利用規約をコピーして使うリスクについて、弁護士が解説します。
- 利用規約であっても、創作性のある部分のコピペやパクリは著作権法違反
- 利用規約のコピーは、法律問題だけでなく炎上リスクや社会的責任がある
- 弁護士に利用規約作成を依頼するのがお勧め(費用は20万円〜30万円程度)
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
利用規約とは

利用規約とは、ユーザーとサービス提供者の間の契約内容になる文書であり、サービスの提供時や利用時の統一的なルールを定めるものです。
利用規約は「契約」の一種なので、「契約自由の原則」があてはまり、誰と、どのような内容で締結するかは、当事者間の合意で自由に決められます。そのため、利用規約は、サービスの実態に合わせて柔軟に定めるべきですが、一定の書式やひな形があります。
利用規約によく定められる条項は、次の通りです。
- 利用規約への同意条項
- 利用規約の改定・変更への同意条項
- サービス内で利用されるポイントや仮想通貨の取扱いに関するルール
- ユーザー情報の登録手続と、提供された個人情報の取扱いに関するルール
- アカウントの管理、利用停止に関する条項
- ユーザー投稿型サービスにおけるユーザーコンテンツの権利帰属(著作権など)
- サービス利用時の禁止行為と、違反に対する制裁(違約金、損害賠償金、退会措置など)
- サービス利用の中断、中止、終了時のルール
「契約自由の原則」によって、利用規約の条項はある程度自由に定められますが、公序良俗に反する内容は無効となります(民法90条)。また、ユーザーは消費者契約法で保護される「消費者」であることが多く、あまりにユーザー側に不利だったり、事業者側の責任を限定しすぎていたり、過大な損害賠償義務を課したりする規約は、消費者契約法違反として無効になるおそれがあります。
利用規約を作成する際は、「適法性」だけでなく、「炎上を回避できるか」という観点でも検討が必要です。特に、ウェブサービスやアプリが一般化し、ユーザーの権利意識が強まる現在では、不適切な利用規約は、誹謗中傷や企業の信用低下に繋がるおそれが大いにあります。
利用規約の具体的な条項は、そのウェブサービスやアプリの種類に合わせて変更する必要があるため、弁護士に相談するのが最善です。
他社の利用規約をコピーすることは著作権法違反となるか

次に、利用規約と著作権の問題について解説します。
利用規約は、ウェブサービス上やアプリ内に記載されるのが通常で、誰でも見られる状態になっています(ユーザーが閲覧できない利用規約は、契約の内容になりません)。したがって、類似サービス、競合サービスを提供する事業者もまた当然見ることができるので、他社の利用規約を参考にして自社の利用規約を作成することはよく行われています。
しかし、他社の利用規約を「参考にする」程度はともかく、丸々コピーして利用する行為は、著作権侵害の問題が生じるおそれがあるなど、多くのリスクがあります。
著作権侵害とは
著作権とは、著作権法に定められた著作物に関する財産的権利です。
著作物には財産的な価値があり、法的な保護の対象となるので、著作権侵害をすると損害賠償請求や差止請求を受けるリスクがあります。悪質な著作権侵害は犯罪行為にもなり、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられます(複製権侵害のケース)。
著作権法では、「著作物」は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)と定められています。重要なポイントは、「創作性」がなければ、著作物として法的保護の対象にならない点です。
例えば、著作物の典型例としては、小説や論文、脚本、楽曲やその歌詞、ダンスの振付、絵画、版画、彫刻、漫画、書道、写真からコンピュータープログラムに至るまで、幅広いものが挙げられます。
しかし、この中でも「創作性」のないものは著作物とはならないため、ごく短い標語やキャッチフレーズ、ありふれた一般的な表現や、アイディアそれ自体は、著作物にはあたらないとするのが実務です。
利用規約は「著作物」にあたるか
他社の利用規約をコピーして自社の規約を作るとき、「コピペやパクリが著作権侵害とならないかどうか」を検討する必要があります。
利用規約が、前章で解説した「著作物」(著作権法2条1項1号)に該当するなら、他社の利用規約をコピーして利用する行為は、「複製権」の侵害として著作権侵害になります。この点で、「利用規約に『創作性』があるかどうか」が問題となります。
利用規約には、サービス提供者とユーザーの間の契約内容となる性質があるので、その記載は「ありふれた表現」となることが多いです。そのため、利用規約の中でも、ありふれた表現や法律に従った形式的な表現については著作物にならず、コピーしても著作権侵害にはなりません。
これに対し、他社の利用規約に、創作的な表現にあたる部分があるときには、その部分については著作物性が認められ、コピーする行為が著作権侵害となります。
著作権法違反を認めた裁判例
著作権法違反を認めた裁判例として、東京地裁平成26年7月30日判決があります。
【事案の概要】
時計修理サービス業者が、ウェブサイト上の修理規約などを無断でコピーした競合他社の行為について、著作権侵害であるとして1000万円の損害賠償請求と差止請求を行った事案。
【裁判所の判断】
裁判所は、利用規約であっても、その内容について創作的な表現があるときには著作物として保護されるとして、著作権侵害を認め、5万円の支払と利用の差止を命じました。
本裁判例で、裁判所は「通常の規約であれば、ありふれた表現として著作物性は否定される場合が多いと考えられる」としました。一方、「規約であることから、当然に著作物性がないと断ずることは相当ではなく、その規約の表現に全体として作成者の個性が表れているような特別な場合には、当該規約全体について、これを創作的な表現と認め、著作物として保護すべき場合もあり得るものと解するのが相当というべき」と判断し、結論としては著作権侵害を認めました。
つまり、利用規約の著作物性について、著作物となるかどうかはケースバイケースの判断が必要ということであり、創作的な表現の有無を個別に検討しなければなりません。
特にスタートアップ企業、中小・ベンチャー企業などがしのぎを削る新規性の高いサービスの場合、創業者の思いが反映された利用規約には、創作的な表現があり著作物性が認められる場合も多いと考えられます。
他社の利用規約をコピーして利用するリスク

他社の利用規約をコピーして利用することで、著作権法違反になるおそれについて解説しました。そして、必ずしも違法でなかったとしても、事実上のリスクが生じることもあります。
以下では、他社の利用規約のコピペやパクリについて、著作権法違反という法律面以外のリスクを解説します。
サービス自体の価値が低下する
利用規約は、サービス利用に関する重要な取り決めです。そのため、規約がコピペやパクリだと、そのサービスやアプリそのものの新規性が失われたり、評価が落ちたりする危険があります。
スタートアップ企業、中小・ベンチャー企業が、新サービスの開始に伴って利用規約を作成する段階では、「他の類似サービスとは一味違う」「全く新しいサービス」であるという確信があるのではないでしょうか。一生懸命作り上げたサービスを、「既存のものとどこか似ている」「ありふれたサービス」にしないためにも、独自の規約を作成するのがお勧めです。
サービスに合わない利用規約となる
利用規約は、事業者がある程度柔軟に作成することができます。
利用規約を一から作成するのであれば、サービス内容を丁寧に分析し、そのメリットを最大限活かし、デメリットやリスクを軽減できる十分なルールを定めるべきです。オーダーメイドで利用規約を作成すれば、サービスに適した十分なリスクヘッジが可能です。
他社の利用規約をコピーして利用したとき、自社には不要な部分が存在したり、自社のサービスにあてはめると不利益となる条項が存在するおそれがあります。
企業イメージが低下する
他社の利用規約を丸写ししていることがユーザーに発覚したとき、炎上を招くおそれがあります。ひいては、企業イメージの低下に繋がりかねません。
利用規約作成時に違法とならないための注意点

最後に、違法性やリスクを避け、独自の利用規約を作成するための注意点を解説します。
他社の運営する類似サービス、競合サービスの利用規約をコピーして利用することはよく行われていますが、著作権侵害として違法になったり、サービスが陳腐化するリスクがあったりします。
「丸パクリ」は避ける
どれほどサービスが似通っていたとしても、利用規約の「丸パクリ」は避けるべきです。
利用規約を「丸パクリ」すると、著作権侵害の問題はもちろんのこと、サービスを陳腐化させます。有名なサービスの「丸パクリ」であることがユーザーに知られることとなると、誹謗中傷、炎上によって企業の信用が低下するおそれもあります。
注意せずに「丸パクリ」して、利用規約内に記載された固有名詞を記載したまま公開すれば、大変恥ずかしい思いをすることとなります。
創作的な表現をコピーしない
次に、「丸パクリ」でなくても、少なくとも創作的表現をコピーしないよう注意してください。
前章の通り、創作的な表現のコピペやパクリは、著作権侵害として違法になるからです。前述の裁判例(東京地裁平成26年7月30日判決)でも、利用規約が著作物となり得ると判断されており、創作性のある部分をそのまま利用することは法的にも問題があります。
「簡易な利用規約なら、著作権侵害にはならない」という安易な判断は禁物です。
利用規約の作成を弁護士に依頼する
利用規約について、違法性の問題をなくし、かつ、将来のリスクを減らすために、弁護士に一から作成を依頼する方法が有効です。
新規のウェブサービスやアプリを立上げるとき、特にスタートアップ企業、中小・ベンチャー企業などでは、他に売上があったり十分な出資を受けていたりしない限り、経済的余裕はないことが多いでしょう。しかし、起業が増加し、ウェブサービスやアプリの利用規約、プライバシーポリシー、特商法の記載事項(いわゆる「3点セット」)などの書面を作成する機会が増え、ノウハウの蓄積が進んでいます。そのため、利用規約についても、相当複雑かつ難解なものでない限り、リーズナブルな弁護士費用で依頼することができます。
新規のウェブサービス、アプリの立上げ時に必要となる書面の作成にかかる弁護士費用の相場は、20万円~30万円程度が目安となっています。継続して相談が発生することが予想される場合には、顧問契約しておくのも効果的です。
「顧問弁護士の費用(顧問料)」の解説

まとめ

今回は、利用規約をコピーすることの違法性について解説しました。
利用規約といえど、著作権により保護される可能性があります。ビジネスリスクを回避できる適切な利用規約とするには、そのサービスに合った規約を作らなければなりません。
他社が類似サービス、競合サービスを既に展開しているとき、その利用規約を「参考にする」ことはよくありますが、丸写しやコピペ、パクリだと、最悪の場合は著作権侵害となり、損害賠償請求や差止請求の対象となるおそれがあります。
サービス開発に真剣に取り組んできた思いそのままに、利用規約にも真摯に、独自性を出すべきです。新規サービスの開始時に生じる、適法性チェック、利用規約やプライバシーポリシーの作成をはじめ、企業法務にお困りの会社は、ぜひ一度弁護士に相談してください。
- 利用規約であっても、創作性のある部分のコピペやパクリは著作権法違反
- 利用規約のコピーは、法律問題だけでなく炎上リスクや社会的責任がある
- 弁護士に利用規約作成を依頼するのがお勧め(費用は20万円〜30万円程度)
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/