Webサービス、アプリに自社独自のポイントサービスを導入するとき、法的リスクに注意しなければなりません。ポイントサービスには、顧客の購買意欲を向上させ、継続的な利用を促す効果がある反面、ユーザーを不当に害しないよう、法律による制約が加えられているからです。
景品表示法は、「おまけ」として付与する景品についての規制です。景品として付与したポイントが法的規制に違反していると、Webサービスやアプリ本体が良いものでも、違法の制裁を受けるおそれがあります。Webサービスやアプリにおけるポイントサービスでは、特に、サービス開始時のキャンペーンや懸賞・抽選、キャッシュバックなどの販促手段をとるとき、景品表示法の法的規制を遵守しているかが問題になります。
今回は、ポイントサービスを規制する法律のうち、景品表示法の観点から解説します。
- Webサービスやアプリに付ける「おまけ」には法律上のルールがある
- 無料でポイントを付けることには、取引額に応じた上限規制がある
- ポイントサービスの設計次第では、景品表示法違反となるリスクを伴う
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
景品表示法とポイントサービス

景品表示法(正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」)は、商品やサービスの品質、内容、価格についての不当な表示を規制し、過大な景品によって不当に顧客を誘引することを防止する、消費者保護のための法律です。景品表示法で禁止されるのは、過大な景品と不当な表示です。
Webサービスやアプリに導入する自社独自のポイントサービスが、無償で「おまけ」として付与されるとき、景品表示法の法的規制のうち、過大な景品を禁止するルールに違反しないか気にしておかなければなりません。
ポイントサービスを開始するとき、ユーザーの注目を集めて販促効果を得るため、ポイントを無償付与することがあります。景品表示法の法的規制は、「一定確率の『抽選』でポイントが当たるサービス設計」と「一定の利用頻度、利用態様の人に『一律』でポイントを付与するサービス設計」のいずれにも適用される可能性があります。
例えば、景品表示法に注意が必要なポイントサービスは、次の通りです。
- プレゼントキャンペーン
例:ポイントを全員に無償でプレゼントする。 - 懸賞・抽選
例:一定確率で、当選者にポイントを付与する。 - キャッシュバック
例:購入者に対して一定割合のポイントを付与する。
特に「ポイントサービスと資金決済法の法的規制」の通り、ポイントサービスが資金決済法の制約を受けないよう、ポイントを無償とし、期限を6ヶ月以内としてサービス設計する例では、景品表示法への配慮が漏れていることがあり、注意を要します。
資金決済法の適用を避けるために無償ポイントとしても、今度は景品表示法の規制を意識して慎重に運用しなければならなくなります。わかりやすくいうと、有料のポイントでは資金決済法、無料のポイントでは景品表示法を意識して設計すべきということです。
「ポイントサービスの法律問題」の解説

景品表示法の「景品類」とは

無償で発行・付与する「おまけ」としてのポイントサービスは、景品表示法の法的規制を検討する必要があります。無償付与だとしても、ポイントを「顧客吸引力」として利用するので、ユーザーに対する不当な扱いにならないよう法的規制が課されるからです。
景品表示法で、法的規制の対象となるものは「景品類」(景品表示法2条3項)であり、次のように定義されています。
景品表示法2条3項(抜粋)
この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。
景品表示法(e-Gov法令検索)
なお、要件を満たす場合でも、「内閣総理大臣が指定するもの」である必要があり、この点で、告示などで示された例外規定にあてはまるときは「景品類」に該当しません。
以下では、各要件について、どのようなポイントサービスの設計をすると「景品類」に該当するのか、解説していきます。
【要件1】顧客誘引の手段となる
「景品類」の1つ目の要件が、顧客誘引の手段となることです。
付与されたおまけが、顧客に魅力を示し、サービス購入の動機になっているか、という要件です。顧客誘引の手段となっているかどうかは、発行者の意思ではなく、客観的に判断されます。自社のWebサービスやアプリ内で利用できるポイントを無償発行するケースは、顧客のサービス利用を促進する目的があることがほとんどなので、この要件を満たすと考えられます。
なお、「アンケート回収に対してポイントを無償でプレゼントする」といったケースのように、市場調査、顧客満足度調査などを目的とする場合でも、結果的に顧客誘引の手段となっていると判断されるおそれがあります。
【要件2】取引に付随して提供される
「景品類」の2つ目の要件が、取引に付随して提供されることです。
取引に付随して提供する場合には、以下の双方を含みます。
- 取引の条件として、経済上の利益を提供する場合
- 取引の勧誘の際に、経済上の利益を提供する場合
したがって、商品・サービスの利用・購入時にポイントを付与するケースはもちろん、利用・購入前でも、勧誘の手段として先にポイントを無償付与するときは、この要件を満たします。これに対して、利用者、購入者を紹介した人に、謝礼として与えた経済上の利益は「取引に付随する」とは言えません。そのため、紹介者へのポイント付与は、景品表示法の「景品類」に該当しません。
【要件3】経済上の利益がある
「景品類」の3つ目の要件が、経済上の利益があることです。
経済上の利益の典型例は、金銭に代替される価値を持つケースです。例えば、ポイントを貯めると商品やサービスのグレードが上がる場合や、ポイント自体で商品やサービスの売買ができる場合、そのポイントには経済上の利益があるといえます。
売買できなくても、通常は経済的対価を支払って取得するのが通常だと言えるときは、「経済上の利益があること」の要件を満たします。
これに対し、Webサービスやアプリ内で、「名誉が上がる」といった意味しかない表彰、バッジ、ランク、トロフィーなどのサービスは、通常、経済的対価を支払って取得するものとはいえず、経済上の利益はないと考えるのが実務です。
例外規定にあたるか
以上の3要件を満たす場合でも、告示によって示された例外規定にあたるときは、「景品類」に該当しません。このことを示す告示が、「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公取委告示第3号)(「定義告示」)です。
定義告示には、「値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益」は、「景品類」にあたらないと定められています。そして、「値引」の定義について「景品類等の指定の告示の運用基準について」(「定義告示運用基準」)にて、次の2点が示されています。
- 取引通念上妥当な基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること
- 支払った代金について割り戻しをすること
つまり、ポイント付与と同時に購入した商品・サービスを減額する場合だけでなく、次に購入するとき減額される場合も「値引」にあたります。したがって、無償ポイントのうち、次回以降「1ポイント=1円」といったように利用できるサービス設計は「値引」該当するので、景品表示法の「景品類」にはあたりません。
ただし、「値引」以外にも特典がついたポイントの場合には、やはり景品表示法の「景品類」にあたり、法的規制の対象となります。
商品・サービスの対価となるポイントでも、自社サービス内でのみ利用できるのか、他社サービスでも利用可能なのかによって、「値引」にあたり景品表示法の「景品類」かどうかの判断が異なります。
他社サービスでも利用できるポイント(いわゆる「共通ポイント」)は、ポイント発行者の商品・サービスの減額という意味だけでなく、他社の商品・サービス購入にも利用できるため、景品表示法の「景品類」にあたります。
景品表示法におけるポイントサービスの法的規制
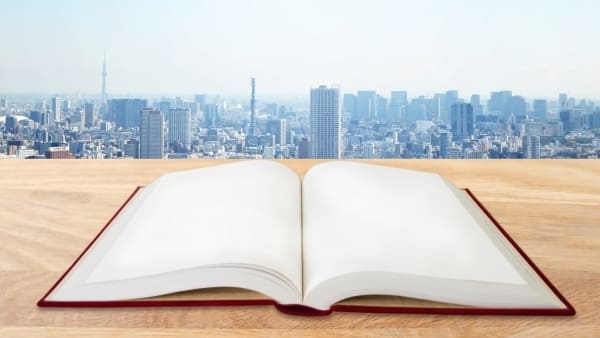
景品表示法の「景品類」にあたるポイントサービスは、その最高額や総額が制限されます。不当に高額な「おまけ」の付与を許すと、「本体」より「おまけ」を目的にユーザーが購買を決定し、自主的かつ合理的な判断ができなくなってしまうからです。
そのため、景品表示法の「景品類」に該当するポイントサービスは、以下の景品規制を遵守する必要があります。なお、景品規制は、ポイント付与の方法によって2つのケースに分けられます。
懸賞・抽選でポイントを付与する場合の法的規制
1つ目が、懸賞・抽選でポイントを付与するときの規制です。
景品表示法の「懸賞」は、以下の2つの方法によって「景品類」を提供することをいうものとされています。
- くじその他偶然性を利用して定める方法
例:「抽選で3名様にポイントをプレゼント」や「先着1名様にポイント付与」といったキャンペーンによりポイントを付与する場合。 - 特定の行為の優劣または正誤によって定める方法
例:キャッチフレーズを公募し、優秀賞をとった人にポイントを付与する場合。
景品表示法の「懸賞」にあたる「景品類」の提供をする場合は、その取引額に応じた最高額、総額の法的規制があります。
| 懸賞による取引価額 | 景品類の最高額の限度額 | 景品類の総額の限度額 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
| 5,000円以上 | 10万円 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
例えば、Webサービスやアプリ内で1,000円以上のサービス利用者を対象にプレゼントのキャンペーンを行う場合、ポイントの最高額の限度は20,000円(1,000円×20倍)となります。
購入すれば、その購入額によらずポイント付与の対象となるときは、「取引価額」は100円とすることとされています。つまり、このときの最高額の限度は2,000円(100円×20倍)となります。
なお、総額の規制は「売上予定総額の2%」とされますが、「売上予定総額」は、前年の販売実績などを参考に合理的に算出すればよく、結果的に売上が予想を下回り、「景品類」の総額が売上総額の2%を超えたとしても法違反とはなりません。
全員にポイントを付与する場合の法的規制
2つ目が、全員にポイントを付与する場合の規制です。
景品表示法では、このように購入者や申込者全員に対して、もれなく「景品類」を提供することを「総付景品」といいます。総付景品の場合、懸賞によるポイント付与とは異なった法的規制があり、その取引額に応じて最高額の法的規制があります。
| 取引価額 | 景品類の最高額の限度額 |
|---|---|
| 1,000円未満 | 200円 |
| 1,000円以上 | 取引総額の20% |
「取引価額」とは購入金額のことです。なお、購入者を対象とするけれども購入額を問わないで全員に景品類を提供する場合には、その景品類の最高額は「取引価額の20%」とされています。
ただし、プレゼントの対象商品またはサービスの取引価額のうち、当該景品類提供の対象商品または役務について通常行われる取引価額のうちの最低のものが1,000円を下回っていると認められるときは、取引価額を1,000円として、景品類の最高額を200円とすることができます。
以上のことから、購入者全員にプレゼントするキャンペーンで配布できる景品は、自社サービスの最低価格が1,000円未満のときは200円が上限となります。また、自社サービスの最低価格が1,000円以上の場合には、その最低価格の20%が上限となります。
まとめ

今回は、景品表示法におけるポイントサービスの規制について解説しました。
ポイントサービスを開始する際は、法律に抵触しないか、慎重に判断しなければなりません。景品表示法によるポイントサービスの法的規制は、無償でポイントを付与する際に適用されます。なお、有償ポイントの場合は、資金決済法の前払式支払手段として、ポイント発行者は更に厳しい義務を負う可能性があるので注意を要します(「ポイントサービスの導入時の資金決済法の法的規制と、規制回避の方法」参照)。
法律違反とならず、かつ、サービスとしても有効なポイント設計とするには、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けることが有効です。特に、スタートアップ企業、中小・ベンチャー企業が新規性の高いビジネスを開始するときは、事前の適法性チェックが欠かせません。
ポイントサービスの適法性をはじめ、企業法務についてお悩みの会社は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
- Webサービスやアプリに付ける「おまけ」には法律上のルールがある
- 無料でポイントを付けることには、取引額に応じた上限規制がある
- ポイントサービスの設計次第では、景品表示法違反となるリスクを伴う
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/


