就職時に企業から「身元保証人を立ててほしい」と求めるケースがあります。
しかし、労使共に、「身元保証」がどのような契約か、身元保証人がどのような責任を負うか、正しく理解していないことが多いです。企業が身元保証を求める理由は、労働者の不正や業務上のミスによる損害の補填が主な目的です。労働者側は「重い責任を負わされるのではないか」と不安を抱く人もいますが、就職時に身元保証人を立てる慣行は一般化しており、法律に沿って正しく運用されれば、過剰にリスクを気にする必要はありません。
特に、2020年の民法改正で、極度額(上限額)の設定が義務化されるなど、身元保証人のルールは法律で定められています。
今回は、就職時の身元保証の仕組みと、保証人が負う責任の範囲について弁護士が解説します。保証人を依頼する企業にとっても、引き受ける労働者側にとっても、双方が知っておくべき重要な知識を整理してお伝えします。
- 身元保証は、企業の将来のリスク回避のための契約
- 保証人の負担を軽減するため、2020年民法改正で極度額の定めが義務化された
- 法改正に対応した身元保証契約書を準備し、適正な内容で締結する必要がある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
就職時の身元保証とは

はじめに、就職時の身元保証の基本的な仕組みについて解説します。
就職時の身元保証とは、企業が採用する労働者に対し、万が一不正行為や業務上のミスによって会社に損害を与えた場合に備え、あらかじめ第三者(身元保証人)がその責任を負うことを保証するよう求める契約です。
身元保証の基本的な仕組み
身元保証は、企業と身元保証人との契約です。
企業が、社員を雇用する際に、その労働者本人ではなく、信頼できる第三者(通常は親族や身内)に依頼して、「その人が問題を起こさない」と保証してもらうと共に、万一のときは損害賠償責任を共に負うことを約束させる内容です。企業にとっては、労働者の行動が将来のリスクとなる場合に備えた「保険」の役割を果たします。
身元保証人は、労働者が不正やミスを犯した際に、その損害に対して金銭的な賠償責任を負います。ただし、保証人の責任は、身元保証契約書に明示された範囲内に留まります。後述の通り、2020年施行の改正民法で極度額(上限額)の設定が義務化されました。
多くの企業では、採用時に身元保証人を立てることを求めるのが通例です。特に、現金や貴重品を扱う部署、機密情報に触れる重要な役職で、リスク管理を徹底する手段として用いられます。
身元保証契約の法的根拠と法規制
就職時の身元保証は、「身元保証二関スル法律」(身元保証法)に基づいて行われます。
同法は、身元保証契約における保証期間や保証人の責任範囲、通知義務などを規定し、身元保証人が過大な責任を負わないよう規制しています。
法律に定められた身元保証に関するルールは、主に次の通りです。
- 身元保証人の保証期間は3年間が原則。
- 保証期間を合意で定める場合は5年間が上限(5年以上の期間を定めても、その期間は5年に短縮される)。
- 身元保証契約は更新可能だが、更新後の期間の上限も5年間。
- 保証額は、裁判所において、使用者の当該従業員への監督状況や、身元保証人の契約締結の経緯など、様々な事情を総合的に考慮して判断される。
労使間には上下関係があり、入社時の身元保証を断るのは現実的に困難です。そのため、会社が負った損失を、全て社員や身元保証人に責任転嫁するような不当な扱いを避けるため、法律が一定の保護をしているのです。企業が、労働者を使用して利益を上げている以上、それによって生じた損失についても、労使間で公平に分担されるべきであり、故意のあるような悪質なケースでない限り、全てを従業員負担とするのは問題があります。
2020年4月に施行された民法改正により、個人保証契約のうち将来発生する不特定の債務を包括的に保証する「根保証」の場合、極度額(上限額)を定めなければなりません。同改正は、身元保証契約にも適用され、保証人が負う金銭的責任の上限を定める必要があります。
身元保証人のリスクを軽減するための責任制限は、たとえ労働者や身元保証人の同意があっても違反することはできません。
採用時に企業が身元保証を求める理由

次に、採用時に企業が身元保証を求める具体的な理由を解説します。
企業が新たな従業員の入社時、身元保証を求める背景には主に「信用確認」と「リスク管理」の2つの側面があります。単なる法的手続きというだけでなく、今後の労使の信頼関係を築くために、身元保証は重要な役割を果たします。
労働者の信用を確認する手段となる
身元保証人を立てることには、信用を確認する意味合いがあります。
身元保証人を求めることで、企業としては、履歴書や採用面接で見抜けなかった労働者の人物評価を聞き、信用に値する人物であるかを確認することができます。また、労働者に対し、「不正やミスを起こした場合は身元保証人に影響が及ぶ」という心理的プレッシャーを与えることで、仕事に集中させ、不適切な言動を抑制する効果を生むことも期待されています。
就活では、内定後や入社時などに、企業から身元保証契約書への署名を求められる例が多いです。
損害賠償の担保を得てリスクを管理する
身元保証は、損害賠償請求の担保を得て、企業側のリスクを軽減する意味合いがあります。
企業にとって、採用した労働者の不正やミスで損害が生じた場合、被害回復が必須となります。ただ、企業の受ける損害の大きさに比して、労働者の資力は十分でないことも多く、その担保を得る目的で身元保証契約を締結し、賠償の請求先を増やしてリスク分散する狙いがあります。
特に、金銭や機密情報を扱う業務では、従業員の不正による企業のダメージは大きく、身元保証人を立てることで対策を講じておく必要があります。この点から、「身元保証人を付けることができるかどうか」は、入社する労働者の信用や評価を基礎づける指標となる側面もあります。
身元保証人の責任とリスク

次に、身元保証人になることの責任とリスクについて解説します。
身元保証人となることは、採用された労働者が不正やミスによって企業に損害を与えた場合に、賠償責任を負う可能性があるということです。
身元保証契約では、身元保証人は、労働者が起こした不正やミスにより生じた損害について、契約の範囲内で責任を負います。2020年の民法改正により、身元保証において極度額(上限額)を定めることが必須となったので、身元保証人の負う責任は、一定程度制限されます。
また、そもそも、労使の関係性において、企業に損失が生じたからといってその全てが「労働者の責任」とも言い切れません。実際、企業側の管理や監督の不行き届きを理由として、労働者側の負担を減らす判断が下された裁判例も数多くあります。
なお、前述の通り、身元保証契約の有効期間は原則として3年間、合意がある場合でも最長5年間とされ、その後に発生する損害については保証責任を負いません。
以上のことから、身元保証人を頼まれたときは、契約内容をしっかりと見た上で、どれほどの責任が生じる可能性があるのかを理解し、慎重に判断するようにしてください。
2020年の民法改正における「身元保証」の変更点
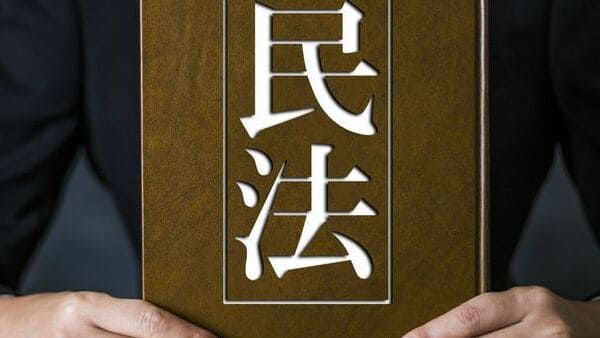
2020年4月1日に施行された民法改正において、身元保証についても大きな変更がありました。特に、身元保証人が負う金銭的責任の上限設定が義務化された点が重要です。
なお、改正民法は、2020年4月1日以降に締結された契約に適用されるので、それ以前に取得した身元保証書を変更したり、再締結したりする必要はありません。
極度額の設定義務
就職時の身元保証契約は、将来発生する不特定の債務を包括的に保証する「根保証契約」の性質を持ちます。改正民法では、個人の根保証については極度額(上限額)の明記が必須とされました。これは、保証人が予測不能な大きな金銭負担を負うリスクを回避するための改正です。
民法改正で追加された条項は、次の通りです。
民法456条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)
1. 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他の債務に従たるすべての者及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2. 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
この規定により、身元保証人は「最大いくらまで責任を負うか」を契約書上明らかに知ることができ、事前にリスクを把握できるようになりました。上記条文の通り、個人の根保証について極度額(上限額)の定めがなければ、その契約自体が無効となります。したがって、企業側は今後、身元保証契約書に極度額(上限額)を必ず定めるようにしなければなりません。
「民法改正(2020年4月施行)」の解説
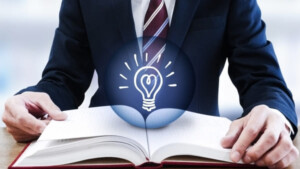
企業の通知義務の強化
企業は、労働者の状況に変化が生じ、身元保証人の責任に影響する可能性のあるときは、速やかに身元保証人に通知することが義務付けられました。具体的には、社員の役職変更、業務内容の大幅な変更、懲戒処分など、身元保証人のリスクとなる事項が生じる場面が典型例です。
この改正により、企業と保証人の双方が契約内容やリスクを正確に理解し、互いに適切な判断を下せるようになることが期待されています。
「保証契約の基本」の解説

身元保証契約を締結する際の注意点

次に、就職時の身元保証契約を結ぶ際に、各立場で注意すべきポイントを解説します。
就職時の身元保証は、企業にとっても、労働者や保証人にとっても将来のリスクとなる重要な取り決めです。契約締結時には、各当事者が法律を十分に理解し、準備することが不可欠です。
労働者側の注意点
第一に、労働者側の注意点は、次の通りです。
適任者を保証人に選定する
労働者は、身元保証人として適任者を選定しなければなりません。
誰でもなれるわけではなく、企業が信頼を置けると考える一定の条件(年齢、関係性、収入など)を定める例が多いです。
通常は、夫や妻、両親、兄弟などといった家族や親族から選定します。身元保証人をお願いする際は、その人物が経済的に自律しており、万一の際に責任を負う能力がなければいけません。また、自身と同等の責任を負うおそれがあるため、関係性の薄い友人や知人を身元保証人とするのはお勧めしません。
就職先に対し、労働者自身の評価の裏付けとなる機能もあるため、会社が求める「信用」「収入」を備えた人物かどうかも検討要素となります。
契約内容を十分に確認する
就職の身元保証人には、万一の際に迷惑をかける可能性もあるので、労働者側でも契約書をよく確認し、誤りや不備がないか精査しておいてください。特に、2020年施行の改正民法で義務化された極度額(上限額)が、しっかりと明記されているか確認してください。
企業側の注意点
第二に、企業側の注意点についても解説します。
極度額(上限額)の記載と通知義務
企業は、本解説の通り、極度額(上限額)を記載した身元保証契約書を作成し、労働者に提示しなければなりません。また、労働者や身元保証を依頼された人の中には、「際限なく不当な請求をされるのでは」などと抵抗感を示す人もいるので、誤解が生じないよう、身元保証の役割や機能をしっかりと説明し、理解を求めておきましょう。
適切なリスク管理のために、2020年3月以前に使用していた身元保証契約書は、法改正に合わせて修正する必要があります。
民法改正に対応した身元保証書【書式・ひな形】
2020年4月以降の改正法に対応した身元保証書の書式、ひな形を紹介します。企業側が書類を準備すべきなので、参考にして作成してください。
身元保証書
【会社名・代表者名】宛
【労働者の指名・住所など】
上記の者が、この度貴社に入社するにあたり、今後本人の身元は勿論、その雇用契約より生ずる一切の義務に対し、本人と連帯して保証の責めに任じ、本人の故意、過失により貴社の被った損害を賠償する旨を確約します。その際、お支払いすることとなる賠償の上限額は金〇〇円とします。なお、催告の抗弁権を放棄します。
保証期限は、20XX年XX月XX日から20XX年XX月XX日までのX年間とし、期間満了のXヶ月前までに書面をもって更新しない旨の申し出をしなかった場合は、満了日の翌日から引き続きX年間同一条件にて更新することを了承します。
20XX年XX月XX日
身元保証人 ○○○○ 印
(本人との続柄: )
現住所:○○県○○市○○町△―△―△
生年月日:○○年○○月○○日
重要な点は、繰り返しになりますが保証の上限額(極度額)を記載です。この部分がないと身元保証書自体が無効となるので、必ず明記してください。
あわせて、身元保証人の身分証明書のコピーを求める例もあります。また、企業によっては実印を求めることもありますが、少なくとも、労働者と保証人で同じ印鑑を使い回すことは避けるべきです。
極度額(上限額)の決め方
極度額(上限額)を設定するにあたり、「いくらにしたらよいか」という相談をよく受けます。企業側は上限が高いほど安心ですが、高額すぎる保証は、身元保証人を探すのが困難となりますし、最悪は「公の秩序又は善良な風俗に反する法律行為」(民法90条)に該当し、公序良俗違反として無効となる危険もあります。一方、少額過ぎると、悪質な行為によって多大な損害を負ったとき十分は被害回復ができません。
民法改正以前、身元保証人の保証額が争われた裁判例で、会社の監督状況、身元保証書の締結の経緯など、様々な事情が総合的に考慮されてきました。これを参考にすると、民法改正後の保証の上限額(極度額)の決め方は、次の点を参考にすべきです。
- 保証人がリスクを予見可能か。
- 労働者・企業・保証人の三者が納得できる合理的な金額か。
- 企業側のリスクマネジメントの実効性があるか。
企業側としては、身元保証人となる予定の人に対して、「なぜその上限額なのか」を合理的な理由と共に説明できるようにしておかなければなりません。業種・業態や企業規模、労働者の地位・役職や担当業務によっても、適切な上限は異なります。
身元保証人側の注意点
第三に、身元保証人側の注意点を解説します。
責任範囲とリスクを把握する
身元保証人となる人としては、万一の場合にどれほどの賠償責任を負うリスクがあるのか、その範囲や極度額(上限額)を確認することが大切です。自身がそのリスクを負えるか、保証する労働者との関係が良好かどうかも含め、慎重に判断する必要があります。
十分な説明を受ける
身元保証契約を締結する前に、十分な説明を受けましょう。
身元保証書を提示する企業側からの説明はもちろんですが、保証する労働者からも「どのような会社なのか」「なぜ入社するのか」「どのような業務を担当するのか」「しっかり働く覚悟があるのか」といった観点から念入りに確認をすることで、将来に賠償しなければならないような事故の起こるリスクを未然に防ぐことができます。
身元保証人の候補者がいない場合の対策
以上の通り、企業側の都合によって作成されることの多い身元保証契約ですが、中には、身元保証人の候補者がいない人もいます。このような場合にどのような対策を講じるべきか、労働者、企業のそれぞれの立場から解説します。
労働者側の対策
労働者側では、身元保証人を確保できない場合、早急に企業に事情を説明し、どのような代替措置を講じられるか相談してください。隠したり嘘をついたり、友人に代筆してもらったりといった不誠実な対応は全くお勧めできません。
早期に、誠実に説明をすれば、保証人以外の方法でリスク管理を行うため、企業側としても対応策を検討してくれる可能性があります。これに対して、嘘をついたことが後から発覚すれば、信頼を失い、最悪は解雇などの厳しい処分も懸念されます。
身元保証人の代行サービスなども存在するので、検討してみてもよいでしょう。
企業側の対策
企業側では、身元保証人を用意できない応募者がいるとき、大前提として検討すべきなのが「身元保証がなくても、その人を入社させたいかどうか」という点です。雇用契約の締結前であれば、まだ「入社させない(雇用契約を結ばない)」という選択肢もあり得ます。
入社させる場合、親や親族などの近しい身内がいないといった事情がある社員については、身元保証人を立てる代わりに、次の対策があります。
- 労働者自身に誓約書を記載させる。
- 緊急連絡先として親族の連絡先を確保しておく。
このような対策によって、身元保証人を立てなかったことで、万が一の際に損害賠償を請求しそこねてしまうリスクを軽減することができます。
まとめ

今回は、就職時の身元保証について、2020年4月の民法改正も踏まえて解説しました。
身元保証は、企業にとって、労働者の不正やミスによって損失を被った際の対策として必要不可欠なものです。一方で、民法改正によって極度額(上限額)の定めが義務化されたり、身元保証人への通知義務が生じる場面があったりと、法的にも注意しなければならないポイントがあります。
身元保証契約を適切に締結し、リスク管理に役立てるために、企業側としては身元保証契約書の準備から弁護士にサポートしてもらうのが適切です。また、労働者や身元保証人側においても、不当な契約書を締結させられそうなときは、弁護士に事前のチェックを依頼すべきです。
- 身元保証は、企業の将来のリスク回避のための契約
- 保証人の負担を軽減するため、2020年民法改正で極度額の定めが義務化された
- 法改正に対応した身元保証契約書を準備し、適正な内容で締結する必要がある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
民法の改正は、契約や取引、債権債務など、生活や企業経営に密接に関わります。改正の内容を正しく把握しなければ、思わぬトラブルを招くおそれもあります。
適切な権利行使をするためにも、民法改正に関する解説記事を通じて、最新のルールを理解しておいてください。


