売買契約は、日常生活でもビジネスでも、頻繁に登場する基本的な契約です。
例えば、商品を購入する、サービスを提供する、不動産を売却するなど、当事者間で売買が起こる全てのケースで、「売買契約」が締結されます。しかし、身近な契約形態であるがゆえに、高額で重要な売買なのに口約束で済ませ、後でトラブルになるケースも少なくありません。
民法555条では、売買契約について法的な定義がされています。また、2020年4月1日に施行された民法改正では、危険負担や契約不適合責任など、売買契約において問題となる売主・買主の責任分担について、重要なルール変更が行われました。
今回は、売買契約の基本的な法律知識と、契約成立の要件、法的効力について、民法改正も踏まえて弁護士が詳しく解説します。
- 売買契約は、契約書がなくても、当事者の合意だけで有効に成立する
- 「物を買う」など身近な契約類型でも、民法上のルールに注意すべき
- 売買に関わる契約不適合責任、解除、危険負担などが2020年に改正された
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
売買契約とは

売買契約とは、財産権を移転する代わりに代金を支払うことを約束する契約です。
わかりやすく言うと「モノとお金の交換」が売買であり、日常生活やビジネスでも身近で、頻繁に用いられる典型的な契約類型です。民法555条は、売買について次のように定めています。
民法555条(売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法(e-Gov法令検索)
この条文からも分かる通り、売買契約は、以下の2つの約束が合致することで成立します。
- 売主が「財産権(物や権利)を相手方に移転する」旨を約束すること
- 買主が「その代金を支払う」旨を約束すること
つまり、「売ります」「買います」という当事者の合意(意思表示の一致)があれば、売買契約は有効に成立し、法的な効力が発生します。契約書は必須ではなく、口頭でも売買契約は成立しますが、不動産売買などの高額の取引では契約書を締結するのが通例です。
売買契約にも、他の契約と同じく「契約自由の原則」が適用されるので、誰と、どのような条件で契約するのか(または、しないのか)は、当事者の自由に決めることができます。したがって、売主と買主が納得していれば、自由に売買契約を締結し、内容も任意に決められます。
ただし、法令や、公序良俗に反する契約内容は無効となります(民法90条)。例えば、違法薬物や盗品を対象とした売買契約は、合意があっても法律上無効です。
売買契約の成立要件

次に、売買契約の成立要件について解説します。
売買契約は、当事者が自由に締結でき、成立に特別な手続きは不要です。契約書がなくても成立しますが、紛争防止のためにも、合意内容を契約書に記録しておくのが大切です。
申込みと承諾による意思表示の合致
売買契約の成立には、「申込み」と「承諾」による意思表示の合致が必要です。
例えば、「ある不動産を1,000万円で売ります」という申込みに対し、「1,000万円で買います」というように承諾の意思表示をすれば、その時点で売買契約が成立します。当事者双方の意思表示が合致することで、契約が法的に有効に成立するからです。
この場合、意思表示は、相手方に到達した時点で効力を生じます(到達主義、民法97条)。2020年の民法改正で、従来採用されていた「承諾」についての「発信主義」(意思表示を発信したときに効力を生じるとする考え方)は廃止され、到達主義に統一されました。
口頭契約とすると証拠が残りにくいので、争いになるリスクを軽減するには、合意の内容を記録し、契約書を作成すべきです。また、メールやLINE、オンラインショッピングなど、電子的な手段による意思表示でも、売買契約は有効に成立します。
「民法改正(2020年4月施行)」の解説
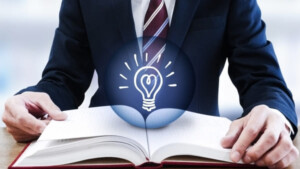
売買の目的物と代金額の特定
売買契約が有効に成立するには、目的物と代金額の特定が必要です。つまり、「何を売るのか」「いくらで売るのか」が明確化されていなければ、売買契約の合意があったとは言えません。例えば、「この車を100万円で売る」というように具体的に示したり、店舗やオンラインショッピングで値札が付いていたりすれば、目的物も金額も明らかです。
売買の目的物は、財産権であればよく、商品や土地・建物などの不動産、サービスや権利も、売買契約の対象となります。
一方で、単に「何かを売ってあげる」「それほどの値段ではない」といった曖昧な表現のみでは、目的物や金額が特定されず、売買契約は成立しません(このように曖昧に示して何かを売りつけようとするのは、悪質商法や詐欺の可能性もあります)。
目的物や価格について、売主と買主の認識にズレがあると、錯誤(民法95条)を理由として契約が取り消される可能性もあります。
「錯誤の基礎知識」の解説

書面などの形式は必須ではない
民法上、売買契約を結ぶのに書面(売買契約書)は必須ではありません。
売買契約は、契約書を作成しなくても、当事者の合意で成立する「諾成契約」の性質があるからです。実際、コンビニで商品を買うのも売買契約ですが、わざわざ契約書を交わすことはなく、代金を払って商品を購入するはずです。
ただし、後のトラブルを防ぐには、売買契約書が重要な役割を果たします。特に、金額の大きな取引や企業間取引(BtoB)の場合、契約内容の詳細(目的物、代金額や支払条件、引渡日など)を明記した書面がないと、裁判などで契約の存在を証明することが困難になってしまいます。
また、不動産会社が仲介する不動産売買は、宅建業法によって売買契約書の交付が義務付けられているなど、例外的に一部の取引では売買契約書が必須となります。
売買契約の法的効力

売買契約が成立した際に、民法555条によって具体的にどのような法的効力が生じるのかについても解説します。売買契約が成立した時点で、当事者双方には法的な義務が生じ、履行しなかった場合には責任を追及されることとなります。
契約の成立時に所有権が移転する
売買契約は、当事者が合意した時点で法的効力が生じます。
売買に関する意思表示が合致すると、その時点で契約が成立し、双方に契約上の義務が生じます。具体的には、売主に目的物の引渡し義務、買主に代金の支払い義務が生じます。売買契約は、「双務契約」「有償契約」なので、双方が互いに対価的な義務を負い、一方が契約上の義務を果たさなければ、他方も義務の履行を拒むことができます(同時履行の抗弁権)。
法律上は、契約を締結した時点で、所有権が移転すると考えるのが一般的です。
ただし、所有権の移転時期について、民法555条は任意規定であるため、契約や約款によって所有権の移転時期を変更することも可能です。例えば「代金の支払いを完了した時点で所有権が移転する」などとして時期を遅らせる例はよく見受けられます。
また、目的物の引渡し時期については、必ずしも契約時や所有権移転時期と同じというわけではなく、契約によって指定することができます。
債務不履行や契約解除
売買契約が成立したにもかかわらず、一方が義務を履行しなかった場合、債務不履行となり、法的責任が生じます。例えば、売主が契約通りの商品を渡さなかった場合や、買主が代金を払わなかった場合が典型例です。
この場合、相手方は、相当の期間を定めて催告し、それでも履行されない場合には解除できます(民法541条)。また、履行不能や履行拒絶が明らかな場合には、無催告解除も可能です(民法542条)。更に、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときや、債務の履行が不能なときは、生じた損害の賠償を請求することができます(民法415条)。
なお、契約違反で責任追及されるリスクは、売主と買主のどちらにもあるので、契約内容の確認や履行の準備を怠らないことが双方にとって重要です。
売買契約書の作成時のポイント

売買契約は、当事者の合意のみで成立しますが、後のトラブルを防止するには契約書を作成し、内容を明確に定めておくことが重要です。特に、2020年4月の民法改正によって変更された契約のルール(契約不適合責任や解除、危険負担など)の法的扱いには注意を要します。
以下では、売買契約書に明記すべきポイントについて解説します。
売買の目的物に関する条項
売買契約には、目的物の特定が必須です。後でトラブルにならないよう、以下の点に注意して契約書に目的物を明確に定めておいてください。
- 目的物を特定する情報
商品名、型番、数量、仕様などを、できるだけ詳細に明記します。特に、目的物が不動産の場合には、登記情報を正確に転記するようにしてください。 - 納入の方法
納入場所がどこか、持参するのか配送するのか、設置が必要か、引渡し時期はいつかといった点に注意して明示してください。
買主の立場では、目的物の記載が曖昧だと、求めていたものが手に入らず、トラブルの原因となります。後から「契約書で予定していた売買契約の目的物ではない」と主張したくても、そもそも目的物の特定が抽象的だと責任追及は困難です。
売買代金に関する条項
売買契約では、代金額の記載も必要となります。金額はもちろんのこと、支払い期限や条件、遅延時の対応などについて、次の点を意識して定めておいてください。
- 代金額について
総額、税込か税抜か、通貨の種類などを記載します。 - 支払期限
支払期限を具体的に定めてください。特に、分割払いの場合には、支払期限とスケジュールを定める必要があります。 - 支払方法
振込の場合は振込先や振込手数料の負担、現金交付の場合は持参先を指定します。 - 支払遅延が生じた場合の扱い
利息や遅延損害金、契約違反があった場合の違約金などの制裁を定める例が多いです。分割払いの場合には、期限の利益喪失(支払いに遅滞が生じたら残額を一括で払うなどの条項)を定めるのが通例です。
売主の立場では、代金額の記載が曖昧だと、財産権を移転したのに、予定していた対価が受け取れないおそれがあります。債権回収の際にも、契約書が重要な証拠となるので、慎重に契約書を作成、チェックするようにしてください。
契約不適合責任
売買契約の目的物が契約に適合していない場合、契約不適合責任を追及できます。
改正前は、「隠れた瑕疵」がある場合に限り「瑕疵担保責任」を追及できる定めでした。しかし、2020年の民法改正で「契約不適合責任」が新設され、目的物の性質や状態などが契約内容に適合しないときは、追完請求(修補や代替品の提供など)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除といった責任を追及できる制度となりました。
契約不適合責任は、「隠れた瑕疵」に限定されていた瑕疵担保責任と異なり、買主が瑕疵を知っていたとしても、契約に不適合であれば売主に責任が生じる可能性があります。
契約不適合責任について、売買契約書では以下の点を盛り込む必要があります。
- 不適合が軽微な場合は解除不可とする条項
民法541条但書に定められた内容ですが、確認的に定めておくと丁寧です。 - 不適合があるとみなす条件
目的物の性質や状態を詳しく記載したり、検品基準を設けたりする例があります。設計図や仕様書を添付することで契約内容をより明確化するのも有効です。 - 責任追及の期間制限
契約不適合責任の期間制限(1年)は任意規定なので、契約で変更可能です。 - 追完の方法と範囲、売主の費用負担など
契約不適合責任が生じ、追完請求が選択される場合、どのような方法で追完すべきか、契約書であらかじめ定めることで、予見可能性を高めることができます。
なお、契約不適合責任の追及は、個人間の売買契約の場合、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければなりません(民法566条)。また、事業者間の売買では、目的物を受領したら遅滞なく検査し、不適合を発見したら直ちに通知をする必要があり、直ちに発見できない場合でも、引渡しから6ヶ月以内に通知する必要があります(商法526条)
「契約不適合責任」の解説

売買契約の解除に関する条項
売買契約書には、どのような場合に契約解除が可能かを明記しておく必要があります。
改正前の民法は、契約の解除には相手の帰責性(落ち度)を必要としていましたが、2020年の民法改正により、解除は「契約の拘束力からの解放」を趣旨とするものに改められ、帰責性とは無関係に解除できるようになりました(なお、債権者に帰責性があるときは、解除は認められません)。また、解除は「重大な契約違反」に限定され、「債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微」な場合には認められません(民法541条但書)。
売買契約書においては、例えば、次のような規定が考えられます。
- 解除可能な事由(例:納期遅延○日以上、重大な不適合がある場合)
- 催告期間の設定(例:「履行遅滞が10日以上継続した場合」)
- 解除の方法(書面通知、内容証明郵便など)
- 解除後の精算方法や返金の期限
売買契約書では、相手が義務を履行しない場合に、どの程度の催告期間を要するかなどを定めるのが有益です。また、催告なしで解除できるケースも、契約書で具体化しておくのがお勧めです。
「契約の解除」の解説

手付解除に関する条項
手付とは、買主が売主に対して、契約締結時に支払う金銭であり、特に不動産の売買契約でよく利用されます。手付には、以下の3つの意味があります。
- 証約手付
売買契約の成立を証明するために交付される手付。 - 解約手付
契約を一方的に解除できる権利を留保するための手付。買主は支払った手付を放棄することで、売主は受領した手付の倍額を返還することで理由を問わず解除可能。 - 違約手付
債務不履行があった際、売主の違反に対しては「手付金の倍額の返還」、買主の違反に対しては「手付金の放棄」によって損害賠償があったものとみなす手付。
一般に、不動産取引などで授受される手付金は、「解約手付」として扱われます。
2020年の民法改正では、手付のルールについて、法律の条文が明確化されました。手付による解約は、改正前の民法が「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」と定めていたのに対し、従来の裁判実務でも、「解約をされる相手方(が契約の履行に着手するまで)」という意味に解釈されていました。改正後の民法では、この実務上の解釈が条文に反映され、「相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」と明記されました。
危険負担に関する条項
危険負担は、売買契約の目的物が引渡し前に滅失・損傷した場合に、代金支払い義務をどう扱うかを定めるルールです。例えば、不動産売買契約を締結後、引渡し前に地震で建物が倒壊した場合、買主は代金支払い義務を負うかどうかは、危険負担のルールによって決まります。
改正前の民法は、特定物売買の場合に「債権者主義」を採用し、債務者の帰責事由なく目的物の引渡し前に履行不能となった場合でも、反対債務の履行義務は消滅しないと考えられていました。しかし、このルールだと、「売買の目的物が入手できないのに代金を支払う必要がある」という不都合な事態が生じるおそれがあることが指摘されていました。
そのため、2020年の民法改正では、危険負担のルールが「債務者主義」に統一され、売買契約成立後、引渡し前に目的物が滅失した場合、買主は代金支払義務を負わないこととなりました。
また、これまで必ずしも明らかでなかった目的物の滅失などに関する危険の移転時期については「引渡し」の時点をもって移転することが明文化されました(民法567条1項)。なお、売買契約書においては、危険の移転時期となる「引渡し」の意味について具体化しておくのが有効です。
「危険負担の基本知識」の解説

売買契約に関するよくある質問
最後に、売買契約に関するよくある質問について解説しておきます。
口頭の売買契約でも訴えられる?
口頭の売買契約も、法律上有効なので、当事者の双方に権利義務が生じます。そのため、相手が義務を履行しなければ、口頭の売買契約に基づいて訴訟などの法的手続きで訴えることができます。
ただし、口頭の売買契約だと証拠が残りにくいため、契約内容を立証できないリスクがあります。裁判所の審理では、証拠のない事実は認定されないおそれがあるからです。口頭の売買契約となってしまった場合、後に争いとなる場合に備え、当事者間のメールのやり取りや当時のメモなどの記録を残しておくことが大切です。
売買契約はキャンセルできる?
売買契約のキャンセルは、法的には「解除」を意味します。
原則として、売買契約は合意で成立するので、一方当事者のみの意思でキャンセル(解除)することはできません。有効に成立した契約には拘束力があり、買主が「やっぱりいらない」、売主が「やっぱり売りたくない」と思っても、一方的な都合で解除はできません。
ただし、以下の場合には、解除が認められることがあります。
- 債務不履行(引渡し・支払い遅延など)がある。
- 契約書に定められた解除事由に該当する。
- クーリングオフ制度が適用される取引(訪問販売など)。
- 当事者間で解除の合意がある(合意解除)。
トラブルを回避するためにも、売買契約書に解除条項を定め、解除の条件や方法を事前に取り決めておくことが重要です。
ネット通販も売買契約になる?
ネット上の商品購入(ネット通販)も、売買契約に該当します。そのため、サイトやアプリ、SNS上での申込みと承諾があれば売買契約が成立し、売買に関する民法のルールが適用されます。
ネット通販では、特定商取引法によって消費者が保護される反面、購入者側に不利な利用規約、定型約款などを定めているサービスもあるので注意を要します。ネット通販では、購入ボタンを押すだけで契約が成立するケースが多く、売買契約が成立するハードルが低いので、申込内容や返品規定などをよく確認してから購入しなければなりません。
まとめ

今回は、売買契約について、民法改正を踏まえて解説しました。
売買契約は、財産(商品やサービス、動産や不動産など)の移転と代金の支払いという最も基本的な契約形態でありながら、法的には非常に重要な意味を持ちます。民法555条では、売買契約は「財産権の移転」と「代金」を合意するだけで成立しますが、その手軽さゆえにトラブルや誤解が生じやすいのも現実です。
民法は、目的物に瑕疵があったり、売買の当事者に違反があったりしたときの責任について、重要なルールを定めています。特に、2020年の民法改正で、危険負担や契約不適合責任のルールが大幅に見直されたため、売買契約を安全かつ円滑に結ぶためにもよく理解すべきです。
売買契約のリスクを軽減するには、適切な売買契約書を作成することが重要です。契約の場面で不安を感じるときは、ぜひ早めに弁護士に相談してください。
- 売買契約は、契約書がなくても、当事者の合意だけで有効に成立する
- 「物を買う」など身近な契約類型でも、民法上のルールに注意すべき
- 売買に関わる契約不適合責任、解除、危険負担などが2020年に改正された
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/


