賃貸借契約は、住居や事業用物件を借りる際など、生活に身近な契約です。
日常生活でもよく締結される賃貸借契約ですが、法律には細かいルールが定められています。2020年4月に施行された改正民法では、賃貸借契約に関するルールにも変更が加えられました。敷金の返還や原状回復の義務、賃貸人・賃借人の権利義務の整理など、法律上の定めが明確化され、貸主・借主の双方に影響を与える可能性があります。
今回は、賃貸借契約の基本と、改正民法による実務上の変更点について、弁護士が解説します。
- 賃貸借契約は、個人にとっても身近な契約だが、法律の遵守は徹底すべき
- 2020年民法改正では、これまでの判例法理や慣習が条文化された
- 原状回復義務や敷金返還ルールなどの法改正を賃貸借契約書に反映する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
賃貸借契約とは

賃貸借契約とは、当事者の一方が、ある物の使用及び収益を相手方にさせることを約束して、その相手方が賃料を支払うことと返還を約束することで効力を生じる契約です(民法601条)。
民法601条(賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
民法(e-Gov法令検索)
例えば、賃料を支払ってアパートや店舗を借りる建物賃貸借契約、建物を建てるために土地を借りる不動産賃貸借契約などが典型例です。
賃貸借契約を締結すると、貸主は売主に対して目的物の使用・収益を認める義務を負い、借主は貸主に対して使用の対価として賃料を支払う義務を負います。2020年4月施行の民法改正では、この定義に加え、契約終了時に、借主が目的物を返還する義務があることが明記されました。
まとめると、賃貸借契約における当事者の法律関係は、次の通りです。
【貸主(賃貸人)の義務】
- 目的物の引渡義務(民法601条)
契約締結後、賃貸人は借主に目的物を使用収益できる状態で引き渡す義務を負います。 - 使用収益に必要な修繕を行う義務(民法606条)
賃貸人は、契約期間中、借主が目的物を通常通り使用収益できるよう、維持管理する必要があり、賃貸人の負担で修繕をする義務を負います(例:建物の雨漏りの修理など)。 - 妨害排除義務(民法605条の4)
借主の使用が第三者により妨害された場合、賃貸人はこれを排除する義務を負います。具体的には、賃貸借契約において、第三者による占有の妨害や不動産の占有があった場合、賃借人は賃貸人に妨害の停止や返還を請求できます。 - 契約終了後の敷金返還義務(民法622条の2)
借主による賃貸物の返還完了後に、未払債務などを控除した上で敷金を返還する義務があります。
【借主(賃借人)の義務】
- 賃料支払義務(民法601条)
賃借人は、契約で定められた期日に、使用の対価として賃料を支払う義務を負います。 - 転貸・譲渡の制限(民法612条)
貸主の承諾なく、借主は目的物を第三者に転貸したり賃借権を譲渡したりすることはできません。無断転貸があれば、賃貸人は契約を解除できます。 - 善良なる管理者としての注意義務(民法616条)
借主は目的物の性質や契約の趣旨に従って使用・管理する必要があります。重大な汚損や用途違反があると、契約違反となります。 - 原状回復義務(民法621条)
契約終了時には、借主は目的物を原状に復して返還する義務があります。ただし、通常損耗や経年劣化については原状回復義務の対象外となります。
2020年4月施行の民法改正による賃貸借契約の変更点

次に、2020年4月施行の改正民法における、賃貸借契約の変更点を解説します。
改正民法による賃貸借契約の変更点は、敷金や原状回復のルールなど、従来は明文の規定がなく、判例や慣習に頼っていた部分について、実務の慣行を法律上明文化し、取引の予見可能性を高めることを目的としています。これにより、借主・貸主間や保証人との間で生じやすいトラブルのルールを明確にし、未然に防ぐことが期待されています。
賃貸借契約の存続期間の延長(20年→50年)
改正後の民法604条により、賃貸借契約の存続期間の上限が、従来の20年から50年に引き上げられました。この改正には、建物所有目的以外の土地賃貸借で、20年を超える長期利用のニーズがあったことが背景にあります(例:ゴルフ場の敷地、工場用地、大規模商業施設など)。
改正後の賃貸借契約の存続期間のルールは、次の通りです。
- 最長50年の賃貸借契約を有効に締結することができる。
- それ以上の期間を設定した場合、超過分は無効となる。
- 更新時にも、更新日から起算して50年以内に収める必要がある。
改正によって、土地の長期賃貸が可能となり、柔軟な契約が可能となった反面、超長期契約の場合には、賃料改定条項や中途解約条項の設計を慎重に行わなければならなくなりました。なお、借地借家法上、建物賃貸借については賃貸期間の上限が撤廃されていますし(借地借家法29条2項)、建物所有目的の土地賃貸借契約にも借地借家法が適用され、賃貸期間の上限はありません(借地借家法2条1号、同法3条但書)。
「民法改正(2020年4月施行)」の解説
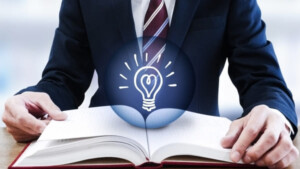
賃貸人の地位の移転に関する規定
民法605条の2では、賃貸された不動産の所有権が第三者に譲渡された場合、賃借権が第三者に対抗できるときは、賃貸人の地位も新所有者に移転する旨が明記されました。借主から見れば、賃貸人が新所有者に変更されることとなります。
ただし、新所有者が登記を備えていないと、賃借人に対して地位の移転を主張することができません。また、譲渡人と譲受人の間で、賃貸人の地位を譲渡人に留保する旨の合意がある場合は、賃貸人の地位は新所有者に移転しません。
この条項は、従来の判例や慣習を踏襲したものですが、敷金や未清算の原状回復費用の支払い義務についても、賃貸人の地位と共に新所有者に承継される点に注意しなければなりません。
賃貸人の修繕義務と賃借人の修繕権
賃貸人は、目的物について賃借人の責任で修繕が必要になった場合を除き、修繕義務を負います。賃貸人は、賃料を得ている反面、使用収益が可能な状態を維持しなければならないからです。もっとも、改正前の民法では賃借人の責任で修繕が必要になった場合について必ずしも明確ではなかったことから、改正民法ではルールが明確化されました(民法606条、607条の2)。
修繕に関するルールを整理すると、次のようになります。
【賃貸人による修繕】
- 賃貸人は、賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、賃借人の責任で修繕が必要となった場合は修繕義務を負わない。 - 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は拒否できない。
【賃借人による修繕】
- 賃借人は、次の場合には自ら修繕できる。
- 修繕が必要なことを賃貸人に通知してから、または賃貸人が修繕が必要なことを知ってから相当期間が経過しても賃貸人が修繕をしないとき
- 急迫の事情があるときは、次の場合は、自ら修繕できます。
- 賃借人が修繕費用を支出した場合、次のように賃貸人に償還請求できる。
- 必要費(賃貸物を使用収益するのに適した状態にするために修繕した費用)は、直ちに償還を請求できる。
- 有益費(賃貸物の価値を増加させる費用)は、賃貸借契約の終了時に、価値の増加が現存していれば支出された金額または増加額のいずれかの償還を請求できる。
賃貸物の一部滅失・使用不能時の賃料減額
民法611条1項は、借主の責任によらずに、賃貸物の一部が滅失その他の事由により使用収益できなくなったとき、使用不能となった割合に応じて賃料が当然に減額されることを定めています。
改正前の民法は、一部滅失した場合に限って、賃料の減額を請求できることとされていましたが、滅失以外の理由でも使用収益できる価値が下がる可能性があること、請求によらず賃料を減額すべきことなど、借主保護の観点から改正法のような定めとなりました。
例えば、一部滅失などによる使用不能は、次のようなケースで問題になります。
- 地震や火災で建物の一部が損壊して使えなくなった。
- 上階からの漏水で一部の部屋が使用不能になった。
- アスベストが検出されて使用禁止となった。
また、賃貸借契約の期間中に、賃借物の一部が滅失し、残りの部分では契約の目的が達成できない場合には、借主は賃貸借契約を解除できます(民法611条2項)。
原状回復義務の明確化
原状回復とは、賃貸借契約の終了時、賃借人が賃貸物を元の状態に戻すことです。
改正後の民法は、次の通り、賃借人に原状回復義務があることが明確化されると共に、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」について、原状回復義務の対象外であることが明記されました。
民法621条(賃借人の原状回復義務)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
民法(e-Gov法令検索)
これは、従来の判例や「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省)で示されていた実務運用の基準を条文化したものです。例えば、次のようにして原状回復の負担が決定されます。
【借主が負担しないとされた例】
- 日焼けによるクロスの変色
- 冷蔵庫・家具の設置による床のへこみ
- 年数経過による設備の劣化(給湯器、換気扇など)
【借主が負担すべき例】
- ペット飼育による臭気・傷
- 喫煙による壁紙のヤニ汚れ
- 故意・過失による設備破損(壁に穴を開けたなど)
本条文は任意規定なので、当事者間の契約によって原状回復義務の範囲を拡大することができます(例:退去時に「クリーニング費用」を払う旨の特約)。賃借人としては、賃貸借契約書の条項によって過大な義務を負わないか注意を要します。賃借人にあまりにも不利な原状回復を強いる契約は、消費者契約法10条などに違反し、無効になる可能性があります。
判例でも、通常損耗に関する費用について賃借人に負担させる特約自体は有効ですが、賃借人が原状回復義務を負う範囲、内容が契約書の条項自体に具体的に明記されていることが必要であると判断されています(最高裁平成17年12月16日判決)。
敷金の定義と返還ルールの明文化
敷金とは、賃料債務などの担保のため、賃借人が賃貸人に預け入れる金銭です。
従来の民法には、敷金の定義や敷金返還請求権の発生根拠となる規定がなかったところ、改正によって次の通り明文化されました(名目が「保証金」「預り金」であっても、実質が賃料担保であれば敷金と扱われます)。
民法622条の2
1. 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。2. 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
具体的には、敷金の返還は、以下の流れに従って行われます。
- 賃貸借契約の終了
- 賃借人による明渡しの完了
- 未払賃料や損害賠償などを敷金から控除し、差額を賃借人に返還
賃貸借契約書に、返還方法や控除項目を明記する必要があり、「一切返還しない」といった特約は無効となる可能性が高いです。
また、敷金からあらかじめ契約書に定めた額を差し引く特約(敷引き契約)は、改正民法でも一律無効なわけではありませんが、判例では消費者契約法10条に違反する可能性が示唆されていることに注意を要します(最高裁平成23年3月24日判決)。
個人根保証人の保護
民法465条の2は、個人が根保証契約(一定の範囲の不特定の債務を保証する契約)をする場合、保証人の保護のため、保証債務の極度額(上限額)を明記しなければ無効となることを定めています。賃貸人の保証人は、賃貸借契約から生じる様々な債務を包括して保証する立場となるため、まさに個人根保証契約の典型例です。
したがって、賃貸借契約の連帯保証では、保証債務の極度額(上限額)の定めが必要です。また、債権者(賃貸人)は、保証人から請求があった場合、主債務の履行状況(賃借人の賃料の支払い状況など)を遅滞なく開示する必要があります。
また、民法465条の10は、事業用目的の賃貸借では、借主は連帯保証人となる人に対し、財産や収支の状況、その他の債務の情報などを事前に提供する義務があります。
「保証契約の基本」の解説

賃貸借契約書の見直しポイント
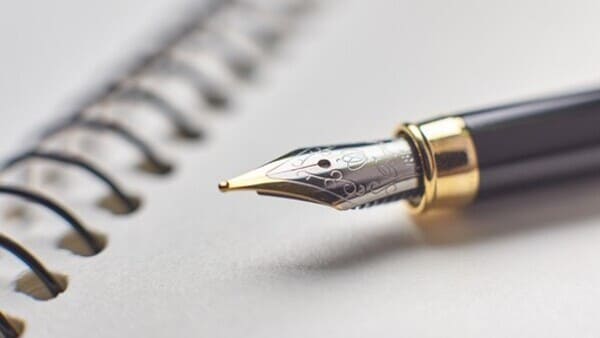
最後に、賃貸借契約書の見直しのポイントについて解説します。
本解説の通り、2020年の民法改正によって賃貸借契約に関する法律のルールに変更がありました。これに伴って、従来の契約書のひな形や書式を放置しておくと、法令違反になったり、紛争を招きやすくなったりするリスクがあります。
改正民法に対応した条項に修正する
まず、現在の契約書ひな形を見直し、改正民法に対応した条項に修正しましょう。既存の契約もまた、更新時に新しい書式へ変更すべきです。
前章の改正点を参考に、契約書の次のような点を修正してください。
契約期間条項
民法改正によって存続期間の上限が20年から50年に延長されたことに伴い、長期の賃貸借を予定する契約では、50年を上限とした期間設定に修正することが可能です。
賃貸人の地位移転に関する条項
民法改正によって賃貸人の地位が、対抗要件を備えた所有権移転に伴って移転することが明記されたことから、賃貸人が不動産を売却した際の敷金の扱い、費用の清算などについて契約書に記載しておくのが良いでしょう。
原状回復義務に関する条項
原状回復について、民法621条に従い、「通常の使用及び収益による損耗・経年変化を除く」と明記しておくのがよいでしょう。また、予想されるキズや汚れについては、どのようなものが対象内・対象外なのか、例示して説明すると親切です。
なお、原状回復義務の民法のルールは任意規定なので、特約によって範囲を変更できますが、通常損耗も借主負担とすることは消費者契約法違反となるリスクがあります。
敷金に関する条項
敷金の返還義務について、民法622条の2に基づき、契約終了後にどのような債務が控除されるのか、返還の流れなどを明記しておいてください。また、名称にかかわらず、担保目的の金銭の預託が民法の「敷金」と評価される可能性があるので、「権利金」「預り金」などの名称でも、それが法律上の「敷金」の性質を有するのであれば、その旨契約書にも記載しておくべきです。
連帯保証人に関する条項
民法465条の2により、個人保証には極度額の設定が必要となります。
したがって、個人を保証人とする場合には「極度額:◯◯万円」などと具体的な上限金額を契約書に明記します。
弁護士に契約書チェックを依頼する
契約書の書式・ひな形を作成したら、社内に共有し、マニュアル化しておきましょう。
この際、事業用の賃貸借契約書など、複雑なケースほど、弁護士にリーガルチェックを依頼するのがお勧めです。特に、こちらが事業者で、賃貸借契約の相手方が消費者の場合には、借主に一方的に不利益を課す条項については消費者契約法10条によって無効となるリスクがあります。
例えば、「通常損耗や経年劣化も一律に原状回復の対象とする」「敷金は一切返還しない」などといった判例や慣習に反する定めは、無効となる可能性が高いです。
まとめ

今回は、賃貸借契約に関する法律知識を解説しました。
2020年4月の民法改正によって、賃貸借契約に関する法律上のルールも変更されました。敷金や原状回復など、紛争が生じがちな点が明文化され、契約当事者間の認識のズレを予防することが期待されています。一方で、改正に対応していない古い契約書を流用し続けると、思わぬ法的リスクを抱えるおそれがあります。
また、実務上は、民法だけでなく借地借家法、消費者契約法などの特別法の理解も欠かせません。賃貸人、賃借人の立場を問わず、契約の内容を定期的に見直し、最新の法令に沿った内容となるよう、賃貸借契約書をチェックしておかなければなりません。
不明点やトラブルの兆候を発見したら、早めに弁護士に相談し、アドバイスを受けるのがお勧めです。契約をめぐる紛争を避けるには、正しい知識と早めの準備が不可欠です。
- 賃貸借契約は、個人にとっても身近な契約だが、法律の遵守は徹底すべき
- 2020年民法改正では、これまでの判例法理や慣習が条文化された
- 原状回復義務や敷金返還ルールなどの法改正を賃貸借契約書に反映する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
民法の改正は、契約や取引、債権債務など、生活や企業経営に密接に関わります。改正の内容を正しく把握しなければ、思わぬトラブルを招くおそれもあります。
適切な権利行使をするためにも、民法改正に関する解説記事を通じて、最新のルールを理解しておいてください。


