贈与契約は、無償の財産移転を内容とする契約です。家族や友人など近しい関係の間でよく行われるほか、近年では、相続対策や事業承継の一環としても贈与契約が用いられます。
「無償」であるがゆえに軽視されがちな贈与契約ですが、契約内容に不備があるとトラブルに発展するケースも少なくありません。将来の紛争を回避するには、対価を伴わない贈与でも、必ず書面化し、贈与契約書を締結することがお勧めです。
なお、2020年4月1日に施行された民法改正では、債権法の扱いに大幅な変更があり、贈与契約書の書式にも影響を与えます。
今回は、贈与契約の基本的な考え方と、贈与契約書の作成方法、締結時の注意点について弁護士が解説します。
- 贈与契約は、書面契約とすることで証拠を確保すべき
- 贈与契約は、無償であるがゆえに軽くみられがちだが、リスクを伴う
- 特に、負担付贈与の受贈者は、リスクが大きいため慎重に検討する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
贈与契約とは

はじめに、贈与契約の基本的な考え方について解説します。
贈与契約の法的な意味
贈与契約とは、一方(贈与者)が、自分の財産を無償で他方(受贈者)に譲渡するという意思表示と、受贈者がこれに応じる意思表示をすることで成立する契約です。例えば、「祖父から孫への財産の贈与」などが身近な例です。
民法549条は、贈与契約について次のように定めています。
民法549条(贈与)
当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる。
民法(e-Gov法令検索)
贈与契約の特徴は、対象となる財産を「無償で与える」という点です(無償性)。無償契約なので対価の授受はなく、受贈者は金銭その他の対価を支払う義務を負いません。これに対して、贈与者には財産を移転させる義務が生じ、受贈者には財産を引き受ける権利が生じます。
贈与契約は、贈与者と受贈者の意思表示が合致することで成立する「諾成契約」です。口頭でも成立しますが、実務上は、紛争防止のため、書面での契約として証拠化するのがお勧めです。贈与契約を証明する文書が、贈与契約書です。
贈与契約と他の契約の違い
贈与契約は、他の契約形態と比較すると、次のような違いがあります。
売買契約との違い
売買契約では、財産の移転に対して代金の支払いが発生しますが、贈与契約は無償なので対価は存在しません。このことは契約の解除や取消しのルールに影響します。例えば、口頭で成立した贈与契約は、履行前であれば一方的に取り消すことができます。
使用貸借契約との違い
財産を無償で使用させる契約が、使用貸借契約ですが、贈与契約と異なり、財産の返還義務が生じます。これに対して、贈与契約では所有権が確定的に移転し、返還は不要です。
贈与契約の種類
贈与契約は、契約の内容や条件によって、いくつかの種類に分類できます。
- 定期贈与(民法552条)
一定期間にわたり定期的に財産を贈与する契約(例:毎年一定額を贈与するケース)。税務上、1年間の贈与額が110万円以内の場合には贈与税が非課税ですが、贈与総額が一括で評価されるリスクがあるため、計画的に進めなければなりません。 - 負担付贈与(民法553条)
無償で財産を譲渡するだけでなく、受贈者に一定の義務(負担)を課す贈与(例:介護義務を課して自宅不動産を子に贈与するケース)。受贈者が負担を履行しないときは、贈与者は契約解除や返還を求めることができます。 - 死因贈与(民法554条)
贈与者の死亡を条件に効力を生じる贈与契約(例:「私が死亡したら○○を贈与する」と合意するケース)。死因贈与は当事者間の合意に基づく契約ですが、遺贈の規定が準用されます。
なお、贈与は、口頭での合意でも成立し、口頭契約だと履行前であれば解除が可能です。ただ、証拠が不十分となってトラブルの可能性が高まるので、書面契約とするのがお勧めです。書面による贈与であれば、一方的な解除は認められません。
贈与契約書の書き方

次に、贈与契約書の作成方法について解説します。適切な贈与契約書を締結することは、後の法律・税務上のトラブルを回避する役に立ちます。
贈与契約書に書くべき内容
贈与契約書を作成する際、記載しておくべき基本的な条項は、次の通りです。
契約日・当事者の情報
贈与契約書上の「日付」は、「実際の贈与日」とする例が多いです。
あわせて、贈与者・受贈者それぞれの氏名と住所を記載し、氏名の末尾に押印を行います(認印も可能ですが、実印を押して印鑑証明を添付することで、証拠としての価値が上がります)。
贈与の対象となる財産
次に、贈与の対象となる財産についても明記します。他の財産と区別して特定できるよう、次のような情報を正確に記載します。
- 金銭を贈与する場合
贈与する金額と支払い方法、支払い期限 - 不動産を贈与する場合
所在地、地番、地目、地積、建物の詳細(種類、構造、床面積)などの物件情報を、登記事項証明書に基づいて正確に記載します。
贈与の方法と引渡しの条件
贈与をどのような方法で行うか(手渡しか、銀行振込か、不動産の場合には所有権移転登記手続きの手順など)、履行期限と条件を具体的に贈与契約書に定めます。
あわせて、費用の負担者を明記しておくと、トラブル回避に役立ちます。特に、不動産を贈与する場合、登録免許税や司法書士費用など、税金や手数料がかかります。
その他の合意事項
その他に特別な合意をしたときは、その旨も記載します。例えば、贈与契約書では次のような特約事項を定める例があります。
- 書面によらない贈与の場合
解除規定の適用除外を明記しておく。 - 負担付贈与の場合
受贈者に課す負担の内容や履行期限、違反した場合の制裁など。 - 紛争解決方法
協議条項や専属的合意管轄裁判所など。
贈与契約書の書式・ひな形
以上の必要項目をもとに、贈与契約書の書式と文例を紹介します。以下では、よくある例として、個人間の金銭贈与、親子間の不動産贈与、企業間の株式贈与の3パターンを取り上げます。
個人間の金銭贈与契約書の例
贈与契約書
贈与者◯◯◯◯(以下「甲」という)と、受贈者◯◯◯◯(以下「乙」という)は、以下の通り、贈与契約を締結した。
第1条(贈与の意思表示)
甲は乙に対し、金〇〇万円を無償で贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
第2条(引渡し方法及び時期)
甲は、前条の現金を20XX年XX月XX日までに、乙の指定する金融機関口座へ振込送金するものとする(振込手数料は甲負担)。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲・乙各自が記名押印の上、各1通を保有する。
【作成日・署名押印】
親子間で不動産を生前贈与する契約書の例
贈与契約書
贈与者◯◯◯◯(以下「甲」という)と、受贈者◯◯◯◯(以下「乙」という)は、下記不動産(以下「本件不動産」という)の贈与について、以下の通り合意した。
第1条(贈与の意思表示)
甲は乙に対し、本件不動産を無償で贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
【本件不動産】
(1)土地
所在:東京都□□区□□町□□丁目□□番□□号
地目:宅地/地積:〇〇〇.〇㎡
(2)建物
所在:同上
種類:居宅/構造:木造、2階建/床面積:〇〇〇.〇㎡
第2条(引渡し及び登記手続き)
甲は、20XX年XX月XX日までに、本件不動産の現状引渡し及び所有権移転登記手続きを完了するものとする。
第3条(費用負担)
登録免許税、司法書士報酬、その他本件不動産に関する登記手続き費用は、原則として乙の負担とする。
第4条(税金その他)
固定資産税その他公租公課は、引渡し日を基準に日割りで精算し、引渡し日前の分は甲、以降の分は乙が負担する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲・乙各自が記名押印の上、各1通を保有する。
【作成日・署名押印】
固定資産税等の税金の負担についても明記します。通常は、引渡日を境に分割することが多いです。不動産贈与契約書では、物件の詳細な記載が不可欠なので、登記事項証明書の内容に基づき、土地や建物の情報について正確に転記してください。
引渡し日と所有権移転登記の期限を明確に定めることは、後の登記手続きでもトラブルを防ぐことに繋がります。
法人の株式を贈与する契約書の例
贈与契約書
贈与者◯◯(以下「甲」という)と、受贈者◯◯(以下「乙」という)は、下記株式(以下「本件株式」という)の贈与について、以下の通り合意した。
第1条(贈与の意思表示)
甲は乙に対し、乙の普通株式◯◯株を無償で贈与する。
第2条(本件株式の内容)
本件株式は、乙の定款に基づく普通株式であり、株券発行の有無にかかわらず、当該会社の議決権、配当請求権その他株主としての一切の権利が付随するものとする。なお、発行済株式総数、株主名簿記載事項等の詳細は、別紙「株式明細書」に記載する。
第3条(株式の移転方法及び手続き)
甲は、乙に対し、本件株式の贈与に伴う株式名義書換手続を速やかに実施し、完了証明書又は登記事項証明書を交付するものとする。株式の名義書換に必要な書類、手数料その他一切の費用は、原則として乙の負担とする。
第4条(表明保証)
乙は、本契約締結に際し、株式譲渡に必要な内部承認その他の手続きを完了していることを表明する。甲は、本件株式が第三者の権利行使の対象となっていないこと、及び、株式譲渡について法令及び定款の制限が存在しないことを表明する。
第4条(税金その他)
固定資産税その他公租公課は、引渡し日を基準に日割りで精算し、引渡し日前の分は甲、以降の分は乙が負担する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲・乙各自が記名押印の上、各1通を保有する。
【作成日・署名押印】
贈与契約に関する民法改正のポイント
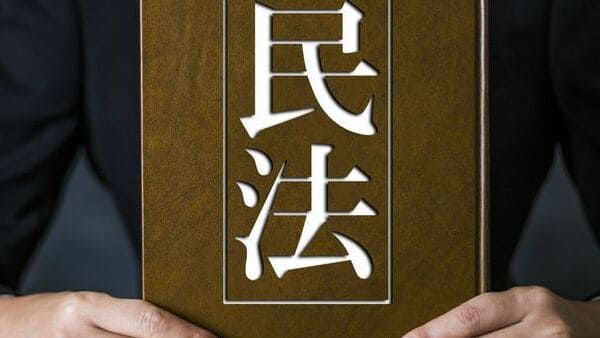
2020年4月施行の民法改正では、贈与契約に関連する規定についても見直しが行われました。以下では、改正のポイントと、実務上の影響について解説します。
目的物の変更(他人物贈与の明確化)
民法549条は、改正前は「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」となっていたところ、2020年施行の民法改正で「自己の財産」から「ある財産」に、条文上の表現が変更されました。
改正前の条文だと、贈与者自身の財産を対象とする場合に限ると誤解されるおそれがありましたが、改正後は、他人の所有物も贈与の対象となることが明確化されました。改正前も、実務上は他人物贈与が許容されていたため、運用面に大きな変更はないものの、他人物の贈与契約を結ぶときは、特に、贈与者の義務(他人から買い取って贈与する義務など)や違反に対する責任などを明記する必要があります。
「民法改正(2020年4月施行)」の解説
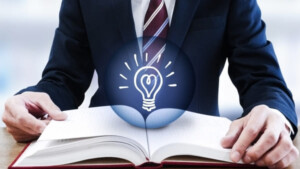
解除権の用語の統一
書面によらない贈与は、履行の終了まで、各当事者は自由に解除することができます。このことを定めた民法550条は、改正前は「撤回」と定められていましたが、2020年施行の民法改正により「解除」という用語に統一されました。
書面での贈与契約は、原則として一方的な解除が認められないため、口頭契約の解除権について明確なルールが示され、贈与者・受贈者の権利義務が把握しやすくなりました。
瑕疵担保責任の見直し
無償の贈与は、「贈与の目的として特定した時の状態」で引き渡せばよく、目的物の結果について、責任を負わないのが基本とされています(民法551条)。贈与の無償性からして、隠れた瑕疵(キズやへこみなど)があっても、贈与者がその責任を負うことはありません。
ただし、負担付贈与の場合、受贈者には負担が課されるため、贈与者にも、その負担の限度において売買契約の売主と同様の担保責任が生じます。
この点、2020年施行の民法改正により、「貸担保責任(法定責任)」は、「契約不適合責任(契約責任)」という考え方に改められました。これにより、負担付贈与の贈与者の責任もまた、契約で定められることとなり、ますます贈与契約書への明記が重要となっています。
贈与契約に関する法律上の注意点

次に、贈与契約を締結する際の、法律上の注意点について解説します。
贈与契約は無償が原則なので、贈与契約書を作成する場合であっても、贈与の意思表示が軽率に行われ、思わぬトラブルに巻き込まれるケースがあります。贈与者・受贈者のいずれにとっても、法的リスクの少ない適切な贈与契約書を作成することが重要です。
贈与契約が無効や取消しとなるケース
贈与契約は、贈与者と受贈者の合意によって成立しますが、以下の場合は例外的に、無効や取消しとなるケースがあります。
公序良俗違反による無効
贈与の目的が社会秩序や公序良俗に違反する場合、贈与契約は無効となります(民法90条)。例えば、犯罪の報酬としての贈与や、あまりにも不合理な条件が付された契約は、無効となるリスクがあります。
錯誤による取消し
契約の重要な部分についての認識に誤りがあった場合には、錯誤を理由として取り消すことができます(民法95条)。なお、契約の重要な部分であると言うためには、贈与契約書に記載しておくことが非常に大切なポイントとなります。
詐欺・強迫による取消し
詐欺や強迫によって贈与の意思表示をしたときは、契約を取り消すことができます(民法96条)。例えば、受贈者が嘘を付いて、贈与者が誤認して贈与の意思表示をしたケース、受贈者が不当な圧力や脅迫によって無理やり贈与をさせたケースなどがこれに該当します。この場合、贈与契約が取り消された結果、既に譲渡された財産の返還を求めることができます。
贈与税の留意点
贈与税は、贈与契約に基づいて財産を受け取った受贈者に課されます。したがって、受贈者となったら贈与税の納税義務を負います。
ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があり、それ以下の贈与には贈与税がかかりません。具体的には、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税が課税されます(国税庁HP「No.4402 贈与税がかかる場合」)
なお、同一の当事者間で定期的に同額の贈与を繰り返すと、贈与総額が一括して評価されて課税されるおそれがあるので注意を要します。
贈与契約書のチェックを弁護士に依頼する
口頭契約による贈与は、一方的な解除が認められやすいので、必ず書面により契約内容を明確化しておく必要があります。このとき、贈与者・受贈者のいずれにとっても、契約書が将来のリスクを回避する重要な武器となるため、弁護士にリーガルチェックを依頼するのがお勧めです。
特に、贈与額が多額となる場合や、負担付贈与の場合には、契約の内容に不備がないか、自身に不利な条項がないか、慎重にチェックしなければなりません。
贈与契約についてよくある質問
最後に、贈与契約についてのよくある質問に回答しておきます。
贈与契約書を作成するメリットは?
贈与契約書を作成することで、口約束で済ますのではなく、文章によって具体的な内容を記録し、証拠を残すことができます。これにより、後の取り消しや紛争のリスクを大幅に軽減できます。
夫婦間などの身近なケースも、トラブルが起こらないとは限りません。口頭の贈与だと、合意のタイミングや内容の確認が困難なので、贈与契約書の必要性は高いです。
なお、暦年贈与のように毎年計画的に行う贈与では、税務上も、契約内容を明確化するために贈与契約書が必須となります。
贈与契約書に収入印紙は必要?
贈与契約書のうち、不動産の贈与以外については印紙税がかかりません。
これに対し、不動産の贈与の場合には、一律200円の収入印紙が必要となります。ただし、「◯◯円の建物を贈与する」というように金額を記載すると、その額に応じた印紙代がかかってしまうので注意を要します。
未成年者との贈与契約は可能?
未成年者(満18歳未満)との贈与契約は、原則として法定代理人(通常は親権者)の同意が必要です。年齢によって未成年者の判断能力には制限があるので、法定代理人の同意のない意思表示は、後に取り消しとなるリスクがあります。
したがって、子供が受贈者となる場合(祖父母から孫への贈与など)は、親権者など法定代理人の同意を得たことを贈与契約書に明記すべきです。
贈与契約書の作成の流れは?
贈与契約書の作成の流れは、まずは必要書類を準備し、双方の情報や贈与の内容、引き渡し方法などについて話し合いを行います。合意後はその内容を贈与契約書にし、両当事者が署名押印を行います。複数ページに渡る場合は、各ページに割印することで文書の改ざんを防ぐことができます。
完成した契約書は、各自で適切に保管します。より信頼性を高めるために公証役場で公正証書の形式にすることもお勧めです。
まとめ

今回は「贈与契約」について、契約のポイントや注意点を解説しました。
財産を無償で譲渡することを内容とする「贈与契約」と、それを文書化する「贈与契約書」は、2020年4月1日施行の改正民法を踏まえてチェックポイントを理解する必要があります。
贈与契約は、書面がない場合には容易に解除されるリスクがあります。そのため、企業間のビジネス上の贈与や、家族間の相続対策としての贈与など、重要な贈与契約であるほど、適切な贈与契約書を作成することが非常に重要です。特に、贈与を受ける側にとっては、契約が簡単に解除されないようにすると共に、契約締結後に予期しない負担が生じないよう注意が必要です。
改正民法に対応していない贈与契約書を使用している方など、契約書にお悩みの場合、適切な契約内容になっているかを確認するため、弁護士にご相談ください。
- 贈与契約は、書面契約とすることで証拠を確保すべき
- 贈与契約は、無償であるがゆえに軽くみられがちだが、リスクを伴う
- 特に、負担付贈与の受贈者は、リスクが大きいため慎重に検討する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
民法の改正は、契約や取引、債権債務など、生活や企業経営に密接に関わります。改正の内容を正しく把握しなければ、思わぬトラブルを招くおそれもあります。
適切な権利行使をするためにも、民法改正に関する解説記事を通じて、最新のルールを理解しておいてください。


