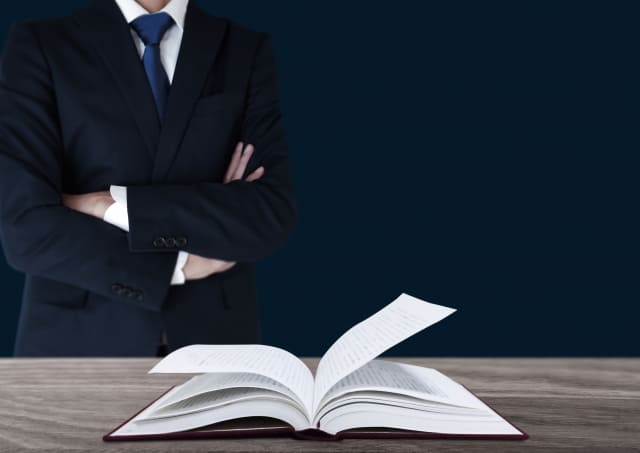実務では、意思表示のミスや誤解がトラブルに発展するケースがあります。
意思表示の瑕疵のうち、ミスや誤解によるものが「錯誤」です。契約をするかどうか、どのような内容の契約とするか、といった前提に関する重要な認識の違いがあるとき、「錯誤」を理由として意思表示を取り消すことができます(民法95条)。
2020年4月1日に施行された民法改正では、錯誤について重要な変更がされました。具体的には、これまで判例で確立された法理が、法律にも明文化されました。
今回は、錯誤の意味や要件について、具体的な事例を交えて説明します。特に、民法改正によって契約実務にどのような影響が及ぶのか、トラブルを未然に防ぐためにどうすればよいのかについて、弁護士が解説します。
- 意思表示と内心のズレが、錯誤に該当するかどうかの決め手となる
- 錯誤がある場合、取り消すことができるが、善意無過失の第三者は保護される
- 錯誤が生じないよう、契約締結前の入念な確認でトラブルを回避すべき
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
錯誤とは(民法95条)

錯誤とは、契約などの法律行為において、当事者が誤った認識を持ち、その結果、意思表示と内心に不一致が生じてしまった状態を指します。
錯誤が生じると、実際に表示された意思と、当事者の真意との間にズレが生じるので、そのような誤認のある意思表示が有効かどうかが問題となります。民法95条は、次の通り、錯誤に基づく意思表示は「取り消すことができる」と定めています。
民法95条(錯誤)
1. 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤2. 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3. 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。4. 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
民法(e-Gov法令検索)
例えば、次のケースは「錯誤」が議論される具体例です。
- 価格の表示に誤記があった契約
売買契約で「1,000万円」で売却するつもりが「100万円」と契約書に記載してしまったケース、「1万円」で売るつもりが「1万ドル」と記載してしまったケースなど。 - 取引の対象を取り違えた契約
本来は「土地A」を購入したかったのに、物件名を誤認して書類上「土地B」を購入する契約を締結してしまったケースなど。 - 契約動機に誤解があった場合
「将来、新駅の開発計画があるので価値が上がる」と期待して不動産を購入したが、後日噂に過ぎないことが判明したケース(動機の錯誤であり、後述の通り、それが相手にも表明された場合に限って取消可能)。 - 商品の品質に関する思い違い
新商品が「自分の期待した性能を備えている」と誤信して契約したケースなど。
錯誤の種類には、大きく分けて次の2種類があります。
表示の錯誤
当事者が内心で意図した内容と、実際の意思表示が一致しない状態が「表示の錯誤」です(例:契約書の記載ミス、言い間違いなど)。表示の錯誤の場合、外から見た意思表示そのものが誤っているため、取消しが可能です。
動機の錯誤
契約を締結する動機や基礎となる事情について誤った認識を持っていた状態が「動機の錯誤」です(例:不動産の将来価値の誤信や、商品の品質についての誤った期待など)。動機の錯誤は、相手方に表示されていた場合に限って取消しの理由になります。
錯誤の要件と効果について
次に、錯誤の要件と効果について解説します。
つまり、どのようなケースで錯誤があったといえるのか、そして、錯誤が成立するとどのような効果があるのか、という点についてです。
錯誤が成立するための条件は?
第一に、錯誤が成立するために、満たすべき条件について解説します。
法律行為の要素の錯誤であること
錯誤が認められるには、誤認が、契約の目的や条件、価格、対象物といった「法律行為の要素」に関わるものである必要があります(要素の錯誤)。一方で、契約の根幹に関わる事項の誤認でない場合には、錯誤は成立しません。
契約締結の動機となった事情に誤認がある場合、その動機を相手に伝えていて、契約内容の一部として認識されていた場合に限って、取り消しを主張することができます。
錯誤が「重要なもの」であること
錯誤が重大なものであることも要件となります。
些細な誤解や、訂正が可能な誤記などでは、錯誤は成立しません。少なくとも、その誤認がなければ当事者が契約を締結しなかったであろうと言える必要があります。つまり、誤認が、契約内容に大きな影響を及ぼすものでなければなりません。
このことは、主観・客観の両面から判断されます。
- 主観的に、「錯誤がなければ契約しなかった」という内心の意思があったこと。
- 客観的に、「法律行為の目的及び取引上の社会通念」に照らして重要なものと評価できること。
表意者に重大な過失がないこと
表意者が誤認に陥った原因について、重大な過失があると、取り消しを主張できません。明らかな不注意や調査不足といった事情は、「重大な過失」と評価されるおそれがあります。
例えば、契約前に簡単に確認すれば誤りに気付けたにもかかわらず、確認を怠って契約をしてしまった場合、重大な過失による錯誤といえます。ただし、相手方が錯誤があったことを知っていた、または重大な過失があった場合や、両当事者が同一の錯誤に陥っていた場合は、この制限は適用されず、取消しが認められます。
錯誤がある場合の法的効果
次に、要件を満たし、錯誤があるといえる場合、法的効果は「取り消し」です。
民法95条は、錯誤による意思表示を取消し可能と定めます。取り消された意思表示は、最初から無かったものとみなされるので、既に履行された部分は、原状回復を求めることができます。
取り消しが認められるとしても、第三者が善意無過失で権利を取得した場合は、その第三者に対しては取り消しの効果を対抗できません。これは、取引の安全と信用を守り、第三者を保護するための仕組みです。「善意でかつ過失がない」というのは、表意者が錯誤に陥っていることを知らず、知らなかったことについて過失がない状態を指します。
錯誤と他の意思表示の瑕疵の違い

意思表示の瑕疵には、錯誤と似た考え方として、他に「詐欺」「強迫」があります。いずれも、当事者の意思決定の自由を損なう理由となりますが、法律上の扱いが異なります。
- 詐欺(民法96条)
他人に騙され、誤信して意思表示をすることを指し、取り消しが可能です。錯誤が「本人の勘違い」であるのに対し、詐欺は「相手の故意による欺き」である点が異なります。相手の欺罔行為という違法があるので、表意者に過失があっても取り消しが制限されず、また、加害者への損害賠償請求も可能です。 - 強迫(民法96条)
相手に脅されて意思表示をすることを指し、取り消し得る行為です。相手の不法な圧力によって、「誤って」というよりは「脅威によって意思表示が歪められた」状態を指すので、救済する必要性が高いケースです。
共通点は、錯誤・詐欺・強迫はいずれも「意思表示の瑕疵」と呼ばれ、被害を受けた当事者が「取り消し」によって遡って契約をなかったことにできる点です。
ただし、錯誤は表意者に重大な過失があると原則取消し不可という制限があるのに対して、詐欺・強迫にはそのような制限がありません。錯誤は「不注意」「勘違い」という側面があるので、自らにも落ち度がある場合には救済されないと考えられているからです。
民法改正による「錯誤」の変更点
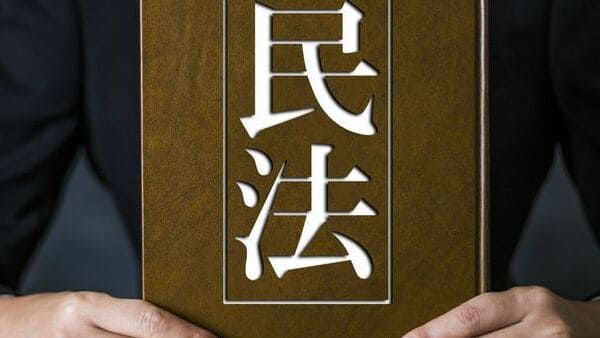
最後に、2020年4月1日に施行された民法改正における「錯誤」の変更点を解説します。改正に応じて、契約書のひな型を修正することが、適切なリスク管理のために非常に重要です。
取消権の効果の変更
錯誤があった場合の効果について、改正前は「無効」とされ、表意者の意思に関わらず自動的に効力を失うものとされていました。これに対し、改正後は「取消」とされ、表意者が自ら取り消しを求めない限り、契約は有効に存続することとなりました。
この変更により、実務上は次の影響があります。
「民法改正(2020年4月施行)」の解説
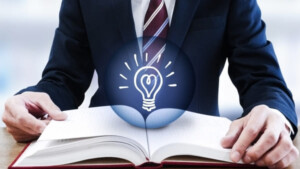
動機の錯誤に関する明文化と要件の整理
動機の錯誤について、改正前は法律に規定がなく、判例で「動機が明示され、契約の基礎となっている限り認められる」という判断がされてきました。改正後は、この点が民法に明文化されました。具体的には、「前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる」(民法95条2項)とされました。
これにより、動機の錯誤の扱いが明らかにされ、かつ、その基準も明確となったので、実務上も紛争を防止する効果が高まったということができます。
表意者の重大な過失に関する例外規定
表意者が錯誤について重大な過失がある場合、取消権が制限されますが、具体的な基準は裁判例に委ねられていました。改正後の民法95条3項では、相手方の悪意や重過失、または双方が同一の錯誤に陥っていた場合に、表意者に重大な過失があっても取消しが認められる例外が明記され、救済の余地が残されることとなりました。
第三者保護の明確化
錯誤の効果が「無効」から「取消」に変更されたことにより、権利を取得した第三者が、「取り消されるかどうか」によって不安定な地位に置かれかねない状況が生まれます。そのため、善意無過失の第三者が権利を取得した場合には、保護すべきという考え方が、法律に明文化されました。
改正民法では「第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」として、第三者の保護を図っています(民法95条4項)。
まとめ

今回は、錯誤に関する基本的な法律知識について解説しました。
錯誤は、意思表示における「勘違い」です。意思表示を取り消すことができ、契約がなかったことになるという重大な効果を生むため、契約実務において重要な考え方です。特に、2020年4月1日に施行された民法改正で「効果」について大幅な変更がされた点に注意すべきです。
契約締結の当事者はいずれにとっても、錯誤の生じるリスクがないかどうか、よく注意して進めるようにしてください。万が一、錯誤があってトラブルに発展したとき、適切な契約書が締結されているかどうかが、トラブル解決の鍵となります。
トラブルを未然に防ぐには、弁護士に契約書のチェックを依頼するのがお勧めです。
- 意思表示と内心のズレが、錯誤に該当するかどうかの決め手となる
- 錯誤がある場合、取り消すことができるが、善意無過失の第三者は保護される
- 錯誤が生じないよう、契約締結前の入念な確認でトラブルを回避すべき
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
民法の改正は、契約や取引、債権債務など、生活や企業経営に密接に関わります。改正の内容を正しく把握しなければ、思わぬトラブルを招くおそれもあります。
適切な権利行使をするためにも、民法改正に関する解説記事を通じて、最新のルールを理解しておいてください。