会社が労働者を雇用するとき、採用面接などで選考を行います。選考の結果、応募者が基準に達しない場合に採用を拒否することは、会社側の判断として広く認められています。
このように、会社には労働契約を締結するかどうかを自由に決める権利、つまり「採用の自由」が認められており、特定の思想・信条を有する応募者の採用を拒否したとしても、直ちに違法となるわけではありません。一般社会では思想・信条による区別は「差別」として許されませんが、採用にはそれだけの特殊性があるのです。
今回は、会社側に認められる「採用の自由」や「調査の自由」、それらが制限されるケースなど、採用場面における労働問題について解説します。
- 会社には「採用の自由」があり、誰を採用するかは企業側の自由
- 採用の自由の前提として、採用時の調査も自由であるのが原則
- 男女差別、障害者や組合員の差別などは、採用の自由があっても認められない
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
採用の自由とは
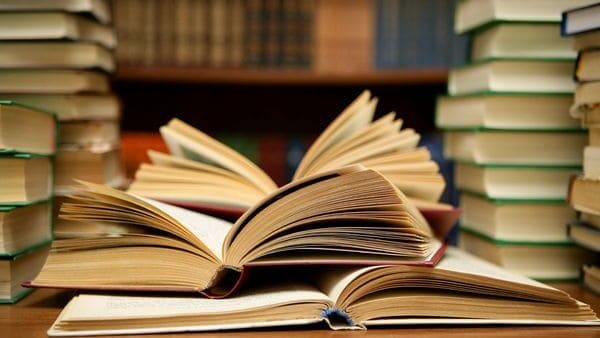
採用の自由とは、企業(使用者)が労働者を雇用するにあたって、誰と雇用契約を結ぶかを自由に決定できる権利のことです。「契約自由の原則」に基づくものであり、雇用契約の「入口」において企業側に一定の裁量があることを示しています。
採用の自由の具体的な内容
「採用の自由」の具体的な内容には、次のものが含まれます。
採用人数を決定する自由
複数の求職者がいるとき、そのうち何名を採用するか(あるいは全員を不採用とするか)について、企業の自由な裁量に委ねられています。
選択の自由
複数の求職者がいるとき、どのような基準で、どの人と雇用契約を締結するかについて、企業側が決めることができます。
契約締結の自由
各求職者と会社との間で、雇用契約を締結するかどうかについても、企業が最終的に判断することができます。
調査の自由
以上の採用段階の選択について、企業側が有効に行使するために、考慮要素となる事情について自由に調べることができます。具体的には、面接時の質問、採用調査などの方法で実施されます。
採用は自由だが、解雇は制限される
企業には、雇用契約の「入口」である採用時は、「採用の自由」による広い裁量が認められていますが、雇用契約の「出口」である契約終了時には、厳しい法的制限があります。
特に、会社から一方的に雇用契約を解約することを意味する「解雇」は、労働者の不利益が大きいため、日本の労働法では厳しく制限されています。具体的には「解雇権濫用法理」により、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められない限り、「不当解雇」となります。
会社側としては、一度入社させると、一方的に解雇することは容易ではありません。そのため、後のトラブルを避けるためにも、「採用の自由」の認められる選考段階において、慎重かつ十分な判断を行うことが非常に重要です。
採用の自由の法的根拠
採用の自由は、憲法、民法、労働基準法といった複数の法律に基づいて、法的に認められた企業の権利です。それぞれの法的根拠について、以下に詳しく解説します。
憲法上の根拠
日本国憲法では、国民に「経済的自由権」が保障されています。具体的には、憲法22条、憲法29条に、財産権の行使、営業、その他広く経済活動の自由が定められています。
憲法22条
1. 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2. 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
憲法(e-Gov法令検索)
その反面、憲法19条では、思想・信条の自由が保障されており、思想・信条の自由は侵してはならず、これらの理由で差別してはなりません。そのため、労働問題の場面でも、思想・信条を理由として労働条件について差別するのは違法です。
このように、採用選考の場面では、企業側の「経済的自由」と応募者側の「思想・信条の自由」という、憲法上の二つの権利が対立することとなり、これらの調整が必要となります。その調整の結果、裁判例によって示されたのが「採用の自由」という結論なのです。
民法上の根拠
民法には「契約自由の原則」という考え方があります。これは、契約を結ぶかどうか、誰とどのような契約をするかといった点は、契約当事者の自由な意思に委ねられるという原則です。「採用の自由」は、この「契約自由の原則」を雇用契約という特殊な場面にあてはめた考え方です。
つまり、雇用契約もまた「契約」の一種なので、企業は「誰を雇うか」「どのような労働条件とするか」を自由に決めることができます。雇用契約は労使の合意によるものなので、会社側においても、契約締結を拒絶したり、選択したりする権利があるというわけです。
労働基準法上の根拠
民法は、対等な当事者の法律関係を前提としますが、労使関係のように力関係に差があるとき、弱い立場の保護が必要となります。弱い立場である労働者の保護を目的とするのが、労働基準法をはじめとする労働法です。
労働基準法には、採用の自由を直接定める規定はありませんが、労働条件に関する差別的待遇を禁止する規定があります。
労働基準法3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
ただし、この規定はあくまでも「雇用契約締結後」に適用されるもので、「採用段階」において、誰を雇い入れるかという判断自体を制限するものではありません。つまり、企業は入社後に応募者の思想・信条などを理由に不利益な扱いをすることは許されませんが、そもそも誰を採用するかという判断は、企業の裁量に委ねられ、「採用の自由」があるというわけです。
終身雇用の慣習が長く続いていた日本社会で、企業経営の円滑な運営の妨げとならないようにするため、入社時の企業側の自由を広く認めています。
「調査の自由」により、採用時の質問が許される

「採用の自由」により、採用時の判断は企業側の裁量が認められると解説しました。しかし、選考のプロセスで、面接だけで適性を見抜くのは非常に難しいです。そのため、採用の自由を実効的に行使するには、採否の基準となる事項について質問し、回答を求める自由が必要です。
採用選考において企業側が労働者に質問をし、回答を求める自由が許されていることを「調査の自由」といいます。
採用時に企業が行う主な調査方法
採用の自由と調査の自由が認められることから、企業側としては、採用時に十分な調査をすることが可能です。
次章の通り、虚偽申告が解雇理由となることの裏返しとして、「調査を十分に行わなかったために、重要な事実が判明していなかった」とすれば、それは採用段階の企業側の責任であり、後から発覚した事情に基づいて解雇するのは難しくなります。したがって、採用面接では、後から発覚した場合には「経歴詐称」として解雇したいと考えるような重要な事情があるなら、必ず質問しておくのが重要なポイントです。
また、面接だけでは聞きづらい内容も、採否の判断にとって重要な事項であれば、以下のような複数の手段を活用して聴取しておくべきです。
- 履歴書・職務経歴書・エントリーシートの提出と書面審査
- SPIなどの適性検査や試験の実施
- 任意回答によるアンケート調査の実施
- 面接時における直接・間接の質問
- 調査会社を通じた素行調査、行動調査
調査結果を証拠に残すことが重要
採用選考において調査を行ったとき、その回答を証拠化しておくのが大切なポイントです。後に労働紛争が労働審判・訴訟など争いに発展したとき、証拠による立証が重要だからです。
応募者が、入社を希望するあまり虚偽の申告をするケースも考えられます。しかし、企業が「嘘があった」ことを立証できれば、後に「経歴詐称」として解雇できる余地を残すことができます。「真実はわからないから」といって質問すらしないと、後から判明しても、会社から出て行ってもらうことが難しくなってしまいます。
採用面接における口頭のやり取りは、後から「言った、言わない」の水掛け論になりがちです。証拠を残すときは、次の点に注意してください。
- 採用面接は、質問者と記録係の2名体制で行い、議事録やメモを残す。
- 面接を担当した社員が、上司宛に選考内容を報告書として記録する。
- 内定候補者については、面接内容を録音し、保存しておく。
虚偽申告は解雇理由になり得る
採用の自由と調査の自由が企業側に認められているため、応募者が採用判断に関わる重要な事情について虚偽の申告をしていた場合、それは入社後の解雇理由となる可能性があります。
解雇には「解雇権濫用法理」による制限がありますが、虚偽申告の内容が重要であれば、不当解雇とはなりません。解雇理由となり得る典型的な虚偽申告には、次のものがあります。
- 前科や前歴の隠蔽
- 業務に必要な資格や能力に関する虚偽申告
- 学歴を偽る行為(学歴詐称)
調査の自由が認められている趣旨からして、労働者側が虚偽の事実を伝えたり、事実を隠したり、回答を拒否したりすることが許されてしまっては、採用の自由が無意味になってしまいます。むしろ、採用の自由を適切に行使するためには、採否決定の重要な要素となると考える事情があるのであれば、思想・信条にかかわる過去の行動についても積極的に調査を行うことが必要です。
採用の自由を認めた裁判例

採用の自由は、労使それぞれに認められた憲法上の重要な権利の調整であり、かつ、民法上の契約の自由のあらわれである、法的な根拠を備えたものであることを解説しました。重要な最高裁判例でも、採用の自由が認められたものがあります。
企業側に「採用の自由」を認めた最高裁判例が「三菱樹脂事件判決(最高裁昭和48年12月12日判決)」です。本裁判例は次のように述べ、採用の自由を認めています。
憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、22条、29条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想・信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。
三菱樹脂事件(最高裁昭和48年12月12日判決)
本裁判例では、労働基準法3条が、思想・信条による労働条件の差別を禁じているのは「雇用後」のことであり、「雇入れ時の規制」ではないことに言及しています。採用の自由があることから、会社が思想・信条などを理由に雇い入れを拒否したとしても、労働者側から損害賠償請求・慰謝料請求を受けることもありません。
また、採用の自由とあわせて、調査の自由についても次のように判示しています。
企業が雇用の自由を有し、思想、信条を理由として雇入れを拒んでもこれを目して違法とすることができない以上、企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。
三菱樹脂事件(最高裁昭和48年12月12日判決)
むしろ、採用時の調査で知れた事情であれば、調査が不十分で採用時には知ることができず後から判明したとしても、解雇理由とするのが難しくなってしまうおそれもあります。採用時に知り得る事情なら、その際に知って採用を拒否できたはずです。一旦採用したのなら、その事情は採否を決定づけるほどに重大ではないと労働者が期待してしまうためです。
なお、三菱樹脂事件の最高裁判決に対し、控訴審判決では、採用の自由について限定的に判断し、企業側敗訴となっています。
控訴審判決は、労働者側が秘匿していた事実が、政治的な思想・信条であったことから、これを理由とする差別が平等原則(憲法14条)、均等待遇(労働基準法3条)に違反すると判断しました。そして、採用選考で、政治的な思想・信条について申告を求めることが公序良俗に反し、秘匿による不利益を労働者に課すことはできないとし、採用の拒否は無効だと判断しました。
このように、企業の採用の自由よりも、労働者の思想・信条の自由を優先し、企業側の敗訴と判断した控訴審と比較して、最高裁判断のポイントを理解しておいてください。
採用の自由の限界

採用の自由にもまた限界があります。というのも、採用の自由は、憲法上認められた重要な自由について、労使の調整の結果として認められたものです。そのため、労働者の権利・自由を重視すべき場面では、逆に、企業の採用の自由が制限されるべきと考えられるからです。
採用の自由が法的に制限される場合があるのは、次のような特定の理由での採用拒否が違法となることからも明らかです。
- 男女雇用機会均等法による制限
事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与える必要がある(男女雇用機会均等法5条)。男女差別は明確に禁止される。ただし、均等な機会を与えればよいのであり、「男女を同数採用すべき」という意味ではない。 - 障害者雇用促進法による制限
会社は、障害者を積極的に雇用する努力義務を負う。また、一定の雇用率に達する障害者の雇用を義務として、これを満たさない場合は、障害者雇用納付金が必要となる。 - 労働組合法による制限
労働組合法7条1項では、労働者が労働組合に加入せず、もしくは労働組合から脱退することを雇用条件とするなどは禁止される。組合員であることを理由として採用を拒否することは、労働組合法に定められた「不当労働行為」という違法行為となる。 - 雇用対策法による制限
雇用対策法10条で、募集・採用において、年齢に関わりなく均等な機会を付与すべき義務がある。ただし、期間の定めのない労働者を定年年齢を下回ることを条件として募集・採用する場合、新規学卒者を長期雇用のために募集・採用する場合、特定職種において特定年齢層の労働者が少ない場合にその年齢層の者を補うための募集・採用である場合などは例外となる。 - 「労働者の個人情報保護に関する行動指針」(厚生労働省)による制限
使用者の採用選考時における行動指針。使用者は原則として、労働者の人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、思想、信条及び信仰といった個人情報を収集してはならない。 - 「HIV指針」(厚生労働省)による制限
HIV(いわゆる「エイズ」)にり患した患者の差別を禁止し、HIV感染のみを理由とした採用拒否、労働条件に関する差別、不利益な取扱いを禁止する。裁判例でも、本人の同意なくHIV抗体検査やB型肝炎ウイルス検査を行ったケースで、企業側の違法性を認めたものあり。
採用の自由の限度は、これらの法律に禁止された違反行為以外でも問題となることがあり、不当な差別は、労働審判・裁判などの法的手続きで、後に違法と判断されるリスクがあります。
重要なことは、労働者のある性質や事実、行為に着目して採用を拒否するときに、その「業務上の必要性」があるかどうかを立ち止まってよく検討することです。その採用拒否の理由が、純粋に業務上の必要性があるものであり、このまま採用して入社させると業務に大きな支障が生じることが説明できれば、後日紛争になったとしても十分戦える材料があることを意味します。
まとめ

今回は、「採用の自由」が会社にどの程度認められるかについて解説しました。
採用の自由が問題になる選考の場面において、会社が労働者に対して行う質問には、非常にデリケートなものが多いです。会社側が遠慮してしまった結果、後になって「会社の期待していた人物ではなかった」と判明すると、争いとなるおそれがあります。
会社側に採用の自由が認められ、これに基づく調査の自由があることをきちんと理解し、採用面接段階において適切な対応をすることが、後の労働紛争を未然に防止するのに有効です。
入社後の問題社員対応や解雇などだけでなく、入社時の対応も、弁護士のアドバイスを聞くことが有益です。労務管理にお悩みの方は、ぜひ一度弁護士に相談してください。
- 会社には「採用の自由」があり、誰を採用するかは企業側の自由
- 採用の自由の前提として、採用時の調査も自由であるのが原則
- 男女差別、障害者や組合員の差別などは、採用の自由があっても認められない
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/


