寄託契約とは、財産の一時的な保管や管理を目的として結ばれる契約で、わかりやすく言うと「物を預ける契約」のことです。寄託契約を証明する契約書が「寄託契約書」です。寄託契約は、民法改正で「要物契約」から「諾成契約」に変更された点がポイントです。
今回は、寄託契約の基本的な考え方から、寄託契約書を作成する際のポイント、そして、2020年4月1日に施行された民法改正が寄託契約に与える影響について解説します。
- 2020年の民法改正で、寄託契約は合意のみで成立することとなった
- 寄託契約書に基本的な条項を明文化し、証拠を確保して争いを回避する
- 解除や再寄託などの条件を交渉することで、リスク管理を徹底すべき
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
寄託契約とは

はじめに、寄託契約の意味について解説します。
寄託契約とは、当事者の一方(寄託者)が特定の物品(寄託物)を、他方(受寄者)に一定期間、保管・管理することを委託し、受寄者がこれを承諾することで成立する契約です。わかりやすく言うと「物を預ける契約」であり、受寄者は預かった物品について、返還の義務を負います。
民法657条は、寄託契約について次のように定めています。
民法657条(寄託)
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法(e-Gov法令検索)
寄託契約の典型例として、倉庫で荷物を預かってもらう際に締結する「倉庫寄託契約」、トランクルームの契約などがあります。
寄託契約の種類
寄託契約には、次のような種類があります。
有償寄託
有償寄託とは、受寄者が寄託物の保管・管理に対する報酬を受け取る契約です。
有償寄託だと、受寄者には善管注意義務が課され、寄託物の安全かつ適切な保管が求められます。また、受領前に解除した際の費用や損害賠償請求など、金銭面の条件について寄託契約書で事前に取り決めておくことが重要となります。
無償寄託
無償寄託とは、報酬の支払いを伴わない寄託契約です。
無償寄託は、個人間や親族間など、善意の委託関係において利用されるケースが多いです。無償の場合、受寄者の注意義務は「自己の財産に対するのと同一の注意」とされ、有償の場合の「善管注意義務」よりも軽いものとなります。
ただし、書面化されていないと受寄者の解除が容易になるなど、後にトラブルの原因となるため、たとえ無償でも必ず寄託契約書を作成すべきです。
消費寄託
消費寄託とは、受寄者が寄託物を消費(使用)することが認められる契約です。受寄者が消費(使用)した場合、後に同種・同等・同数量の物を返還しなければなりません。消費寄託の代表例が、銀行の預金契約です(銀行は、預かった金銭を運用し、預金者に同額を返還します)。
消費寄託は特に、返還の方法や時期、返還時の寄託物の評価方法などが争いになりやすいので、事前に寄託契約書で具体的に定めておくべきです。
混合寄託
混合寄託とは、複数の寄託者から預けられた寄託物を、受寄者が混合して保管する契約です。例えば、倉庫業者が複数の企業から同一規格の商品を一括して保管するケースです。
混合寄託の場合、返還時には、各寄託者が預けた数量に応じた割合で返還され、不足分については損害賠償によって補填されます。寄託契約書には、返還方法、部分滅失時の按分方法などを詳細に定める必要があります。
寄託契約の成立要件と当事者の義務
寄託契約は、従来は、寄託物の引き渡しを成立要件とする「要物契約」でしたが、2020年4月1日施行の改正民法により、合意のみで成立する「諾成契約」となりました。これにより、「物品を預ける」という合意が成立すれば、寄託物の受け渡し前でも契約の効力が生じます。
寄託契約を締結すると、受寄者と寄託者はそれぞれ、次の義務を負います。
受寄者の義務
受寄者は、寄託契約に基づいて寄託物を適切に保管し、契約に定めた条件に従って返還する義務を負います。特に、有償寄託では「善管注意義務」を負います。
また、寄託物を契約以外の目的で使用したり、無断で第三者に再寄託したりすることは原則として禁止されます。
寄託者の義務
寄託者は、寄託物を受寄者に引き渡す義務を負います。有償寄託の場合は、受寄者に対して契約で定められた保管料や報酬を支払う義務を伴います。
寄託契約と他の契約の違い
寄託契約は、「貸し借り」という点で賃貸借契約に似ていますが、「保管」を目的とする点が大きな特徴です。保管のための「業務」や「作業」が生じる点で、委任契約にも似ています。
賃貸借・使用貸借との違い
賃貸借契約は、物を有償で貸し出す契約であり、賃借人には使用する権利が与えられます。また、使用貸借は無償で物を使用させる契約です。いずれも、受領した者が自ら使用することが前提となります。
一方、寄託契約は、受寄者は物の保管・管理をするのみで、使用する権利はありません。
委任契約や業務委託契約との違い
委任契約や業務委託契約は、主に法律行為や事務処理の遂行の依頼を内容としています。一方、寄託契約は、物品の保管・管理に焦点が当てられています。
寄託者は、寄託物を受寄者に引き渡す義務を負います。有償寄託の場合は、受寄者に対して契約で定められた保管料や報酬を支払う義務を伴います。
寄託契約書の作成時の注意点

寄託契約書とは、寄託契約の内容や権利義務について記した文書です。
寄託契約は、口頭での合意でも成立しますが、後日のトラブルを避けるために、書面化して合意内容を証拠に残しておくことをお勧めします。無償寄託は特に、書面がないと、寄託物を受け取るまで受寄者が解除できるため、書面化することは双方のリスク軽減となります。
寄託契約書のテンプレート
寄託契約書のテンプレート・ひな形を紹介します。
寄託契約書
【寄託者の氏名】(以下「甲」という)と【受寄者の氏名】(以下「乙」という)とは、両者の間で締結された寄託契約の内容について、以下の通り合意した。
第1条(寄託)
甲は、別紙「寄託物目録」に記載した物品(以下「寄託物」という)を乙に寄託した。
第2条(保管方法及び保管場所)
乙は、本契約に基づき、寄託物を指定の場所(◯◯市◯◯町所在の倉庫内)にて、善良なる管理者の注意義務に従って保管する。なお、乙は、甲の書面による事前承諾なしに寄託物の保管場所を変更してはならない。
第3条(保管期間)
1. 本契約に基づく保管期間は、20XX年XX月XX日から1年間とする。
2. 乙は保管期間終了又は甲の返還請求があった場合、◯日以内に寄託物を甲の指定する場所に返還する。
第4条(寄託料)
甲は乙に対し、寄託料として月額◯◯万円を支払う。料金の支払いは、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の口座に振込送金する方法による(振込手数料は甲負担)。
第5条(損害賠償)
乙は、故意又は重過失によって寄託物に損傷、滅失を生じさせた場合、甲に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、天災その他の乙の責に帰さない事由による場合はこの限りでない。
第6条(譲渡及び再寄託の禁止)
乙は、甲の書面による承諾なく、寄託物を第三者に譲渡し、又は再寄託してはならない。やむを得ない事由によって再寄託する場合、再寄託者もまた乙と同等の義務を負う。
第7条(契約解除)
1. 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、相手方に催告を行うことなく、本契約を解除することができる。
① 相手方が本契約に定める義務に著しく違反した場合
② 甲又は乙の財務状態が著しく悪化し、信用不安が生じた場合
③ その他、契約履行が困難と認められる事由が生じた場合
2. 本条に基づき契約が解除となった場合、甲乙いずれか責のある方は、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第8条(紛争解決)
1. 本契約に定めのない事項については、甲及び乙が誠実に協議して決定する。
2. 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙が署名押印の上、各1通を保有すものとする。
【作成日・署名押印】
なお、上記の例文はあくまでサンプルなので、寄託契約の内容や状況に合わせて、追記・修正をする必要があります。
寄託契約書に記載すべき内容
次に、寄託契約書のテンプレートをもとに、記載すべき内容とその注意点を解説します。
寄託
寄託契約において、受寄者は預かった物品の返還義務を負うので、「何を預けたのか」、寄託物を具体的に特定しなければなりません。寄託物の種類によりますが、品名や数量、品質、シリアル番号などで、他と区別できるように明確に特定することが重要です。複数の物品を寄託する場合、「別紙物品目録記載の物品」などと特定する方法も有効です。
混合寄託や消費寄託といった特殊な寄託の場合には、その旨を明記してください。
保管方法と保管場所
受寄者は、有償寄託の場合「善管注意義務」を負います。これに加えて、寄託物の特性によって保管方法の注意点があるなら、必ず寄託契約書に明記しましょう。例えば、次のような記載をする例があります。
- 保管場所の温度や湿度
- 入出庫時の注意点
- 火災保険や地震保険の有無
保管場所を特定する場合、住所や施設名などを寄託契約書に具体的に記載し、変更できる場合の条件についても定めておきます。
保管期間
寄託期間の開始日と終了日、返還時期や方法や返還場所について定めます。
また、返還時の手続きとして、点検や検品、目録との照合の方法や、一部が滅失・毀損していた場合の対処法などについても寄託契約書に定める例もあります。返還が遅れた際の遅延損害金や違約金も合わせて規定すると、紛争防止に繋がります。
寄託料
有償寄託の場合には、保管料や寄託料、報酬などの金額、支払い方法と期限を決めておきます。無償寄託の場合でも、報酬が発生しない旨を寄託契約書に明記しておくことが重要です。
損害賠償
寄託物に滅失や毀損が生じた場合の責任として、損害賠償を定めるケースがあります。
受寄者側では責任を限定するため、損害賠償額の上限を寄託料までとするよう交渉するのがよいでしょう。一方、寄託者は、被害回復を図るため、違約金の定めを入れるよう交渉すべきです。
譲渡及び再寄託の禁止
受寄者が、寄託物を無断で第三者に譲渡したり再寄託したりすることは禁止すべきです(もしくは、事前に書面による同意を要すると定めるのがお勧めです)。合わせて、違反時の措置(契約解除や損害賠償)についても定めましょう。
後述の通り、「やむを得ない事由」があると再寄託が許される場合があるので、そのような事態に備え、再寄託できる場合を限定したり、再寄託者の義務を定めたりすることも重要なポイントです。
契約解除
双方が契約を中途解除できる条件を具体的に定めておきます。
例えば、重大な契約違反、支払停止、破産などがよく列挙されます。改正民法によって、寄託物の受領前に寄託者側から解除できる規定が新設されたため、その場合の賠償義務や解除手続きを明記するのもよいでしょう。
その他の条項
その他に、一般的な契約条項として、反社会的勢力排除条項、準拠法、協議条項、専属的合意管轄裁判所といった基本的な規定も盛り込んでおいてください。
寄託契約書の印紙について
寄託契約書について、「金銭又は有価証券の寄託」に該当する場合には印紙税の課税対象となり、収入印紙が必要となります。これに対し、物品の寄託契約については課税されません(国税庁HP「寄託の意義」)。
民法改正のポイントと寄託契約への影響
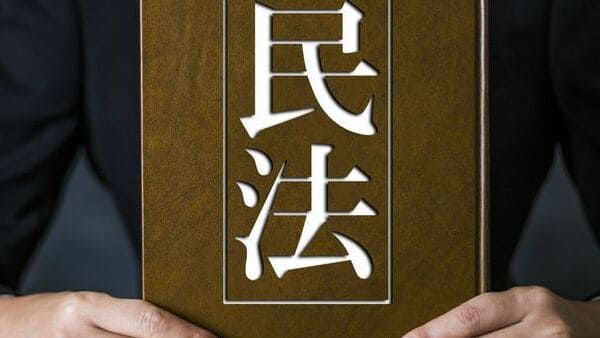
最後に、2020年4月1日に施行された民法改正における寄託契約の改正ポイントと、その実務上の影響について解説します。
改正の背景と目的
従来、寄託契約は、寄託物の引渡しがないと成立しない「要物契約」と解釈されるなど、実務の慣行と乖離している点が問題視されていました。倉庫業や物流業では、実際には物品の受け渡し前に契約を締結するケースが一般的だったので、法的にも柔軟な対応が求められていました。
2020年4月1日施行の改正民法は、このような実態に合わせ、契約の成立要件や解除権、再寄託などの規定を明確化することで、取引の安全性と透明性を高めることを目的としています。
「民法改正(2020年4月施行)」の解説
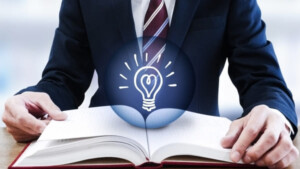
寄託契約に関する民法改正のポイント
寄託契約について、民法改正で変更された主な点は、次の通りです。
諾成契約への変更
改正前、寄託契約は、実際に寄託物が引き渡されることで初めて成立する「要物契約」とされていましたが、改正により、当事者の合意のみで成立する「諾成契約」となりました。実務上も、倉庫寄託契約を中心として、諾成的な寄託契約が広く浸透しており、取引の実情に合わせた改正です。
合意のみで契約成立となるので、寄託契約の成立時期は前倒しされます。そのため、寄託物の受け渡し前から法的拘束力が発生することに備え、特に受寄者は、受領前の解除権や損害賠償リスクに備え、寄託契約書の規定に一層の注意が必要となります。
解除権の明確化
寄託が「諾成契約」となったことに伴い、解除権の定めが明確化され、寄託者と受寄者のリスク分担が明らかにされました。
- 寄託者の解除権
寄託者は、寄託物の交付前であれば契約を解除できます(有償・無償いずれも)。ただし、解除によって受寄者に損害が生じたときは賠償義務があります(受寄者が受領前に準備した費用や、得られるはずだった報酬など)。 - 受寄者の解除権
受寄者は、書面によらない無償寄託であれば、寄託物を受領するまでは解除できます。また、有償寄託や書面による無償寄託でも、約束した時期に寄託物が引き渡されなかった場合、催告しても引き渡されないときは解除できることとなっています。これらの解除権は、受寄者の法的地位の安定を目的とした規定です。
寄託者・受寄者双方に解除権が認められたため、契約成立後も状況の変化に柔軟に対応できる反面、解除権行使やその際の損害賠償に関する取り決めについて、寄託契約書の作り方がより一層重要となります。
再寄託の緩和
再寄託とは、受寄者が寄託物を第三者(再受寄者)に保管させることです。
従来、再委託には寄託者の承諾を要するのが原則でしたが、寄託者の承諾を得るのが困難なケースも多くありました。委任契約は「やむを得ない事由」があれば復委任が認められることとの整合性から、「やむを得ない事由」を要件として、寄託者の承諾のない再寄託が認められるようになりました。ただし、「やむを得ない事由」とは、受寄者が保管することができない事情だけでは足りず、寄託者の承諾を得ることが困難な事情も必要とされます。
再寄託した場合の再受寄者は、寄託者に対して、受寄者と同一の権利及び義務を負うため、寄託物の返還義務を負う一方で、報酬や費用の支払を求めることができます。
「やむを得ない事由」による再寄託が認められるリスクへの対応として、寄託者側では、寄託契約書に「再寄託禁止」の条項を盛り込んだり、「やむを得ない事由」を限定的に列挙したりといった対策を講じることが大切です。
一方、再寄託を要する受寄者側でも、後の紛争を回避するために、再寄託ができる範囲について明確化しておくべきです。
第三者の権利主張への対応
改正民法では、第三者が寄託物の所有権などを主張した場合の受寄者の対応が明確化されました。受寄者はまず、寄託者に速やかに通知し、寄託者の指示がない限り、第三者への引渡しを行わないことが規定されています。
この措置により、受寄者が第三者とのトラブルに巻き込まれるリスクを軽減し、寄託者の権利保護が図られています。
混合寄託と消費寄託
改正民法では、混合寄託、消費寄託という特殊な寄託のルールが明文化されました。
【混合寄託について】
混合寄託は、寄託を受けた代替性のある寄託物を、他の寄託者から寄託された種類及び品質が同一の寄託物と混合して保管し、寄託されたものと同数量のものを返還する契約です。
寄託物の一部が滅失したとき、寄託者は、総寄託物に対する自己の寄託した物の割合に応じた数量の返還を求めることができるに留まり、寄託した物との数量の差は損害賠償によって補填することになる点が特徴です。
混合寄託契約では、後日の紛争防止のため、寄託契約書において混合寄託の方法によると明記して、寄託物をどのように混合して保管するのか、具体的に記載することが大切です。
【消費寄託について】
消費寄託は、受寄者が契約により、寄託物を消費することができる契約です。実務上は、銀行預金等の金融取引の他に、金属や原油などについて消費寄託が利用されます。
寄託物の消費が認められる場合、従来は消費貸借の規定が準用されていましたが、改正により寄託契約の規定が適用されるよう整理されました。ただし、金融機関の預金契約においては依然として消費貸借の規定が準用されるなど、区分ごとに取り扱いが異なるため、契約書上で明確に区別することが求められます。
まとめ

今回は、寄託契約の特徴と、寄託契約書の注意点について解説しました。
寄託契約は、「物を預ける契約」ですが、2020年4月1日施行の民法改正によって従来の「要物契約」から「諾成契約」へと変更されました。これに伴って契約実務でも、寄託物の受け渡し前から法的効力が発生し、寄託者・受寄者の双方に解除権が認められるなど、大幅な変更がされています。
寄託契約を締結する際にも、これらの法改正のポイントを押さえ、リスク管理を徹底した契約書を作成しなければなりません。契約交渉を十分に行い、締結前のリーガルチェックや締結後の柔軟な見直しも必要となるので、弁護士のサポートを受けるのが有益です。
- 2020年の民法改正で、寄託契約は合意のみで成立することとなった
- 寄託契約書に基本的な条項を明文化し、証拠を確保して争いを回避する
- 解除や再寄託などの条件を交渉することで、リスク管理を徹底すべき
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
民法の改正は、契約や取引、債権債務など、生活や企業経営に密接に関わります。改正の内容を正しく把握しなければ、思わぬトラブルを招くおそれもあります。
適切な権利行使をするためにも、民法改正に関する解説記事を通じて、最新のルールを理解しておいてください。


