借金する理由は人それぞれですが、計画通りに一括返済できないなら分割払いに変更してもらう必要が生じます。借入時には返済できる見込みでも、事業の失敗や突然の解雇、予期せぬ事故や病気による出費などで、予定していた収入が得られず返済が難しくなるケースもあります。
自己破産を避け、どうにか返済しようと試みるなら、一括ではなく分割での支払いに変更してもらうよう交渉することが重要です。分割払いを認めてもらうには債権者の承諾を得なければならず、この際は「分割弁済契約書」や「合意書」「覚書」などの書面を作成します。
ただし、債権者にもメリットある条件でなければ、分割払いの提案は受け入れてもらえないでしょう。また、分割払いの交渉は「債務の承認」を意味し、時効が中断されるため、注意して進めなければ不利な状況に陥るおそれがあります。
今回は、借金の返済が難しい方に向けて、分割払いの交渉方法と「分割弁済契約書」の重要性について、弁護士が解説します。
- 借金を一括で返せないとき、分割弁済にするには妥当な分割案を提案すべき
- 分割払いについて債権者の承諾を得られたら、必ず分割弁済契約書を作成する
- 借金の分割返済を続ける際、自己破産と比べて合理的な選択かどうか検討する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
借金を分割払いにする方法

借金を返済することができず、やむを得ず分割払いにしてもらいたいときには、債務者の承諾を得る必要があります。分割払いの交渉をするときには、次の手順で進めるようにしてください。
支払い計画を作成する
まず、債権者に対して、債務者であるあなたが約束できる支払い計画を提示することが必要です。そのため、交渉を開始する前に、支払い計画を作成しておかなければなりません。
分割払いの支払い計画を立てる際は、次の手順で検討してください。
生活を見直す
借金をせざるを得なくなった理由を改善する必要があります。今後しっかりと金銭の管理を徹底できるのでなければ、債権者も分割払いには応じないでしょう。
家計簿を付けて収支を見直し、不要な固定費やサブスク費など、無駄な出費を抑える努力をしましょう。
利息を計算する
分割払いでは、将来かかる利息分だけ返済総額は増えてしまうので、金利の計算は欠かせません。なお、法定利息を超える高利は違法であり、返済を続けていた場合には過払い金返還請求が可能なケースもあります。
毎月の支払い額を決める
支払額の上限は、月収から毎月かかる固定費(家賃・光熱費などを)を控除した額の3分の1を目安として提案してください。
支払い期間を決める
債権者が金融機関のときは、36回払い(3年間)〜60回払い(5年間)が目安です。
支払い計画を立てる際に重要なのは、一方では将来の自分の首を絞めないよう「無理のないプラン」とすること、他方で、債権者に受け入れてもらえるよう、あまりに長期分割であったり少額の返済であったりといったことのないよう合理的なプランを組むことです。
債権者の性質に応じて戦略的に交渉する
借金の分割払いを交渉するにあたり、どのような債権者かも重要なポイントです。
債権者が友人や知人、家族といった個人なのか、銀行やサラ金、貸金業者などの金融機関なのかによって、適切な交渉の進め方が変わるからです。
債権者が個人の場合の分割交渉
債権者が個人のとき、話し合って分割払いを申し出るようにしてください。
個人の場合、「分割払いを受け入れてもらえるかどうか」は、その人との人間関係や信頼の有無、支払いができなくなった理由などが影響します。まずは誠意をもって頼み込むしかありません。個人の債権者は、金融機関とは違い「損得」ではなく「感情」で動くこともあります。感情的な対立が激しいと、分割払いを拒絶されるおそれがあります。
債権者が個人の場合でも、後に「言った・言わない」の水掛け論とならないよう、必ず分割支払いの計画を、「分割弁済契約書」などの形で書面化してください。
債権者が金融機関の場合の分割交渉
債権者が金融機関のとき、支払えなくなった後の交渉を「任意整理」と呼びます。借金が多額のときは弁護士を窓口にして交渉することで、スムーズに債務整理を進められます。
金融機関は通常、借金の分割払いの交渉に応じてくれることが多いです。債務者が自己破産してしまうと借金を回収できなくなるため、努力して少額ずつでも分割払いすると約束するなら、応じるメリットが金融機関側にもあるからです。
ただし、金融機関との任意整理の交渉では、受け入れてもらえる支払い計画には一定の相場があります。分割払いの支払計画は36回払い(3年間)もしくは60回払い(5年間)とする例が多く、これ以上長期で少額の分割払いは受け入れてもらえない可能性が高いです。したがって、このような計画では返済しきれないほど多額の借金があるなら、自己破産の方法を検討せざるを得ません。
分割弁済契約書・合意書の作成
分割払いとすることについて債権者・債務者間で合意ができたら、その約束の内容について書面化するため、分割弁済契約書を必ず作成しておいてください。
分割弁済契約書を作成することにより、支払う意思をきちんと示して誠意を見せ、額や期間などの支払い計画を証拠化することができます。また、債務者側においては、契約書通りに支払いを継続して、信用を回復することが重要です。
分割弁済契約書の書式と、作成するメリット

次に、分割弁済契約書について解説していきます。
分割弁済契約書とは、分割払いを合意する書面のことです。借りたお金を一括返済できず、債権者との交渉の末に分割払いすることで合意に至ったとき、その重要な合意内容について書面に残しておくことが大切です。
分割弁済契約書の書式例
分割弁済契約書の書式は、次の通りです。
分割弁済契約書
A(以下「甲」という)とB(以下「乙」という)とは、甲の乙に対する借入金の返済について次の通り合意した。
第1条 甲は、乙に対し、借入金XXX万円及びこれに対する20XX年XX月XX日から20XX年XX月XX日までの間の年3%の割合による遅延損害金の合計XXX万円の支払義務があることを認める。
第2条 甲は、乙に対し、前条の金員を下記支払計画に従って、分割して、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う(なお、振込手数料は甲の負担とする)。
記
⑴ 20XX年XX月から20XX年XX月まで、毎月末限りXX万円
⑵ 20XX年XX月から20XX年XX月まで、毎月末限りXX万円
⑶ 20XX年XX月末日限り、XX万円
以上
第3条 甲が、前条の分割金の支払を一度でも怠ったときは、当然に前条の期限の利益を失い、乙に対して、第1条の金員から既払い額を控除した残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から年3%の割合による遅延損害金をただちに支払う。
第4条 甲及び乙は、本契約書を強制執行認諾文言付きの公正証書にすることに協力する。なお、公正証書作成費用は甲の負担とする。
第5条 甲は、乙に対し、甲の氏名、住所、電話番号、勤務先について正確に情報提供を行い、かつ、提供した情報に変更のある場合には、事前に連絡しなければならないものとする。
第6条 本契約に定めのない事項、または、本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議をする。
第7条 本契約に関する一切の紛争は、XX地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
甲及び乙は、本書面の通り合意が成立した証として、本書面を2通作成し、署名押印の上、各自1通を保管する。
【作成日付・署名押印】
分割払いの合意内容を書面に残しておくことは、将来争いが起こってしまったときに証拠として活用できるという重要な意味があります。
分割弁済契約書を作成するメリットと理由
分割弁済契約書を作成することは、合意内容を証拠に残す意味があり、このことは、債権者側の利益になるのはもちろん、借金を返済する債務者のためにもなります。
支払い計画を証拠化できる
分割払いの合意内容を書面化することの債権者・債務者共通のメリットとして「支払い計画を証拠化できる」点があります。
客観的な証拠を残すことで、将来の紛争の拡大を防げます。特に、貸し借りの証拠が「借用書」のような形で残っていなかったり、現金手渡しで領収書の交付もしていなかったりといったケースでは、分割弁済・分割払いの合意に至った時点で必ず書面化すべきです。
万が一、分割弁済の履行ができなくなり、裁判になった場合にも、一旦合意した内容を証拠により明らかにすることで、裁判において争点を減らし、スピーディに解決できます。
約束通りの弁済を促す効果がある(債権者側のメリット)
分割払いの合意内容を書面化すれば、債権者側にとって、約束通りの弁済を促せるメリットがあります。口頭の約束に比べ、書面による約束に重きをおく日本社会において、分割弁済合意書に署名押印をしたことが心理的プレッシャーとなるからです。
更に、公正証書にすれば、裁判によらずに強制執行が可能となる強い効果があります。
予定以上の負担がなくなる(債務者側のメリット)
分割払いの合意内容を書面化すれば、債務者側にとって、支払い計画で示した以上の負担を負わずに済むメリットがあります。適切な合意書を準備しておくことで、追加請求などで際限なく責任追及をされるリスクは軽減できます。
なお、このメリットの恩恵を受けるには、分割弁済合意書の作成時に、不当な負担を負わないよう、適切な内容とすることを心がけるべきです。期限の利益の喪失条項が付されることが多く、約束通りの支払いを怠れば、やはり一括返済が必要となります。
借金を分割払いにしてもらう時の注意点

次に、借金を分割払いにするにあたり、注意すべきポイントを解説します。
どうしても一括返済できないなら、分割払いにするのは仕方ないですが、債務者にとっても、分割返済にすることはデメリットが存在します。交渉の結果、債権者に分割払いを承諾してもらうために、債務者側が不利な条件を飲まざるを得ないことがあるからです。
無理のない支払い計画か確認する
一括返済する資力がないとき、たとえ月々少額であっても支払いを続ける意思を示せば、自己破産に至るよりも債権者にとって有利なので、分割払いに応じてもらえる可能性は高くなります。
しかし、債権者に分割払いを受け入れてもらうには、将来の支払いがある程度確実に継続できる必要があります。そのため、債権者の要求に応じる形で無理のある支払い計画を受け入れてしまうケースも少なくありません。無理な計画だと、守れなくなったときに自分の首を絞めてしまいます。予期せぬ出費や事故、ケガなどで計画通りの返済ができなくなる事態を防ぐためにも、現実的で余裕をもった計画とすることが重要です。
自己破産を選択すべき状況か検討する
支払い計画に無理があると、結果的に自己破産を早めるおそれがあります。そして、最終的に自己破産を避けられないのであれば、現段階で破産を選択する方が合理的な場合もあります。
債務整理の実務において、金融機関を債権者とする任意整理の交渉では、毎月の返済額は「月収から家賃・光熱費などの固定費を控除した額の3分の1程度」を上限の目安とし、36回(3年)~60回(5年)の分割払いとするのが通例です。
つまり、この目安を超える金額を支払わなければ5年以内に完済できない場合は、自己破産などの法的手続きを検討する必要があります。あまりに無理な計画を立てると、結局は破産に至るリスクを高めてしまうので、慎重な検討が求められます。
保証人の負担を考える
連帯保証人がいる場合、分割払いの交渉を始めることは、債務者が当初の契約通りに返済できないことを意味します。その結果、債権者は連帯保証人に支払いを請求する可能性があります。また、分割払いの交渉時に、交換条件として新たな連帯保証人を求められることもあります。
連帯保証人は、法律上、債務者と同等の重い責任を負います。債務者が支払えない場合はもとより、債務者に支払いを求めずに保証人にいきなり全額の弁済を求めることも可能です。そのため、分割払いを申し出る際は、保証人に不利益が生じないかどうか、慎重に検討する必要があります。
なお、後述の通り、2020年4月1日施行の改正民法により、事業用資金に関する保証契約では、保証人になろうとする者が契約締結の1ヶ月以内に作成した公正証書によって、保証債務を履行する意思を示すh実用があります(公正証書がない場合、保証契約は無効となります)。
「保証契約の基本」の解説

ペナルティが重すぎないか確認する
借金の一括返済が難しく、分割払いの交渉をする場合、債務者の信用は低下しています。そのため、分割払いとするにあたり、債権者が未払いや滞納に対するペナルティを設定することがあります。よく見られるペナルティには、以下のようなものがあります。
- 遅延損害金
滞納時に発生する追加の利息のこと。 - 期限の利益の喪失条項
一度でも滞納すると分割払いが無効になり、一括返済を求められる条項。 - 違約金
契約違反に対する制裁として一定の金銭支払いを求めるもの。 - 保証人・担保の提供
支払いの確実性を高めるため、追加の担保を要求されることがある。
また、債権の回収を確実にするために、住所や連絡先を変更する際の報告義務を課したり、財産の所在や勤務先を知らせたりといったことを求められるケースもあります。このような要求に応じると、将来未払いとなった際に、強制執行による財産の差押えが容易になります。
分割払いを認めてもらえても、過度に厳しいペナルティを受け入れると、支払いが滞った際に状況が更に悪化してしまいます。交渉の際は、現実的な条件かどうかも考慮してください。
改正民法への対応(2020年4月施行)
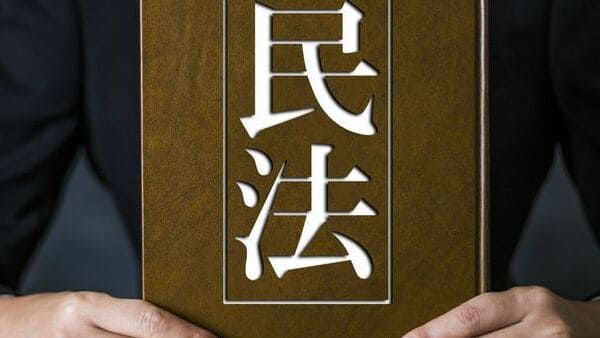
最後に、2020年4月1日に施行された改正民法の留意点も解説しておきます。
契約書などのルールを定める民法の債権法部分について、近時重大な改正があり、2020年4月1日に施行されました。分割払いの交渉を行うにあたっても、改正法の内容、特に「利息」と「保証」に関する変更点を理解しておく必要があります。
「利息」に関する民法改正
改正民法(2020年4月1日施行)では、法定利息について、従来の固定化された利率が、変動利率に変更されました。
従来、民事法定利率は「年5%」、商事法定利率は「年6%」でしたが、市場金利とかけ離れ、実態に沿わないことから改正されました。改正後、民事法定利率は「年3%」となり、その後は3年ごとに市場金利を加味して利率を見直し、変動させることとなりました(なお、商事法定利率は廃止)。
「法定利率」の解説

「保証」に関する民法改正
改正民法(2020年4月1日施行)では、事業様式の保証契約を有効に締結するために、次の2つの条件が必要となるという改正がなされました。
これは、事業用資金の貸付は高額となりやすいため、保証人が予想額の不利益を被らないようにするための規制です。なお、貸付自体が改正民法施行前でも、保証契約の締結が改正民法施行後の場合は、改正民法による「保証」の規制が適用されます。
「保証契約」の解説

まとめ

今回は、借金を一括返済できず、分割払いへの変更を希望する方に向けて、交渉の進め方や注意点、合意に至った際に作成すべき「分割弁済契約書」の書式について解説しました。
分割払いの交渉で無理な条件や支払計画を安易に受け入れると、長期にわたって返済に苦しむこととなります。自身の支払能力を慎重に検討し、無理のない計画を立てることが重要です。
また、債権者との間で分割払いの合意が成立したら、「分割弁済契約書」などの書面を作成し、証拠に残しておくことで将来のトラブルを回避できます。ただし、一度契約書や合意書に署名すると、原則として相手の同意なしに条件を変更できないので、内容を十分に確認することが必要です。
借金を返しきれないとき、法的には様々な対処方法が存在します。それぞれの方法のメリット・デメリットを理解し、自身にとって最適な解決策を選ばなければなりません。
- 借金を一括で返せないとき、分割弁済にするには妥当な分割案を提案すべき
- 分割払いについて債権者の承諾を得られたら、必ず分割弁済契約書を作成する
- 借金の分割返済を続ける際、自己破産と比べて合理的な選択かどうか検討する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/


