法定利率とは法律で定められた利率、法定利息とはその利率に基づく利息のことです。いずれも、金銭消費貸借契約のように人からお金を借りる際の利息の基本となる考え方です。2020年4月1日施行の民法改正において、法定利息のルールは大きく変更されました。改正では、法定利率が実態に即して低減されると共に、変動性となり、将来の変更を予定されることとなりました。
今回は、法定利率の意味と、民法改正における変更点について、弁護士が解説します。
- 法定利率は、約定利率を決めていない場合に適用される金利の基準
- 2020年民法改正で、年5%から年3%に引き下げられ、商事法定利率は廃止
- 今後も、市場金利の状況に応じて、法定利率は変動する可能性がある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
法定利息・法定利率とは

はじめに、法定利率と法定利息の基本と、計算のしかたについて解説します。
法定利率とは
法定利率とは、法律によって定められた金利の基準のことです。
民事法定利率は、2020年4月1日施行の民法改正により、現在は年3%です。
法定利率は、契約において具体的な「約定利率」(当事者間が契約で定めた利率)の合意がない場合や、支払い遅延時の損害賠償(遅延損害金)の計算基準として利用されます。
主に、金銭の貸借において、当事者間で合意された利率がない場合、法定利率が金利の基準として機能します。金利が法律で決められていることにより、貸し手と借り手の間の利益の調整を図り、貸し手による暴利の危険を防ぐと共に、公平な損害賠償が図られる仕組みとなっています。
法定利息とは
法定利息とは、上記の法定利率に基づいて算出される利息のことです。
例えば、契約に基づく支払いが遅延した場合には、契約上の特則がないとき、法定利率によって遅延損害金が計算されます。元本と合わせて利息を請求することで、貸し手は遅延による損失を補填でき、借り手は支払い遅延がもたらすコストを支払うこととなります。
法定利息の具体的な計算は、次の計算式によって算出されます。
- 法定利息 = 元本 × 法定利率 × 経過期間
例えば、100万円の借入金の返済が1年間遅延した場合、法定利率が年3%の場合、1年で3万円の法定利息が付されることとなります。
民法改正による法定利率の主な変更点

次に、2020年施行の民法改正によって導入された法定利率の変更点を解説します。
民法改正の背景と目的
従来の法定利率は、明治時代に制定された基準に基づいて固定的に運用され、一般の金銭債権では年5%、商事取引においては年6%と定められていました。しかし、低金利が続く現状からすると、年5%の法定利率は現在の市場金利から大きく乖離しており、問題視されていました。
民法改正において法定利率が変更された主な目的は、次の点にあります。
- 市場金利との調整
現代の低金利に合わせ、固定的な高金利を実情に即した水準に引き下げること。 - 公平性の向上
債権者と債務者の双方にとって不均衡な負担を是正すること。 - 将来の金利変動への柔軟な対応
固定利率ではなく、将来的な市中金利の変動に合わせて自動的に見直しが可能な「変動制」を導入し、法定利率の運用に機動性を持たせること。
「民法改正(2020年4月施行)」の解説
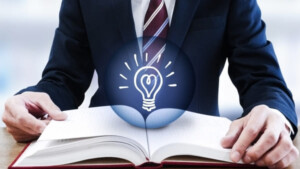
改正前の法定利率(〜2020年3月)
改正前の民法に定められた法定利率は、次の通りです。
- 民事法定利率は年5%
金銭消費貸借や一般の債権の不履行に対して適用される基準です。 - 商事法定利率は年6%
営業上の取引(商事債権)に対し、民事よりも高い金利が定められていました。
改正後の法定利率(2020年4月~)
改正後の民法で定められた法定利率は、次の通りです。
- 法定利率は年3%
改正後は、原則として年3%に引き下げられることとなりました(民法404条2項)。 - 変動制の導入
市中金利の動向に合わせ、3年ごとに法定利率の見直しが行われます(同条3項)。見直し時点の短期貸付の平均利率を「基準割合」とし、法定利率に変動があった期のうち直近の基準割合から1%以上変動があった場合、当該基準割合の変動分(1%未満は切捨)が、法定利率が調整されます(同条5項)。
民事法定利率が、変動制となり、従来よりも低率に調整されることになりました。これと並行して、商事法定利率は廃止されました。
民法改正による利率変更の実務への影響と注意点
以上の民法改正に伴う法定利率の変更は、長期低金利が続く中で、市場実態に合致しなくなった従来の固定的な高金利(民事は年5%、商事は年6%)を、実勢金利に合わせる目的があります。これにより、債務者にとっては過度な遅延損害金の負担の修正、債権者にとっても市場金利に即した適正な補償にとどめ、双方のバランスを調整する狙いがあります。
法定利率の変更は、企業・個人いずれにとっても、非常に大きな影響があります。
企業間の契約において、契約書に約定利率を記載していなかった場合、改正後は低い利率の遅延損害金となるので、契約条項の見直しが必要となる可能性があります。個人の借入金の返済が遅延した場合にも、改正後の利息は低くなります。
ただし、約定利率が定められている契約も多く、その場合は約定利率の方が優先するので、法定利率の引き下げで大きな影響はありません(むしろ、高すぎる約定利率は、利息制限法や消費者契約法などの法規制を受ける可能性があります)。この場合、改めて約定利率がしっかりと定められているかどうか、これを機に契約書を見直しておくことをお勧めします。
法定利率の変更の適用時期について

最後に、法定利率の変更がいつから適用されるか、「適用利率の基準時」について解説します。
改正民法の新しい利率は、2020年4月1日以降に発生した金銭債務に適用されます。つまり、改正前に利息が発生した債務については従来の法定利率が適用され、改正施行後に新たに発生した利息に新利率が適用されることとなります。
改正の前後をまたいで契約を締結したり、債務不履行となっていたりするケースでは、当事者間で別段の意思表示がないときには、「利息が生じた最初の時点における法定利率」が適用されるというルールになっています(民法404条1項)。つまり、利息が初めて発生するのが、民法改正が施行された2020年4月1日より前か後かによって、適用される利率が決められます。
遅延損害金は、遅滞責任が生じた時点における法定利率が適用されます。契約によって別段の定めを設けることのできない「不法行為」の場合、「不法行為時に遅滞に陥る」こととされているので、法定利率は「不法行為時」の法律にしたがって適用されます。
まとめ

今回は、法定利率と、それに基づく法定利息について解説しました。
法定利率は、2020年4月1日に施行された改正民法によって変更されました。今後は、当面の間は年3%から始まり、状況に応じて見直される変動制となります。特に、商事法定利率が廃止されたため、企業間の取引について年6%から年3%への大幅な変更となるので、しっかりと契約書を作成し、約定金利を定めておく重要性は増しています。
改正民法の施行前に作った契約書が、改正に対応しているか不安なときは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
- 法定利率は、約定利率を決めていない場合に適用される金利の基準
- 2020年民法改正で、年5%から年3%に引き下げられ、商事法定利率は廃止
- 今後も、市場金利の状況に応じて、法定利率は変動する可能性がある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
民法の改正は、契約や取引、債権債務など、生活や企業経営に密接に関わります。改正の内容を正しく把握しなければ、思わぬトラブルを招くおそれもあります。
適切な権利行使をするためにも、民法改正に関する解説記事を通じて、最新のルールを理解しておいてください。

