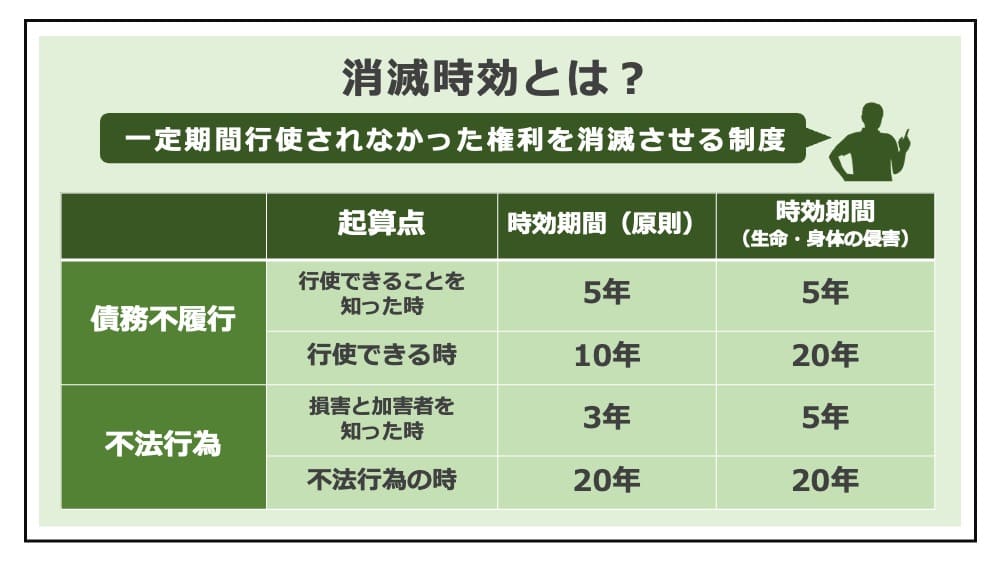交通事故における「過失割合」は、被害者と加害者の責任の程度を決めます。
交通事故において、過失割合が「10対0」となるケースは、被害者側には一切の過失がなく、加害者側に全面的な責任のある事故です。被害者としては、「10対0」の過失割合は最も有利ではありますが、慰謝料請求で損をせず、示談交渉を有利に進めるには、慎重に進める必要があります。
過失割合が「10対0」だと、加害者は、少しでも支払い額を下げるために徹底して争ってくると予想されます。適正な賠償額を請求し、正当な補償を受けるには、事故後の混乱した状況でもしっかりと証拠を集めるなど、的確な対応を心掛けなければなりません。
今回は、過失割合が「10対0」の交通事故における対応方法について弁護士が解説します。
- 過失割合が「10対0」の交通事故では、被害者には全く過失がない
- 「10対0」の事故でも、加害者が不利な過失割合を主張してくることがある
- 過失割合で損をしないよう、示談交渉を弁護士に依頼するのがお勧め
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
\ 動画解説動画(約4分) /
過失割合が「10対0」の交通事故とは

はじめに、過失割合「10対0」の交通事故の意味について解説します。
過失割合とは
過失割合とは、主に交通事故において、事故を招いた当事者間の過失の度合いや責任の割合を数値で表したものです。例えば「信号を確認しなかった」「一時停止を怠った」「歩行者を見逃した」など、本来すべき注意を怠ったという「注意義務違反」の程度を示しています。
過失割合は、事故の原因となった「責任」を明確にするために用いられ、慰謝料や損害賠償の額を決める基準となります。実際に受け取れる賠償額は「損害」と「責任」の掛け算で決まるところ、どれほど損害が大きくても、自分側の過失割合が高いと、賠償額は低くなります。
例えば、過失割合が「5対5」の事故で、損害が500万円だとすると、請求する賠償額は250万円(=500万円×50%)となります。
過失割合の決め方
過失割合は、被害者と加害者の示談交渉において、合意によって決められます(一方の当事者または保険会社が過失割合を提示し、他方が同意する場合)。
ただ、賠償額が大きい場合や、当事者間に感情的対立がある場合には、話し合いで解決できず、裁判に発展するケースもあります。裁判所では証拠を調べ、交通事故の態様や事故原因などから過失割合についての判断を下します。この際、裁判所は、交通事故の態様や違反の程度などを証拠をもとに精査し、類型的に過失割合を決定します。
交通事故の裁判例は、過去に数多くあるため、事故態様によって類型的な過失割合の相場が決まっています。その相場は、「緑の本」(正式名称「別冊 判例タイムズ38号(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)」)に記載されており、裁判所も大いに参考にしています。
過失割合「10:0(10対0)」の意味
「10対0」という過失割合は、加害者側が全責任を負い、被害者には一切過失のない状態を意味します(つまり、加害者側が一方的に悪い事故、いわゆる「もらい事故」のケース)。
「10対0」なら、加害者の行為が事故の原因であり、被害者には全く過失がありません。したがって、過失割合によって賠償額が減額されることもなく、全損害を請求できます。全く責任のない被害者は、十分な補償を受ける権利があるからです。
自動車同士の事故では、双方に多少の過失が認められ、部分的に責任分担が決められるケースが多いです。特に、加害者・被害者いずれも走行中だと、事故が起きる確率は一定程度あり、互いに過失が認められることが多いです。したがって、「10対0」のケースは、被害者が完全に停止している「追突事故」や、加害者の違反が著しい「センターオーバー」などが典型例です。
過失割合が「10対0」となる具体的なケース

次に、過失割合が「10対0」となる交通事故にどのようなケースがあるか解説します。自動車、自転車、歩行者によって注意義務の程度が異なるため、場合に分けて説明します。
過失割合は、裁判例によって類型化されているので、実際の事故態様をあてはめて過失割合がどの程度かを判断できます。「10対0」の事故は、加害者側が信号無視やスピード違反などの交通法規違反を犯し、かつ被害者側が安全確認を怠っていなかったことが前提となります。
過失割合は争いとなることが多いので、裁判も見据えた証拠の準備が欠かせません。
自動車と歩行者の事故で「10対0」となるケース
自動車と歩行者の交通事故では、「弱者」である歩行者が保護されます(優者危険負担の原則)。そのため、自動車と歩行者なら、自動車側の過失が大きいと判断されるのが原則です。
自動車と歩行者の事故で過失割合が「10対0」となるケースは、次の通りです。
歩行者が青信号で横断開始後の事故
信号のある交差点での事故で、「歩行者が青信号で横断を開始した場合」に車両と衝突したとき、過失割合は「10対0」となります。歩行者側が青信号なら、自動車側では「赤信号を直進した」または「青信号だが交差点に進入した後で右折・左折した」場合となり、いずれも過失は非常に大きいと考えられるからです。
歩行者が青信号で横断を開始後であれば、その後に黄信号、赤信号に変わったとしても歩行者の過失は認められません。なお、歩行者が黄信号、赤信号で横断を開始したときは過失割合が「9対1」に修正されます。
横断歩道上の事故
信号のない交差点の場合、「横断歩道上」の事故は「10対0」の過失割合となります。横断歩道近辺でも、1m〜2m以上離れた場所で衝突したときは、歩行者側にも一定の過失が認められて「7対3」に修正されます。
歩道上に車両が進入してきた事故
歩行者が歩道を歩いていたにもかかわらず車両が進入して事故になったとき、歩行者側の過失はなく「10対0」の過失割合となります。歩道のない道路でも、歩行者が道路の端を正常に歩行していたときは、同様に歩行者の過失はありません(なお、歩行者の突然の飛び出しやふらふら歩きがあると、過失割合が修正されます)。
自動車と歩行者の事故の過失割合の修正要素
上記のような類型に該当し、基本的に「10対0」の事故でも、具体的な事故状況によって修正要素が考慮され、過失割合が増減することがあります。
自動車と歩行者の事故の過失割合の修正要素は、以下のものがあります。
【自動車の過失を重くする要素】
- 歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障碍者
- 著しい過失、重過失
【歩行者の過失を重くする要素】
- 幹線道路上の事故(横断歩道上の事故では+5、その他の事故では+10)
- 歩行者の横断禁止の規制あり
- 車両の直前・直後に道路を横断したこと
- 急な飛び出し、ふらふら歩き
自動車同士の事故で「10対0」となるケース
自動車同士の事故では、一方的な有利不利はなく、注意義務違反の程度に応じて過失割合が決まります。どちらも走行していたケースでは互いに過失が認められることが多く、「10対0」となるのは片方の過失が著しい事例に限られます。
自動車同士の事故で過失割合が「10対0」となるケースは、次の通りです(なお、単車(バイク)同士の事故や、単車と自動車の事故も、同様に判断されます)。
追突事故
停車中の被害者車両に対し、加害者車両が後ろから衝突した「追突事故」は、過失割合が「10対0」の事故となります。加害者車両に、一方的な「前方不注視」「車両距離不保持」といった注意義務違反が認められるからです。
追突事故は、被害者車両の側では避けようがなく、「不適切な急ブレーキを踏んだ」などの特別な事情がない限り、被害者の過失はありません。
センターラインオーバーの事故
センターラインの引いてある幅広の道路で、ラインをオーバーして対抗車両と接触した事故は、過失割合が「10対0」となります。
センターラインオーバーの理由には、酔っぱらい運転、居眠り運転などの例が多いですが、これに限らず、追い越しのためにセンターラインをオーバーして対向車とぶつかったケースも「10対0」の事故に含まれます。
赤信号無視による事故
赤信号を無視して突っ切った結果として交通事故になったケースは、「10対0」の事故となります。赤信号無視は明らかな交通法規違反であり、責任が重く判断されます。
自動車同士の事故の過失割合の修正要素
追突事故、センターラインオーバー、赤信号無視と、自動車同士で「10対0」の過失割合となるケースは、加害者の悪質性が相当高いです。しかし、被害者も注意して運転しなければ、修正要素によって一定の過失が認められるおそれがあります。
追突事故では、被害車両が理由のない急ブレーキをかけると「7対3」の事故となるほか、次の修正要素があります。
【被害者の過失を重くする要素】
- 住宅街・商店街等での事故(+10)
- 被害者車両が15kmの速度違反(+10)、30kmの速度違反(+20)
- 被害者側の著しい過失(+10)、重過失(+20)
【加害者の過失を重くする要素】
- 幹線道路を走行線上での停止(-10)
- 制動灯の故障(-10〜20)
- 加害者側の著しい過失(-10)、重過失(-20)
センターオーバーの事故における過失割合の修正要素には、次のものがあります。
【被害者の過失を重くする要素】
- 加害者車両が15kmの速度違反(+10)、30kmの速度違反(+20)
- 被害者側の著しい過失(+10)、重過失(+20)
【加害者の過失を重くする要素】
- 加害者車両の速度違反(-10〜20)
- 追越禁止場所での追い越し(-10)
- 加害者側の著しい過失(-10)、重過失(-20)
なお、著しい過失とは、脇見運転などの著しい前方不注視、著しいハンドル・ブレーキ捜査の不適切、携帯電話で通話しながらの運転、15km以上30km未満の速度違反、酒気帯び運転が挙げられます。
重過失は、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、30km以上の速度違反、過労・病気や薬物の影響により正常な運転ができないおそれがある場合などの例です。
自転車と自動車の事故で「10対0」となるケース
自転車と自動車の事故では、次のケースが「10対0」の過失割合となります。
直進する自転車を自動車が追い越して左折した場合の事故
直進する自転車を後続の自動車が追い越し、その後、交差点などで左折した際に発生した交通事故では、過失割合が「10対0」となります。同じ進行方向を走行する自転車を自動車が巻き込んだケースでは、自転車側に過失が認められる要素はほとんどなく、自動車側が全責任を負うからです。
自転車が青信号で横断中に自動車が赤信号で進入した場合の事故
自転車が青の歩行者用信号で横断している際に、自動車が赤信号を無視して進入し事故を起こした場合、過失割合は「10対0」です。自動車は自転車よりも重い注意義務を負っており、特に信号機のある交差点で「自転車が青」「自動車が赤」という状況で発生した事故は、自動車に一方的に非があります。
自転車と歩行者の事故で「10対0」となるケース
自転車と歩行者の事故では、次のケースが「10対0」の過失割合となります。
歩行者が青信号で横断中の事故
歩行者が青信号で横断中に、自転車が赤信号を無視して進入し、事故を起こした場合、過失割合は「10対0」です。歩行者が青信号で横断を開始すれば、途中で信号が赤に変わった場合でも、自転車が赤信号で進入すればやはり「10対0」となります。
更に、自転車が右折や左折で交差点に進入する際、歩行者側の信号が青なら、自転車側の信号が青でも過失割合は「10対0」となります(同様に、その後に歩行者の信号が赤に変わった場合でも自転車側が赤信号で進入すれば100%の過失責任を負います)。
横断歩道上での事故
信号機のない横断歩道で発生した歩行者と自転車の事故では、自転車側の過失が大きく、過失割合は「10対0」となるのが基本です。横断歩道を渡る歩行者は最も優先されるべき存在なので、自転車側の過失のみが認められるケースがほとんどです。
自転車が歩道上を走行していた際の事故
歩道を直進中の自転車と歩行者の交通事故では、歩行者に過失が認められることはほとんどなく、過失割合は「10対0」が基本です。路側帯を通行中の事故でも同様で、自転車は原則として自動車と同じ道路交通法の適用を受け、歩行者よりも重い責任を負います。
なお、「自転車通行可」の標識のある歩道では、自転車の通行が認められますが、それでも歩行者の通行を妨げることは許されず、歩行者への十分な配慮が必要です。
過失割合が「10対0」の場合の慰謝料請求

次に、「10対0」の交通事故における慰謝料請求のポイントを解説します。
慰謝料は、被害者が被った精神的苦痛に対する補償として算出されますが、その際に、過失割合が考慮されます。過失割合が被害者にとって不利なものとなると、慰謝料の金額が減額されるおそれがありますが、「10対0」のケースなら被害者に過失はないので、高い補償が期待できます。
「10対0」の事故の慰謝料の額
交通事故では、慰謝料の額は次のような点から判断されます。
- 入通院慰謝料
交通事故によって入院や通院を要した場合に、その治療期間に応じて計算されます。 - 後遺障害慰謝料
交通事故のケガによって、後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合には、その等級ごとに定められた慰謝料を受け取ることができます。
本来、慰謝料は、精神的ストレスの大きさによって判断されますが、交通事故のトラブルは数多く起こっているので、ある程度の相場が定まっています。
「後遺障害慰謝料の請求方法」の解説

慰謝料を請求する方法
慰謝料請求の具体的な方法と流れは、次の通りです。
必要な証拠の準備
慰謝料請求を進める際は、事故当時の状況を裏付ける証拠や書類が不可欠です。具体的には、以下のものが役立ちます。
- 事故証明書、警察の報告書
事故発生時の状況が記載されており、過失割合の根拠となる書類です。 - 診断書や医療費の領収書
ケガや障害の状況、治療内容や期間、後遺症の有無を示す証拠です。 - 防犯カメラ映像や目撃者の証言
被害者側に過失がないことを証明するための補強資料となります。
示談交渉
証拠が揃ったら、示談交渉で加害者側に請求を行います。
加害者側やその保険会社は、できるだけ低い金額での解決を狙っており、被害者に不利な提示をしてくることも多いので、安易に示談に応じずに提案額を精査しましょう。加害者側から示談の提示があったら、交通事故を多く扱う弁護士に相談してアドバイスを求めるのが有効です。
示談交渉のプロセスを記録するため、交渉は書面のやり取りで行うのが基本です。
過失割合が「10対0」の示談交渉を有利に進めるポイント

次に、過失割合が「10対0」の交通事故の示談交渉のポイントを解説します。
過失割合が「10対0」なら被害者の過失はなく、損害の満額を受け取れます。被害者側に有利な状況であるのは明らかですが、保険会社の提示額が相場よりも低いことがあるので、示談に応じるかは慎重に見極めてください。
保険会社の示談代行サービスが使えない
過失割合が「10対0」の事故では、保険会社の示談代行サービスが利用できません。
交通事故被害に遭ったとき、保険会社が示談の窓口となる代行サービスは、被害者に過失が一切ない場合は利用できません。というのも、保険会社は実際には「代理人」としてではなく「賠償金(保険金)を支払う当事者」として交渉しているに過ぎないからです。「10対0」の事故では、被害者は損害賠償を受け取る立場であり、支払う側ではないので、保険会社は窓口になれません。
これに対して加害者側の保険会社は、事故態様について争ったり、被害者にとって不利な過失割合を提案したりして、支払う賠償額を減らそうと交渉してくる可能性があります。保険会社に頼めない場合、弁護士を依頼しなければ被害者自身が交渉する必要があります。
物損事故で先に示談しない
交通事故の損害には、「人損」(人身事故の損害)と「物損」(車両や携行品など物損事故の損害)があります。人損は治療終了後に交渉することとし、物損の交渉を先行させるのが通常です。しかし、注意すべきポイントは、物損事故の示談で合意した過失割合が、人損の示談にも影響を及ぼすことが多いということです。
例えば、物損の示談で「9対1」といった過失割合で譲歩してしまうと、その割合が人損にも適用され、受け取れる賠償額が減少するおそれがあります。
そのため、過失割合を「10対0」と主張したいのであれば、物損の示談でも一切譲歩せず、加害者が過失割合について争うときは慎重に対応する必要があります。特に人損事故では、後遺障害慰謝料や逸失利益など、金額が大きくなる賠償項目があるので、物損の段階で不用意に譲歩したことが、後で大きな不利益に繋がるおそれもあります。
加害者側の主張する過失割合を争う
過失割合に争いがある場合、保険会社は加害者側の主張する過失割合を提示してきます。
この際、「緑の本」(別冊判例タイムズ)の図を根拠に、専門的な知識に基づいて過失割合について説明してくることがあります。加害者側の保険会社が「10対0」や「100対0」といった不利な内容を最初から認めるケースは稀であり、たとえ加害者の過失が大きい事故でも、「9対1」「8対2」といった割合を提示して、被害者にも一定の責任を負わせようとする傾向があります。
しかし、過失割合を最終的に決定するのは裁判所であり、保険会社ではありません。その際に参考とされるのは過去の裁判例の蓄積です。
実際の事故では、具体的な事故状況によって過失割合が変わるので、書籍の図表通りになるわけではありません。「緑の本」は各類型に修正要素を定めているところ、保険会社の主張は、加害者に有利な事情を最大限考慮し、被害者に有利な事情を意図的に無視しているおそれもあります。
過失割合の証拠を収集する
過失割合が「10対0」だと主張するとき、事故態様を説明する証拠を集めることが重要です。
加害者側は、支払う賠償金を少しでも減らすため、「緑の本」の図で「10対0」に該当する事故態様だとしても、修正要素を持ち出して「10対0」にならない理由を主張してくることがあります。例えば、典型的な「10対0」となる「追突事故」でも、「停車位置が悪かった」「被害者の車両も動いていた」などと反論して、過失割合を「9対1」に修正しようとします。
このように被害者と加害者の主張が異なる場合は、客観的に事故態様を証明するために、次の証拠を集めることが大切です。
- ドライブレコーダーの映像
事故発生の瞬間を記録し、過失割合を判断する決定的な証拠となります。 - 実況見分調書
警察が作成する事故状況の記録であり、公的なものとして交渉や裁判における重要な資料となります。 - 衝突部分の写真
どこにどのように衝突したかを明確に示し、加害者の主張を覆す材料になります。 - 事故現場の写真
信号機の有無、道路状況、視界の良し悪しなど、事故の発生要因を客観的に示すことができます。
証拠をしっかり確保し、安易に保険会社の提案を受け入れずに交渉を進めることで、適正な過失割合の認定を実現できます。
弁護士に「10対0」の事故を依頼するメリット

最後に、過失割合が「10対0」の事故について、被害者側が弁護士を依頼するメリットを解説します。加害者が「10対0」であるとは認めず争ってくるとき、納得のいく解決を得るには交通事故に精通した弁護士のサポートが有益です。
正しい過失割合を主張できる
過失割合は、まず話し合いで決定され、合意に至らない場合は裁判で判断されます。
加害者側の保険会社は、交通事故の対応に慣れており、適切な過失割合を理解していますが、賠償金を少しでも減らすために、多少なりとも無理のある反論をしてくることもあります。
弁護士が交渉窓口となることで、適切な過失割合の類型や考慮すべき修正要素を反映し、正当な主張をすることができます。保険会社も、弁護士がつくことで裁判のリスクを意識し、結果的に「10対0」であると認めるケースが増える傾向にあります。
なお、過失割合はもちろん、治療の必要性や後遺障害の認定などに争いがあるときは、交渉では決着せず、裁判に移行する方が有利な解決を図れるケースもあります。
示談金を増額できる
弁護士に依頼することで被害者に有利な過失割合を主張するだけでなく、裁判に備えて証拠収集をサポートしてもらい、示談金を増額することが期待できます。
交通事故の損害賠償には、以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準
自賠責保険が採用する基準であり、3つの中で最も低額です。 - 任意保険基準
保険会社が独自に設定する基準であり、相手の損害保険会社によって提案が異なります。 - 弁護士基準(裁判基準)
弁護士に依頼して裁判をした場合に実現できる基準であり、最も高額となります。
示談交渉の際、保険会社は「自賠責基準」や「任意保険基準」で提案してきます。弁護士を依頼せずに自身で交渉を進めると、本来よりも低い金額で示談するおそれがあります。
弁護士に依頼し、交渉の時点から裁判を視野に入れることで、弁護士基準(裁判基準)の賠償金を獲得できる可能性が高まります。特に「10対0」の事故は、被害者側が全額の損害賠償を受け取れる立場なので、裁判をする可能性を示すことで示談金を増額することが非常に重要です。
精神的ストレスを軽減できる
「10対0」の事故では、保険会社の示談代行サービスが利用できず、被害者自身が交渉する必要があります。しかし、加害者の保険会社は「過失割合を争う」「被害者に不利な提案をしてくる」「被害者の気持ちを考えない発言をしてくる」といった対応をすることがあります。「10対0」の被害者であるにもかかわらず、誠実で心無い発言をされると大きな精神的負担となるでしょう。
弁護士に依頼すれば、加害者側との交渉を全て任せることができ、直接やり取りをする必要はなくなるので、ストレスなく進められます。なお、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の負担もありません。
まとめ

今回は、過失割合が「10対0」となる交通事故について解説しました。
過失割合が「10対0」となるのは、被害者に全く責任のないケースです。被害者に全く非がない状況でも、慰謝料請求や示談交渉は必要です。そして、適切な証拠を確保したり、弁護士に相談したりしながら進めないと、適正な賠償額を得られなかったり、加害者から「9対1」「8対2」といった不利な過失割合を主張されてしまう危険があります。
過失割合が「10対0」ということは、加害者が一方的に悪く、いわば巻き込まれ事故といってよいでしょう。にもかかわらず、保険会社には代理交渉を断られ、加害者からは「少しは過失があったはずだ」と反論されるなど、非常に不愉快な思いをするでしょう。
示談金を減らさないよう、正当な補償を受けるには、弁護士への相談が賢明です。
- 過失割合が「10対0」の交通事故では、被害者には全く過失がない
- 「10対0」の事故でも、加害者が不利な過失割合を主張してくることがある
- 過失割合で損をしないよう、示談交渉を弁護士に依頼するのがお勧め
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/