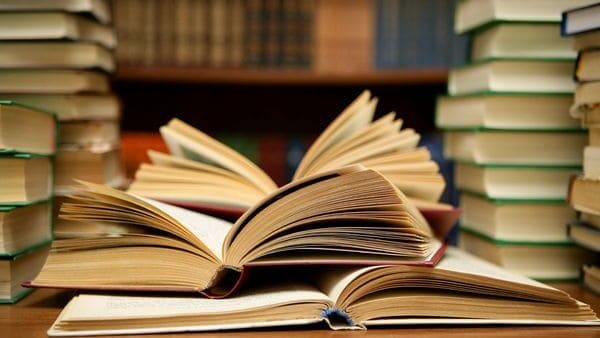契約書や利用規約に「当社の定型約款が適用される」との記載があることがあります。
定型約款は、不特定多数の相手と大量の取引や契約を行う際に用いる、あらかじめ準備した画一的な契約条件のことを指します。大量の同種取引を迅速かつ効率的に行うことを目的に、例えば、電車やバスの運送約款、電気やガスの供給約款、保険約款、ECサイトやサブスクリプションサービスの利用規約などで活用され、現代の取引実務に不可欠な存在となっています。
定型約款について「一方的に不利な条件を押し付けられるのではないか」との懸念もあり、2020年4月の民法改正で、その定義や効力、変更のルールが明文化されました。
今回は、定型約款の法的な意味、契約書や利用規約との違いと、2020年改正民法の定める要件について、弁護士が詳しく解説します。
- 定型約款は、民法の要件を満たす場合、個別の合意なく契約内容となる
- 定型約款を契約内容とするには、事前の合意もしくは周知が必要
- 定型約款を変更するには、変更の合理性と事前の周知をしなければならない
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
定型約款とは

定型約款とは、事業者が不特定多数の者との間で、反復継続的に行う取引に備えてあらかじめ用意した契約条項の総体のことです(民法548条の2)。定型約款は、一般にいう「約款」の中でも、民法上の要件を満たすものであり、「定型取引」における画一的なルールを意味します。定型取引とは、以下の3つの要件を満たす取引です。
- 不特定多数の者を相手方として行う取引であること
- 同種の契約を反復継続して締結すること
- 画一的な処理が双方にとって合理的であること
したがって、以上の成立要件を満たす取引に用いられる約款は、「定型約款」に該当します。
定型約款は、取引相手の属性や状況に応じて都度内容を変更するのではなく、同一の条項を多数の相手方に一律に適用することを前提とします。定型約款に該当すると、契約ごとの個別交渉なく、「当社の利用規約が適用される」といった形で、事前に作成した条項を契約の一部とすることが可能となります。そのため、画一的な運用が、利用者にも合理的であることが前提となります。
定型約款についての民法の条文は、次の通りです。
★ 定型約款に関する民法の条文
民法548条の2(定型約款の合意)
1. 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。2. 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。
民法548条の3(定型約款の内容の表示)
1. 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
2. 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
民法548条の4(定型約款の変更)
1. 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。2. 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3. 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4. 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
民法(e-Gov法令検索)
定型約款が活用される具体例
定型約款が活用される具体例としては、次のようなケースがあります。
- 公共交通機関
JRの運送約款、航空会社の運送約款など - 通信・インフラ系
電力会社・ガス会社・水道会社などの供給約款、通信事業者の利用約款など - ECサイトやWebサービス
Amazonや楽天などのECサイトの利用約款、サブスクリプションサービスの約款、アプリの利用約款など - 金融取引や保険契約の約款
生命保険・損害保険の保険約款、銀行の預金規定、クレジットカード会社の会員規約など
これら定型約款の例はいずれも、契約内容が事前に一律に規定され、個別の契約書を取り交わすのは不自然です。そして、利用者の利便性からしても、規約に同意することで契約を成立させることにメリットがあります。
「民法改正(2020年4月施行)」の解説
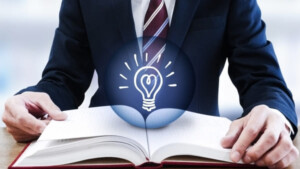
契約書や利用規約との違い
定型約款は、民法における要件を満たす特別なものであり、一般の契約書や利用規約とは異なります。その違いは、以下の通りです。
一般の契約書との違い
契約書は、当事者間で個別に協議、交渉し、合意に至った事項を書面化したものです。例えば、売買契約書、不動産賃貸借契約書、M&A契約書、業務委託契約書など様々な種類がありますが、いずれも一対一で個別に取り交わし、署名押印することで成立します。
一方で、定型約款は、契約締結時には、内容が事業者側によって既に定められており、利用者側は交渉できず、「同意するかどうか」が問われます。契約内容の決定について一方の当事者が関与していない点が、契約書と大きく異なります。
なお、実務では、契約書と定型約款を組み合わせる例もあります。例えば、申込書では個別条件を約束し、規約で一般条項を補完するという方式です。
利用規約との違い
「利用規約」と「定型約款」はしばしば混同されますが、全ての利用規約が民法上の定型約款の定義にあてはあるわけではありません。定型約款とみなされるのは、あくまで民法上の要件を満たすものに限られます(要件は「定型約款とは」で後述)。
したがって、「利用規約」の中でも、不特定多数の者との定型的な取引を反復して締結するにあたり、同一内容で処理する方が当事者双方にとって合理的なものが「定型約款」となります。そのため、「利用規約」と題する文書も、次のケースは定型約款になりません。
- 小規模で個別対応を予定している場合
個人事業主や小規模事業者が、顧客ごとに条件を調整する場合など、画一的に処理していない場合は「定型取引」ではなく、「定型約款」になりません。 - 相手方との交渉が予定される場合
BtoBの取引において、相手企業の要望を聞いて交渉することが予定されている場合、利用規約が存在していたとしても「定型約款」には該当しません。 - 単発の取引の場合
単発の取引で個別に作成する文書には反復継続性がなく、「定型約款」にはなりません。
したがって、自社の規約が形式上「利用規約」「約款」などの名称だとしても、それが民法にいう「定型約款」に該当するかどうか、よく検討しなければなりません。
というのも、定型約款に該当する場合の効果として、契約内容とする合意があるか、あるいは、相手に表示されていれば契約内容となりますが、定型約款とは認められない利用規約を契約内容とするには、あらかじめ相手に確認させ、同意を取得する必要があるからです。
民法改正における定型約款のルール
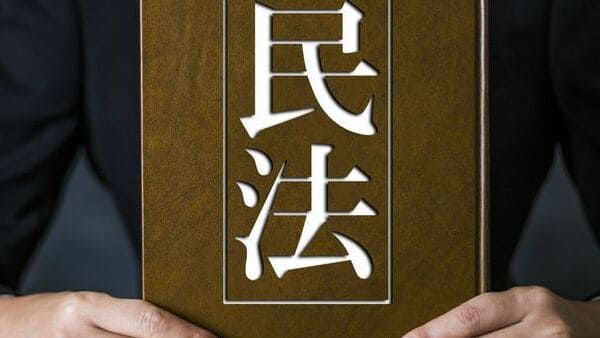
定型約款は、2020年4月1日に施行された民法改正で新たに導入されました。そのため、法改正が行われた経緯や、民法上の要件について理解しておく必要があります。
定型約款の規定が新設された経緯
2020年4月以前も、約款による契約は、金融や運送、保険、通信サービスなどの幅広い分野で行われてきましたが、定型約款についての法律の規定は存在しませんでした。
そのため、事業者の作成した約款が、どのような条件で契約内容になるか、利用者の許可なく変更が可能かといった点について法律上のルールが曖昧であるという問題点がありました。
この状況下では、次のようなトラブルが頻発していました。
- 利用者側が「約款の内容を知らなかった」と主張する。
- 約款が「契約の一部ではない」と争われる。
- 事業者による一方的な規約変更は「無効」と主張される。
特に、インターネット上の取引では、ワンクリックで契約が成立してしまうため、利用規約を読まずに契約を締結し、後でトラブルになるケースが増えていました。裁判例では「利用者に周知されており、内容に同意したとみなされる合理的な状況にあるなら、約款は契約の内容となる」との解釈(いわゆる「約款法理」)が構築されたものの、事案ごとに裁判所の判断が分かれ、事業者・利用者のいずれにとっても予見可能性が乏しく、法的安定性を欠いていました。
このような背景から、2020年4月施行の民法改正で、定型約款についての法律上のルールが明文化されました。今後は、契約実務における透明性と予見可能性が確保されることが期待されます。
定型約款が契約内容となる要件
改正民法は、定型約款が契約内容となるための要件として、次のことを定めています。以下の要件を満たさない約款は、契約の内容とはなりません。
合意または表示(民法548条の2第1項)
まず、定型約款が契約内容として効力を持つには、次のいずれかの方法によって、契約の一部として組入れられる必要があります。
- 定型約款を契約の内容とする旨に合意があった場合
- 取引に際して定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ相手に表示していた場合(ただし、電車やバスの運送契約など、相手方への「表示」が困難な取引類型では、「公表」で足りる旨の特則が個別の業法に設けられている)
表示方法には、次のような例があります。
【Webサービスの場合】
- サイト上に定型約款へのリンクを設置する。
- 申込みフォームに「本サービスには規約が適用される」と明記。
- フォームに「同意する」というチェックボックスを設置する。
【店頭契約・書面契約の場合】
- 約款集の設置、冊子の配布など。
- 申込書に「約款が適用される」と記載し、約款を添付する。
- 規約に関する質問があった場合は、内容を丁寧に説明する。
これらの要件を満たせば、事業者は、定型約款について利用者の個別の同意を得ることなく、約款を契約の内容とすることができます。
不当条項に該当しないこと(民法548条の2第2項)
定型約款の条項が、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの」である場合、合意しなかったものとみなされます。
したがって、定型取引の特質に照らして、相手の利益を一方的に害する契約条項で、信義則に反する内容については、契約内容とはなりません。約款の定めは「契約自由の原則」によりますが、弱者である利用者を保護するためにバランスを取る必要があり、不当な条項については無効となることが定められているのです。
なお、利用者にとって著しく不利な内容を定めた定型約款は、消費者保護法の観点からも無効となる可能性があります。
開示義務に違反しないこと(民法548条の2第3項)
定型約款を準備していた場合でも、相手から定型約款の内容を示すよう請求があった場合に、定型約款準備者が正当な理由なくその請求を拒んだ場合には、その定型約款の条項は、契約内容にはなりません。
したがって、原則として個別の説明義務はないものの、定型約款を開示するよう請求されたら、遅滞なく、相当な方法で約款内容を示さなければなりません。
定型約款の変更はできる?

定型約款は、一定の要件を満たせば、相手の同意なく変更することができます。
定型約款の変更は、①顧客の一般の利益に適合する場合や、②契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款を変更することがある旨の定めの有無、その他の事情に照らして合理的であると認められる場合に行うことができます(民法548条の4第1項)。
約款の変更が許される「合理的」な場合とは、例えば次のケースです。
- 消費税率変更に伴う料金改定
- サービスの仕様変更に伴う条項修正
逆に、事業者の一方的な都合で約款を不利益変更したり、顧客の権利を制限したり、義務を加重したりするのは合理性がなく、変更の効力が否定される可能性があります。
変更にあたっては、効力発生時期を定め、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他適切な方法によって周知する必要があります(民法548条の4第2項)。この要件を満たさない変更後の約款は、契約内容として有効とならず、旧約款が引き続き契約条件となります。
周知の方法には、例えば次のような運用が考えられます。
- ウェブサイト上に変更を告知し、新旧対照表を掲載する。
- 契約者にメール通知で通知し、アプリ内で告知する。
- 効力発生日までの間、確認や異議申立の機会を与える。
告知期間は、取引の重要性によって検討すべきですが、少なくとも2週間~1か月程度が目安となります。企業側は、顧客にとって不利益な変更を行う際は特に注意しなければなりません。形式的に告知を行うだけでなく、「いつから・何が・なぜ変わるのか」を明確に伝えることで、後のトラブルを防ぐ対策を講じることが重要です。
定型約款に関するよくある質問
最後に、定型約款に関するよくある質問に回答しておきます。
定型約款に同意しないとサービス利用できない?
多くのサービスは、定型約款となる利用規約への同意が利用条件となっています。そのため、サービス提供者に一律に適用される約款に同意しなければ、契約を成立させることができません。例えば、「利用規約に同意する」ボタンにチェックを入れなければ申込が完了できないWebサービスが典型例です。この場合、約款に同意できないなら、サービス利用は避けるしかありません。
定型約款の要件を満たす場合には、同意すれば契約内容に組み入れられることとなるので、特にインターネット上のクリックによって同意したことにならないか、注意深く行動すべきです。
途中で規約変更があったら以前の契約はどうなる?
定型約款が、民法548条の4に定める手続きに従って変更された場合、改定後の約款は、将来的にも契約内容の一部となります。そのため、変更後の約款の効力が発生した後は、新しい規約が適用されます。
ただし、変更が合理的でなかったり、周知が適切になされていなかったりする場合は、変更が無効となり、旧規約が引き続き適用されます。
納得できない約款の一部の条項を無効にできる?
定型約款は、その全体が包括的に契約内容となります。
そのため、納得がいかなくても、特定の条項のみ無効にしたり、排除したりすることはできません。どうしても承諾できないなら、サービス利用を避けるしかないでしょう。
ただし、次のケースでは、その条項だけが無効になる可能性があります。
- 民法548条の2第2項により、信義則に反して利用者に一方的に不利益な条項
- 消費者契約法に基づき、消費者の権利を不当に制限する条項
このような条項は、法律により「契約に含まれなかったもの」と扱われ、その部分だけが無効となり、約款の他の条項は有効となる可能性があります。
まとめ

今回は、2020年の改正民法で新たに導入された「定型約款」について解説しました。
定型約款は、現代の商取引に欠かせない存在です。不特定多数の顧客と反復継続して契約を締結する事業者にとって、業務の効率化、リスク回避の両面で大きな意義があります。一方で、事業者が定める約款は、利用者との情報格差が生じてトラブルに発展するおそれもあります。
このような背景から、2020年4月の民法改正では、定型約款に関するルールが整備されました。特に、「周知による合意」「変更の合理性」「不当な条項の排除」といった利用者を保護するためのルールは、企業が定型約款を適正に運用する上で必ず理解しなければなりません。
事業者側では、自社の利用規約や約款が「定型約款」に該当するかを把握し、法律に沿った運用を徹底することが求められます。また、利用者の理解と納得を得るための丁寧な説明や情報提供が、信頼構築のポイントとなります。
- 定型約款は、民法の要件を満たす場合、個別の合意なく契約内容となる
- 定型約款を契約内容とするには、事前の合意もしくは周知が必要
- 定型約款を変更するには、変更の合理性と事前の周知をしなければならない
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
民法の改正は、契約や取引、債権債務など、生活や企業経営に密接に関わります。改正の内容を正しく把握しなければ、思わぬトラブルを招くおそれもあります。
適切な権利行使をするためにも、民法改正に関する解説記事を通じて、最新のルールを理解しておいてください。