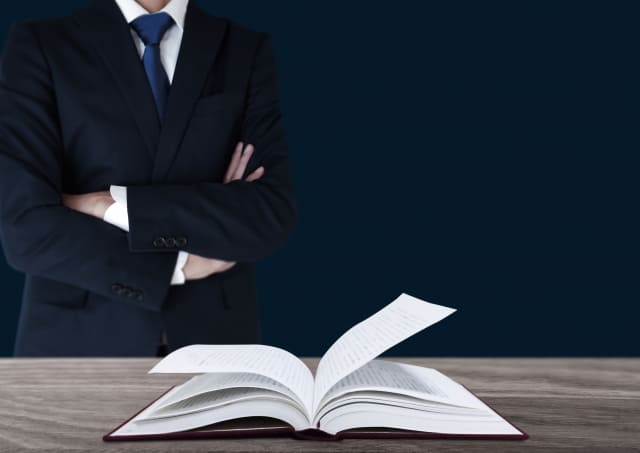危険負担は、片方の債務が帰責事由なく履行不能となったとき、他方の債務が消滅するか、存続するか、という考え方です。例えば、売買契約の締結後、目的物の引渡し前に天災などの不可抗力で滅失した場合、「代金を支払う必要があるのか?」という場面で問題になります。
危険負担の考え方は、契約当事者のどちらが「危険」を「負担」するのかを定めます。
2020年4月の民法改正では、この危険負担のルールが大きく見直され、契約における当事者の責任分配が変更されました。従来の「債権者主義」が取引の常識に反するとして撤廃され、「債務者主義」に転換されたことは、契約実務にも大きな影響を与えます。
今回は、「危険負担とは何か?」という基本知識から、民法改正による具体的な変更点、そして契約実務での注意点まで、弁護士が詳しく解説します。
- 危険負担は、履行不能時の契約当事者のリスク配分を定める制度
- 民法における危険負担は、改正により債務者主義に統一された
- 危険負担は任意規定なので、契約書による変更や修正が可能
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
危険負担とは

危険負担とは、契約の当事者の責めに帰することができない事情で、一方の債務が履行できなくなった場合に、他方の債務がどうなるか(存続するか、それとも消滅するか)についての考え方です。双務契約(売買契約など、双方が債務を負う契約)では、履行不能が発生した場合の責任分配の場面において、危険負担が検討されます。
危険負担は、債権者と債務者の間の公平なリスク配分を目的としており、契約上の義務が履行できなくなったときに、経済的損失を一方のみに負担させることを防ぐ役割を担います。
典型例としては、二者間で売買契約を締結した後、商品の引渡し前に、その商品が天災などの不可抗力で滅失・損傷してしまったケースが挙げられます。売主は引渡し義務を履行できなくなりますが、買主は代金支払い義務を免れるのか、それとも支払わなければならないのか、この判断において、危険負担のルールが重要な役割を果たします。
債権者主義と債務者主義の違い
危険負担の考え方は、大きく分けて「債権者主義」と「債務者主義」の2つがあります。どちらの考え方によるかで、履行不能時の反対給付債務の帰趨が決まります。
なお、危険負担の考え方は、契約の履行前の段階で債務が履行不能となった場合の扱いであり、履行語の問題については「解除」または「契約不適合責任」の考え方で処理します。
債権者主義
債権者主義とは、履行不能により片方の債務が消滅した場合にも、反対給付の債務は残るとする考え方です。つまり、履行不能となった債務の債権者(引渡しを受ける買主など)は、残る債務(代金の支払いなど)を履行しなければなりません。
したがって、債権者主義だと、買主は商品を受け取れないのに、売主に代金を払わなければならず、リスクを「(消滅する債権債務の)債権者」である買主が負うこととなります。
2020年4月施行の改正民法以前は、特定物売買(あらかじめ具体的に特定された物の売買)においては債権者主義が採用されており、その弊害が指摘されていました。
債務者主義
債務者主義とは、債務の履行不能になった場合に、その反対給付の債務も消滅するという考え方です。つまり、履行不能となった債務の債権者(引渡しを受ける買主など)は、自身の債務(代金の支払いなど)を履行しなくてもよくなります。
したがって、債務者主義だと、売主は商品の引渡し義務を果たさなくてよい代わりに、買主も代金支払い義務を負わず、リスクは「(消滅する債権債務の)債務者」である売主が負います。結果的に、買主は何も得られず、また何も失わないことになります。
実際の契約実務や、契約自由の原則にも適合するため、2020年4月の民法改正後は、債務者主義が原則となりました。
具体例における危険負担の考え方
以下の具体例をもとに、危険負担の考え方について詳しく解説します。
A(売主)がB(買主)に、1点物の絵画を100万円で売却するケース。
契約成立後、代金の支払いと絵画の引渡しが行われないうちに、火災が起こって絵画が消失してしまいました。この火災について、売主にも買主にも責任はなく、不可抗力による滅失です。
このとき、債権者主義(従来の民法)と債務者主義(改正後の民法)における結論は、次のように説明することができます。
- 債権者主義の場合
引渡しを受けられないB(買主)は、100万円の代金を支払わなければなりません。したがって、絵画を受け取れないけれど、支払い義務のみ残ることになります。 - 債務者主義の場合
売主Aの引渡義務は履行不能で消滅します。これに伴い、買主Bの代金支払義務も消滅し、双方とも契約上の義務が消滅し、リスクは売主側が負担します。
このように、どちらの立場を採るかで、当事者の経済的負担に差が生じるため、危険負担のルールは契約実務において重要な意義があります。
債権者主義の弊害と改正の経緯
以上のように、従来の民法が採用していた債権者主義は、特定物売買において「目的物がなくなってもなお、代金を払わなければならない」という点で、買主にとってあまりに酷であり、実務にそぐわない面がありました。実際にも、債権者主義を契約書で修正したり、危険負担の移転時期を変更したりといった対応をすることが多いのが実情でした。
そのため、債権者主義のこのような弊害を是正するため、2020年4月1日に施行された改正民法では、債務者主義が原則とされることとなりました。
「民法改正(2020年4月施行)」の解説
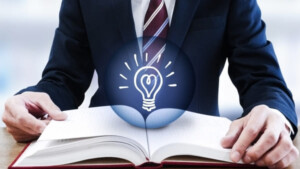
2020年4月の民法改正による危険負担の変更点

2020年4月1日に施行された民法改正により、危険負担に関する規定が大きく見直されました。
改正前の民法の「危険負担」の内容
改正前の民法では、「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合」には、債権者・債務者双方の責に帰すべき事情によらずに目的物が滅失したとき、履行不能となったリスクは不能となった債務の債権者が負担するとされていました(債権者主義)。
債権者主義のルールによると、履行不能となった債務は当然に消滅しますが、債権者側の負う反対債務は消滅せず、変わらず履行する必要があります。これにより「物が滅失したのに、代金は払わなければならない」という買主に酷な事態が生じていました。
なお、「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合」以外は、従来から「債務者主義」が適用されていました。
改正後の民法の「危険負担」の内容
2020年4月の民法改正によって危険負担のルールは債務者主義に変更され、これによって契約当事者間のリスク分担が、より公平かつ明確になり、契約実務での混乱も軽減されると期待されています。主な変更点は、以下の通りです。
債権者主義を廃止して債務者主義に統一
上記の通り、特定物の売買契約などで債権者主義を採用することで生じていた不都合の解消のため、2020年の民法改正で債権者主義は廃止され、債務者主義に統一されました。これによって、売主の責めに帰すべき事由なく目的物が履行不能となった場合、買主は代金支払義務を免れることとなりました。
具体的には、債権者主義について定める民法534条が削除され、債務者主義について定める民法536条が原則とされました。
民法536条(債務者の危険負担等)
1. 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2. 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
民法(e-Gov法令検索)
反対給付債務の履行拒絶権の明文化
改正前の民法では、目的物が滅失・損傷したとき、反対給付債務(買主の代金支払義務)がどう扱われるかが不明確であり、買主が義務を免れるには契約解除が必要とされていました。
改正後の民法536条は、買主は目的物が履行不能となった場合、契約を解除しなくても代金の支払いを拒絶できることを明文化しました。これにより、買主は目的物の引渡しが不可能となった場合、直ちに代金支払義務を拒否できるようになりました。
危険の移転時期の明確化
改正前の民法では、危険が売主から買主に移転する具体的な時期について明確な規定がなく、実務上の解釈や契約上の特約に委ねられていました。
改正後の民法567条では、危険の移転時期が「引渡し時」であることが明文化されました。これにより、目的物の滅失・損傷のリスクは、引渡し前は売主、引渡し後は買主が負担することが明確になりました。
民法567条(目的物の滅失等についての危険の移転)
1. 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2. 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。
民法(e-Gov法令検索)
これまでも、法律の定めにかかわらず、契約によって危険負担の移転時期を「引き渡し時」と定めることが一般的でした。今回の改正で危険の移転時期が明確になり、当事者間のリスク分担が法律上も明瞭になりました。
改正の影響と実務上の注意点

最後に、危険負担についての2020年民法改正の影響と、実務上のポイントを解説します。
民法改正の影響
危険負担についての民法改正は、売主・買主の双方に影響します。
売主への影響と注意点
改正民法が危険負担の原則を債務者主義に統一したことで、引渡し前に目的物が当事者双方の責めに帰すことができない事由で滅失・損傷した場合、売主は引渡義務を免れる一方で、買主は代金支払を拒絶できることとなりました。
この変更で、売主は引渡し前のリスクを負担することになります。特に不動産取引など高額のケースでは、引渡し前の自然災害などで損害が生じると、売主の負担が大きくなります。したがって、売主は引渡し前のリスク管理を徹底し、必要に応じて保険に加入したり契約条項に特約を定めたりして、リスク管理を徹底する必要があります。
買主への影響と注意点
買主にとっては、引渡し前に目的物が滅失・損傷した場合に代金支払義務を拒絶できるようになったことは、リスク軽減となります。ただ、契約書で危険負担に関する特約を定めた場合、買主のリスクが増す危険があります。
したがって、買主の立場では、契約締結時に危険負担に関する条項をよく確認し、不明な点は修正したり、説明を求めたりすることが重要です。
契約書作成時の注意点
契約書作成時には、危険負担についての法改正を踏まえ、当事者間のリスク分担を明確にしなければなりません。危険負担に関する民法の規定は「任意規定」なので、当事者間で異なる特約を設けることが可能です。例えば、契約書で次のように約束する例があります。
- 危険の移転時期の明確化
民法改正で、危険の移転時期が「引き渡し時」とされたものの、契約で「検査合格時」や「代金支払い時」に修正する例があります。また、「引き渡し時」のままだとしても、「当事者のどのような行為が『引き渡し』と評価されるのか」が争われる危険があるので、契約書で、より詳細に記載しておくのが有効です。 - 損傷時の対応策
引渡し前に目的物が損傷した場合の対応策(修補、代金減額、契約解除など)を契約書に明記することで、当事者間の対応が迅速かつ円滑に行えます。 - 保険の加入状況の確認
売主が引渡し前のリスクを負担するために、目的物に保険を付した場合、その内容や保険金の受取人、保険金の取扱いを契約書に明記するケースがあります。
なお、危険の移転時期については、売主にとってはより早い時期、買主にとってはより遅い時期の方が有利なので、契約締結前によく交渉を行う必要があります。
まとめ

今回は、危険負担の考え方について、民法改正も踏まえて解説しました。
危険負担は、売買契約などにおいて、目的物の引渡し前に滅失・損傷があった場合のリスクをどちらの当事者が負うかを定める考え方です。2020年4月の民法改正により、これまでの「債権者主義」から「債務者主義」へとルール変更され、買主に不利益が及ぶ場面が大幅に見直されました。
従来の「債権者主義」では、特定物売買について「商品が手に入らなくても代金を支払わなければならない」という不都合が生じましたが、実務の常識に合わせて「債務者主義」に修正され、引渡し前に目的物が滅失した場合は、買主は代金支払義務を負わないことが明文化されました。この改正に伴い、実務においても契約書の見直しやリスク管理の検討が必須となります。
契約の当事者にとって、危険負担の理解は、紛争を未然に防ぐのに欠かせません。法改正の趣旨を理解し、弁護士に契約書のチェックを依頼するなど、慎重な対応が求められます。
- 危険負担は、履行不能時の契約当事者のリスク配分を定める制度
- 民法における危険負担は、改正により債務者主義に統一された
- 危険負担は任意規定なので、契約書による変更や修正が可能
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
民法の改正は、契約や取引、債権債務など、生活や企業経営に密接に関わります。改正の内容を正しく把握しなければ、思わぬトラブルを招くおそれもあります。
適切な権利行使をするためにも、民法改正に関する解説記事を通じて、最新のルールを理解しておいてください。